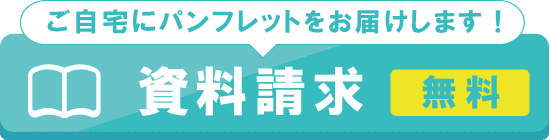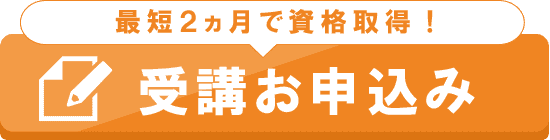幼児期のおやつの目的や与えるポイント
おやつといえば、大人にとってはちょっとしたリラックスタイムですが、子どもにとってのおやつは身体と心を成長させるために非常に重要な存在です。しかし、親にとっておやつの食べ過ぎはちょっと気になるところ。今回は幼児期におやつを食べる目的やおやつを与えるときのポイントについてご紹介します。
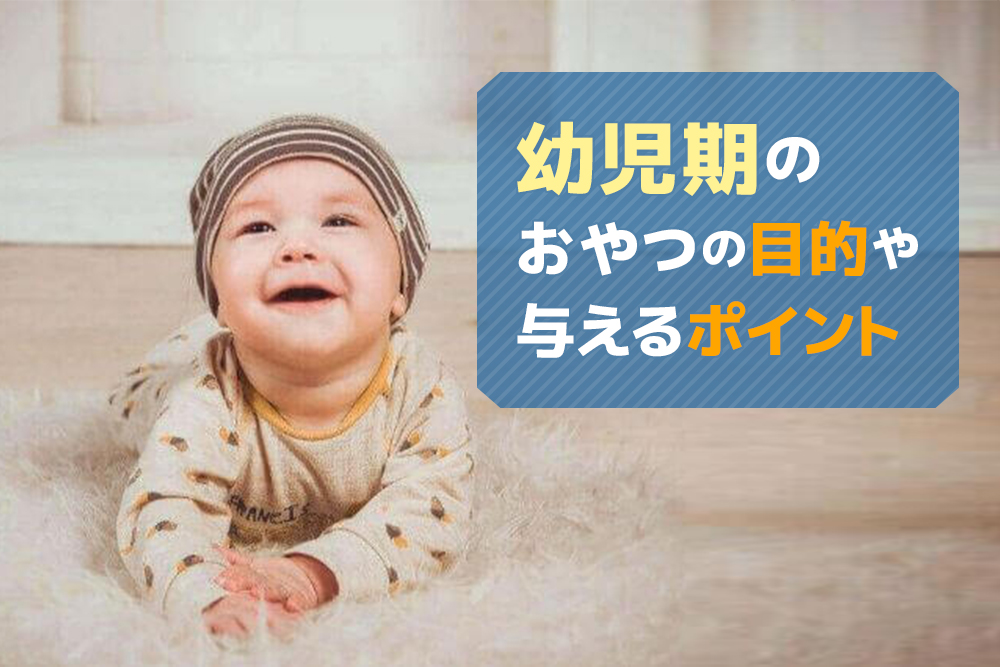
01幼児期のおやつの目的
離乳食を終えて、幼児食に入るときにはおやつの重要性も高まります。それでは、幼児期におやつを食べることにはどのような目的があるのでしょうか。
1-1食事で取りきれなかった栄養の補給源
幼児期のおやつには「食事で取り切れなかった栄養の補給源」という意味があります。子どもの身体はまだまだ未発達で、一度にたくさん食べても、胃や腸はそれらを消化・吸収することができません。また、食べ物を噛む力や飲み込む力、唾液を作る力も弱いので、食べるためには非常に時間がかかってしまいます。そうなると子どもは食事を食べることに疲れたり、飽きたりして、なかなか食事だけではきちんと栄養を補給することができなくなってしまいます。
そこで重要になるのがおやつ。子どもにとっておやつは「リラックスするため」「休憩するため」「気分転換するため」というよりも、軽い食事。この食事によって、子どもは食事では取り切れない栄養を補給し、身体を健康に成長させることができます。
1-2おやつの適量は1日の栄養量の10~20%が目安
おやつは子どもにとっては重要な栄養源。しかし、だからといっていくらでも食べていいというわけではありません。おやつの適量は1日の栄養量の10~20%が目安といわれています。
ただし、栄養学の専門家でもない人にとって、「1日の栄養量の10~20%」と言われてもなかなか難しいもの。
もし、どのようなおやつをどれぐらい与えたらいいのか分からないと言う場合には、ビタミンやミネラルといった不足しがちな栄養素や、食事のときに何を残したのかに注目するという方法があります。
たとえば盛り付けた分のご飯を残していたと言う場合には、残した分のご飯をおにぎりにする、同じくらいの量のパンなどを与える、昼食で乳製品が足りなかったとすれば、牛乳やヨーグルト、チーズなどを与えるなど、その日の食事のバランスを考えながら、不足した分をおやつに与えるとちょうどいい量になるでしょう。
02理想的なおやつとは
子どもにはおやつも重要な栄養源になります。それでは、子どもの成長に役立つ理想的なおやつとはどのようなものなのでしょうか。
2-1夕食までエネルギーをもたせるためのもの
おやつに対する考え方として、「夕食までのエネルギーをもたせるもの」と考えることもできます。多くの家庭では、午後三時におやつの時間というところも多いかと思います。そのときにおやつを食べ過ぎると、どうしても夕食に影響してしまうもの。そのため、午後三時のおやつは夕食までのエネルギーをもたせるための、フルーツや野菜スティックなど、軽めのものを与えると、夕食の頃にはもう一度食欲を感じて、きちんとご飯も食べられることにつながります。
2-2食事で取りきれなかった栄養を補えるもの
おやつには食事で取り切れない栄養素を補うという役割があります。幼児期に必要な栄養素には、身体を動かすための炭水化物、筋肉などの材料になるたんぱく質、身体の機能を正常に保つビタミン、腸の動きを活発にする食物繊維などが挙げられます。また、子どもの成長にとってはカルシウムや鉄分といったミネラルも重要になります。朝昼晩の食事だけでは、これらすべてを補給するのはなかなか難しいもの。そのため、食物繊維が不足していると感じる場合にはさつまいも、ビタミンが不足しているなと思ったらフルーツなど、不足している栄養素を補う感覚でおやつを与えることで、子どもに足らない栄養素を補給、健やかな成長を支えることができます。
2-3朝昼晩の食事に響かないようにする
おやつは子どもにとって必要なものですが、成長するにしたがって、三度の食事だけできちんと栄養が取れるような食習慣を作っていくことも必要です。そのため、おやつを食べるときには食事に響かないようにすることも大切。できれば、一日1~2階、食事との間隔が2~3時間あくのが理想的。ただし、これはあくまでも一つの目安。無理に食事の時間を空けようとして、夕食が遅くなると、今度は次の朝食に影響が出てしまいます。
1-1食事で取りきれなかった栄養の補給源
幼児期のおやつには「食事で取り切れなかった栄養の補給源」という意味があります。子どもの身体はまだまだ未発達で、一度にたくさん食べても、胃や腸はそれらを消化・吸収することができません。また、食べ物を噛む力や飲み込む力、唾液を作る力も弱いので、食べるためには非常に時間がかかってしまいます。そうなると子どもは食事を食べることに疲れたり、飽きたりして、なかなか食事だけではきちんと栄養を補給することができなくなってしまいます。
そこで重要になるのがおやつ。子どもにとっておやつは「リラックスするため」「休憩するため」「気分転換するため」というよりも、軽い食事。この食事によって、子どもは食事では取り切れない栄養を補給し、身体を健康に成長させることができます。
1-2おやつの適量は1日の栄養量の10~20%が目安
おやつは子どもにとっては重要な栄養源。しかし、だからといっていくらでも食べていいというわけではありません。おやつの適量は1日の栄養量の10~20%が目安といわれています。
ただし、栄養学の専門家でもない人にとって、「1日の栄養量の10~20%」と言われてもなかなか難しいもの。
もし、どのようなおやつをどれぐらい与えたらいいのか分からないと言う場合には、ビタミンやミネラルといった不足しがちな栄養素や、食事のときに何を残したのかに注目するという方法があります。
たとえば盛り付けた分のご飯を残していたと言う場合には、残した分のご飯をおにぎりにする、同じくらいの量のパンなどを与える、昼食で乳製品が足りなかったとすれば、牛乳やヨーグルト、チーズなどを与えるなど、その日の食事のバランスを考えながら、不足した分をおやつに与えるとちょうどいい量になるでしょう。
2-1夕食までエネルギーをもたせるためのもの
おやつに対する考え方として、「夕食までのエネルギーをもたせるもの」と考えることもできます。多くの家庭では、午後三時におやつの時間というところも多いかと思います。そのときにおやつを食べ過ぎると、どうしても夕食に影響してしまうもの。そのため、午後三時のおやつは夕食までのエネルギーをもたせるための、フルーツや野菜スティックなど、軽めのものを与えると、夕食の頃にはもう一度食欲を感じて、きちんとご飯も食べられることにつながります。
2-2食事で取りきれなかった栄養を補えるもの
おやつには食事で取り切れない栄養素を補うという役割があります。幼児期に必要な栄養素には、身体を動かすための炭水化物、筋肉などの材料になるたんぱく質、身体の機能を正常に保つビタミン、腸の動きを活発にする食物繊維などが挙げられます。また、子どもの成長にとってはカルシウムや鉄分といったミネラルも重要になります。朝昼晩の食事だけでは、これらすべてを補給するのはなかなか難しいもの。そのため、食物繊維が不足していると感じる場合にはさつまいも、ビタミンが不足しているなと思ったらフルーツなど、不足している栄養素を補う感覚でおやつを与えることで、子どもに足らない栄養素を補給、健やかな成長を支えることができます。
2-3朝昼晩の食事に響かないようにする
おやつは子どもにとって必要なものですが、成長するにしたがって、三度の食事だけできちんと栄養が取れるような食習慣を作っていくことも必要です。そのため、おやつを食べるときには食事に響かないようにすることも大切。できれば、一日1~2階、食事との間隔が2~3時間あくのが理想的。ただし、これはあくまでも一つの目安。無理に食事の時間を空けようとして、夕食が遅くなると、今度は次の朝食に影響が出てしまいます。
03おやつの与え方のポイント
幼児期は将来の食習慣の基礎を作るための大切な時期。そのため、おやつの与え方や食べ方にルールを作ることも必要です。
3-1おやつの時間を決める
まず必要なのは「おやつの時間を決める」ということ。栄養補給が必要だからと、子どもおやつを欲しがったときに常に何かを与えていると、だらだら食べの状態になり、食事のときにお腹が空かなくなるだけでなく、消化や吸収を行い続けなければならなくなって、胃や腸に負担がかかり続けてしまいます。また、歯を磨いてもすぐに何かを口に入れてしまうと虫歯の原因になることもあります。
おやつを食べるときには時間を決めて、少しお腹が空いても我慢することを教えましょう。慣れないうちは難しいものですが、子どもが「お腹を減らしてからご飯を食べると美味しい」と気づいてくれると、それからは食べることが好きな子どもになってくれます。
3-2ガム、あめ、ナッツ類、白玉もち、こんにゃく入りゼリーは3歳頃まで与えない
ガムやあめ、ナッツ類などは大人のおやつの定番ですが、子どもに対しては少なくとも3歳を過ぎる頃までは与えないようにしましょう。そのほかにも、白玉餅やこんにゃく入りゼリーなども、喉を詰まらせる危険があります。大人であれば、少し喉に詰まっても力を入れれば飲み込むことができますが、子どもの場合は飲み込む力もまだまだ弱く、のども細いため、すぐに食べ物を詰まらせてしまいます。
また、ピーナッツなどのナッツ類は、水分が少ないため口の中でまとまりにくく、息を吸ったりしたときに破片が気管に入ってしまう「誤嚥」の原因になります。誤嚥を起こしてしまうと、それが原因で肺炎になってしまうこともあるため、注意が必要です。また、ピーナッツなどはアレルギーの原因となることもあります。
3-3ながら食べをさせない
おやつを食べるときには、テレビを見ながら、遊びながらといった「ながら食べ」は避けましょう。ながら食べをすると、注意力が分散され、食べた気がせずに必要以上の量を食べてしまう原因となります。
3-4できるだけ市販のお菓子に頼らない
おやつを選ぶときには、できるだけ市販のお菓子は避けたほうがいいでしょう。特にケーキやチョコレートは、脂質や糖質が多いため、すぐに満腹になってしまうだけでなく、なかなか消化できないことからその後の食事に響いてしまいます。また、味の濃いものを与えていると、それが癖になってしまい、薄味なものを嫌いになってしまうという可能性もあります。
そのほかにも、市販のお菓子には添加物などが含まれていることもあるため、できることならふかしたお芋やおにぎり、フルーツなどを与えるようにしましょう。
3-51回に食べる量だけお皿に出す
おやつを食べるときには、1回に食べる量だけをお皿に出すようにしましょう。これ以上は食べたらダメという線をはっきりさせることで、子どもは自然とおやつを食べるマナーを身につけることができます。
04まとめ
大人とは異なり、栄養補給と言う大切な役割のある子どものおやつ。食事の基礎を作る上でも大切な存在となるため、しっかりと親が管理してあげることも必要になります。
3-1おやつの時間を決める
まず必要なのは「おやつの時間を決める」ということ。栄養補給が必要だからと、子どもおやつを欲しがったときに常に何かを与えていると、だらだら食べの状態になり、食事のときにお腹が空かなくなるだけでなく、消化や吸収を行い続けなければならなくなって、胃や腸に負担がかかり続けてしまいます。また、歯を磨いてもすぐに何かを口に入れてしまうと虫歯の原因になることもあります。
おやつを食べるときには時間を決めて、少しお腹が空いても我慢することを教えましょう。慣れないうちは難しいものですが、子どもが「お腹を減らしてからご飯を食べると美味しい」と気づいてくれると、それからは食べることが好きな子どもになってくれます。
3-2ガム、あめ、ナッツ類、白玉もち、こんにゃく入りゼリーは3歳頃まで与えない
ガムやあめ、ナッツ類などは大人のおやつの定番ですが、子どもに対しては少なくとも3歳を過ぎる頃までは与えないようにしましょう。そのほかにも、白玉餅やこんにゃく入りゼリーなども、喉を詰まらせる危険があります。大人であれば、少し喉に詰まっても力を入れれば飲み込むことができますが、子どもの場合は飲み込む力もまだまだ弱く、のども細いため、すぐに食べ物を詰まらせてしまいます。
また、ピーナッツなどのナッツ類は、水分が少ないため口の中でまとまりにくく、息を吸ったりしたときに破片が気管に入ってしまう「誤嚥」の原因になります。誤嚥を起こしてしまうと、それが原因で肺炎になってしまうこともあるため、注意が必要です。また、ピーナッツなどはアレルギーの原因となることもあります。
3-3ながら食べをさせない
おやつを食べるときには、テレビを見ながら、遊びながらといった「ながら食べ」は避けましょう。ながら食べをすると、注意力が分散され、食べた気がせずに必要以上の量を食べてしまう原因となります。
3-4できるだけ市販のお菓子に頼らない
おやつを選ぶときには、できるだけ市販のお菓子は避けたほうがいいでしょう。特にケーキやチョコレートは、脂質や糖質が多いため、すぐに満腹になってしまうだけでなく、なかなか消化できないことからその後の食事に響いてしまいます。また、味の濃いものを与えていると、それが癖になってしまい、薄味なものを嫌いになってしまうという可能性もあります。
そのほかにも、市販のお菓子には添加物などが含まれていることもあるため、できることならふかしたお芋やおにぎり、フルーツなどを与えるようにしましょう。
3-51回に食べる量だけお皿に出す
おやつを食べるときには、1回に食べる量だけをお皿に出すようにしましょう。これ以上は食べたらダメという線をはっきりさせることで、子どもは自然とおやつを食べるマナーを身につけることができます。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。
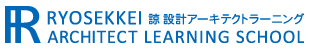
- 幼児の食育に関わる資格について
- 幼児食の鉄分の重要性!正しい摂取方法やおすすめレシピを紹介
- 幼児食に適した食材!適切な食事のポイントや注意点を解説
- 幼児食のそばデビューと注意点
- 幼児の食事マナーのしつけ方
- 幼児期の偏食について
- 幼児の牛乳の飲み方について
- 幼児のダイエットの目安は?やり方や注意点を伝授
- 風邪をひいたときの幼児食とは?食材やおすすめメニューを紹介
- 幼児食の味付けについての基本的な知識や注意点
- 幼児食についての基本的な知識!幼児食はいつからはじめる?
- 幼児食で上手に野菜を取り入れる!おいしく食べられるテクニックやコツ!
- 幼児期のお弁当におすすめの工夫やポイント
- 幼児期のおやつの目的や与えるポイント
- 幼児期に適切な食事の量や注意点
- 幼少期からの朝ごはんの習慣づくりとは?子供の心身の健やかな成長に!
- 幼児期に使用する食器の選び方!注意点やおすすめ食器素材を紹介
- これなら簡単!すぐに作れる幼児食の紹介や取り分けをする時のコツ
- 幼児食資格のおすすめ10選!最短2ヵ月で取得する方法も解説