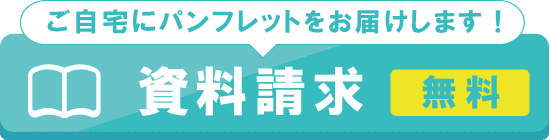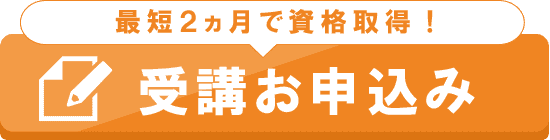幼児食に適した食材!適切な食事のポイントや注意点を解説
幼児期は食習慣を形成する大切な時期です。
適切な食材選びと調理が重要です。
軟らかく咀嚼しやすい食材、栄養バランスの良い組み合わせ、アレルギー対応、害物質の排除などに気をつける必要があります。
食事時間を楽しく過ごすことで、幼児の食への興味と好奇心を育むことができるでしょう。
幼児食選びのポイントを理解し、幼児の健やかな成長を支援することが大切です。
子どもにはきちんとした幼児食を食べさせたいものですが、作るとなると難しいのが難点。大人と同じものを食べていいのかなど悩んでいる方も多いかもしれません。では、幼児食はどのような食材を使い、どう作ればいいのでしょうか。今回は幼児食の作り方や適した食材についてご紹介します。

- 目次
- 1. 幼児期の適切な食事の重要性
- 2. 幼児食を食べるタイミングとは?
- 2-1. 月齢に合わせた食事回数
- 2-2. 離乳食から幼児食への移行
- 2-3. 間食の役割と注意点
- 3. 幼児食に適した主な食材
- 3-1. 穀物類
- 3-2. 肉類
- 3-3. 魚介類
- 3-4. 卵類
- 3-5. 豆類
- 3-6. 乳製品
- 3-7. 野菜
- 3-8. 果物
- 4. 適切な食事のポイント
- 4-1. 1食の量
- 4-2. 彩りや食感への配慮
- 4-3. 噛む力を鍛える食材
- 4-4. 糖分の控えめ
- 5. 幼児食に関する注意点
- 5-1. アレルギー対応
- 5-2. 好き嫌いへの対応
- 5-3. 旬の食材の活用
- 5-4. 食品添加物への配慮
- 6. 幼児食を食べるタイミング
- 7. 幼児食をつくるときのポイント
- 8. 幼児食に適した食材
- 9. 幼児食に適さない注意食材
- 10. まとめ
01幼児期の適切な食事の重要性
01幼児食を食べるタイミングとは?
1-1月齢に合わせた食事回数
幼児の食事時間は月齢に合わせて調整することが大切です。 生後6か月頃から離乳食を始め、1歳頃までに3回の食事と2回の間食を取るのが良いとされています。 2歳頃になると、食事は3回、間食は1-2回が適切です。 乳幼児期は成長の著しい時期のため、小食になりがちです。 空腹感を感じる前に食事を摂れるよう、規則正しい食事リズムを作ることが重要です。 また、幼児期は食べる量が変わりやすいため、柔軟な対応が必要でしょう。 子どもの様子を見ながら、無理せず食事のタイミングと量を調整しましょう。 こうした食事のリズムと量の調整によって、幼児期から健やかな成長につながります。
1-1離乳食から幼児食への移行
幼児食への移行は、離乳食から段階的に行うことが大切です。 生後6か月頃から開始する離乳食は、ペースト状のものから始めて徐々に固さや大きさを増していきます。 1歳頃になると、家族と一緒に食べるテーブルフードへと移行します。 この時期は、赤ちゃんの咀嚼能力の発達に合わせて食材の大きさや固さを調整する必要があるでしょう。 2歳頃になると、完全に幼児食に移行します。 3回の食事と1-2回の間食が基本となり、家族の食事と同じようなメニューを提供します。 幼児期は味覚が発達し、食べ物への好みが出てくる時期です。 食事の時間を楽しい時間にするため、子どもの好みに合わせたメニューを工夫することが大切です。 このように、月齢に合わせて食事形態を変えていくことで、幼児期の健全な発達を促すことができるでしょう。
1-1間食の役割と注意点
幼児期の間食は、成長に必要な栄養を補う重要な役割があります。 しかし、間食の取り方を誤ると、食欲の低下や偏食につながるリスクがあるため、適切な管理が求められます。 1-2歳頃の幼児は、1回の食事量が少ないため、間食を上手に活用することで、必要な栄養を確保できるでしょう。 間食には、牛乳、ヨーグルト、フルーツ、野菜スティックなど、栄養価の高い食品を選ぶことが重要です。 一方で、間食の与え方には注意が必要です。 間食の時間や量を適切に管理しないと、食事の時間に影響し、食欲の低下を招くことがあります。 また、甘い菓子類を与えすぎると、偏った嗜好につながる可能性もあります。 幼児の発達段階に合わせて、間食の時間と内容を検討し、バランスのよい食生活を心がけることが、健やかな成長につながるでしょう。
01幼児食に適した主な食材
1-1穀物類
・米 幼児の主食の中心となる食品です。 消化吸収が良く、ビタミンB1、鉄分などが含まれています。 ・パン 食べやすい食感で、幼児も食べやすい食品です。 小麦粉には良質なたんぱく質が含まれています。 ・麦 大麦、そば、コーンなどの雑穀は食物繊維が豊富で、幼児の健康的な成長を支えます。 ・いも類 じゃがいも、さつまいもなどは、ビタミンやミネラルが豊富で、幼児の成長に適しています。 これらの穀物類は、幼児の消化吸収に適した食感や形状が特徴で、組み合わせることで栄養バランスの良い食事が可能です。
1-1肉類
・牛肉 鉄分やビタミンB12が豊富で、幼児期の発育に重要な栄養素を多く含んでいます。 赤身肉がおすすめです。 ・鶏肉 たんぱく質が高く、消化吸収も良いため、幼児の主な肉類の1つとなります。 ・豚肉 脂肪分が適度に含まれ、食べやすい食感が特徴です。 ただし、脂肪分が高いため、量や調理方法に注意が必要です。 ・魚類 ビタミンやミネラル、DHA、EPAなどの良質な脂肪酸を含んでいるため、積極的に取り入れましょう。 骨部分は食べにくい可能性があるため、骨なしの切り身がおすすめです。 これらの肉類は、幼児の成長に重要な栄養素を多く含んでいます。
1-1魚介類
・サケ DHA、EPAなどの良質な脂肪酸が豊富で、脳の発達に重要です。 骨軟骨部分も食べられるため、カルシウムの摂取にも適しています。 ・カツオ たんぱく質が高く、ビタミンB群も豊富です。 しっかりと火を通すことで、骨部分も食べやすくなります。 ・ホタテ 鉄分やビタミンB12が豊富で、貧血予防に効果的です。 加熱処理をすれば、食べやすい食感になります。 ・かれい アレルギー物質が少なく、消化吸収も良いため、アレルギーのある幼児にも適しています。 これらの魚介類は、幼児期の成長に欠かせない栄養素を多く含んでいます。
1-1卵類
・鶏卵 たんぱく質が高く、バランスの良い必須アミノ酸を含んでいます。 卵黄にはビタミンやミネラルが豊富で、幼児の成長に欠かせません。 ・うずら卵 鶏卵に比べて、小さな大きさなので幼児にも食べやすいです。 栄養面でも鶏卵とほぼ同等の価値があります。 ・卵加工品 卵焼き、目玉焼き、とろとろの卵スープなど、幼児が食べやすい調理法があります。 食べやすい食感と栄養価の高さから、幼児にぴったりの食材です。 これらの卵類は、幼児の骨や筋肉の発達、免疫力の向上に重要な役割を果たします。 調理の工夫で食べやすさも高まるため、様々な卵料理を取り入れましょう。
1-1豆類
・大豆 たんぱく質が豊富で、必須アミノ酸のバランスが良好です。 カルシウムやマグネシウム、食物繊維なども含んでいます。 ・枝豆 豆の食感が柔らかく、幼児でも食べやすい一方で、栄養価も高いです。 特にビタミンC、葉酸、鉄分が豊富に含まれています。 ・金時豆 食物繊維が豊富で、便秘予防に効果的です。 調理すると柔らかくなり、幼児の歯ぐきでも噛み砕きやすくなります。 ・豆腐 たんぱく質が豊富で消化吸収が良く、幼児の成長に重要な栄養素を含んでいます。 食感が柔らかいため、幼児でも食べやすい一品です。 これらの豆類は、幼児の健康的な発育に寄与する優れた食材です。
1-1乳製品
・牛乳 カルシウムやビタミンDが豊富で、骨の発達に重要です。 たんぱく質も高く、幼児の成長に不可欠な栄養素を含んでいます。 ・ヨーグルト 善玉菌を含むため、腸内環境の改善に効果的です。 カルシウムやたんぱく質も豊富で、成長期の幼児に適しています。 ・チーズ カルシウムの濃縮された食品で、骨の発達に最適です。 脂肪分が多いため、エネルギー源としても期待できます。 ・バター 脂肪分が豊富で、エネルギー、ビタミンA、Dの良い供給源です。 食感が滑らかなため、幼児でも食べやすい一品です。 これらの乳製品は、幼児の健やかな成長に不可欠な栄養素を多く含んでいます。
1-1野菜
・緑黄色野菜 ビタミンA、C、食物繊維が豊富です。 視力や免疫機能の向上に役立ちます。 ・根菜類 カロテノイド、ビタミンB、食物繊維が含まれています。 消化吸収が良く、幼児の成長に寄与します。 ・葉野菜 カルシウム、鉄分、葉酸が豊富で、骨の発達や貧血予防に効果的です。 食べやすい調理法を工夫すれば、幼児も喜んで食べられるでしょう。 ・きのこ類 ビタミンB、ミネラルが豊富で、免疫力の向上に寄与します。 柔らかな食感が、幼児にも適しています。 これらの野菜は、幼児の健康的な発育に重要な役割を果たします。
1-1果物
・柑橘類 ビタミンC、食物繊維が豊富で、免疫力の向上や便秘予防に効果的です。 皮膜が柔らかく、幼児でも食べやすい。 ・りんご 食物繊維が豊富で、消化吸収が良好です。 歯ぐきでつぶしやすく、幼児の食べやすさにも適しています。 ・バナナ カリウム、ビタミンB6が豊富で、成長期に不可欠な栄養素を含みます。 軟らかい食感が幼児に合っています。 ・キウイフルーツ ビタミンC、食物繊維が豊富で、免疫力の向上や便秘予防に役立ちます。 酸味が穏やかなため、幼児でも食べやすい。 これらの果物は、幼児の健康的な発育に重要な役割を果たします。
01適切な食事のポイント
1-11食の量
幼児の適切な食事の量は、年齢や成長段階によって異なります。 1食の量は、幼児の胃の大きさを考慮して適切に設定する必要があるでしょう。 1〜2歳児では、おにぎり1個分程度、コップ1/2〜3/4杯分が目安です。 3〜5歳児では、おにぎり1〜1.5個分、コップ3/4〜1杯分が目安です。 食べ残しが多い場合は、1食の量を減らすことで食べ残しを防ぐことができ、逆に、食べ終わってしまう場合は、1食の量を少し増やすことをおすすめします。 成長に合わせて、1食の量を徐々に増やしていくことが大切です。 無理に多く食べさせるのではなく、子どもの食欲に合わせて柔軟に対応することが重要です。 量は子どもによって異なりますが、バランスのよい食事を心がけることで、健やかな成長が期待できるでしょう。
1-1彩りや食感への配慮
幼児の適切な食事には、彩りや食感への配慮が大切です。 まず、料理の彩りに気をつけることが重要です。 赤・黄・緑などの色彩豊かな野菜や果物を組み合わせることで、見た目の楽しさが生まれます。 彩りの良い料理は、幼児の食欲を刺激し、楽しい食事につながります。 次に、食感の変化を取り入れることが大切です。 軟らかい食材と、歯ごたえのある食材を組み合わせることで、食べ応えのある料理になります。 幼児の咀嚼力に合わせて、適度な固さの食材を選ぶことが重要です。 さらに、温かさや冷たさの違いも取り入れると良いでしょう。 温かい料理と冷たいデザートなど、温度差のある料理は食べ応えがあります。 これにより、幼児の食への興味を引き出すことができます。 彩りと食感への配慮は、幼児の食事をより楽しいものにしてくれます。 楽しい食事は、豊かな心と健康な体づくりにつながるでしょう。
1-1噛む力を鍛える食材
幼児期は、噛む力を鍛える大切な時期です。適切な食材選びが重要です。 まず、硬めの食材は噛む力を鍛えることができます。 ニンジンやりんごなどの生野菜、海藻類、干し芋などがおすすめです。 これらの食材を上手に噛むことで、歯の発達や咀嚼力の向上が期待できます。 次に、ゼリー状の食材も噛む力を鍛えるのに適しています。 こんにゃくやゼラチンなどのゼリー状の食材は、噛んでいくうちに固さが変化し、この変化に合わせて噛むことで、噛む力が養われます。 さらに、食材の形状にも配慮すると良いでしょう。 食べづらい形状の食材は、噛む回数が増え、噛む力の向上につながり、角切りや棒状の食材など、噛みごたえのある形状がおすすめです。 このように、噛む力を鍛える食材を取り入れることで、幼児期の健全な成長が期待できます。 無理のない範囲で、徐々に噛む力を高めていくことが大切です。
1-1糖分の控えめ
幼児期の適切な食事では、糖分の控えめが重要なポイントとなります。 糖分は子供の成長や発達に影響を及ぼす可能性があり、過剰な糖分摂取は、肥満や虫歯、生活習慣病のリスクを高めるため、控えめにする必要があるでしょう。 具体的には、菓子やジュース、清涼飲料水などの糖分の多い食品の摂取を控え、代わりに、フルーツやヨーグルト、牛乳などの自然な糖分を含む食品を選ぶことをおすすめします。 また、調理時の砂糖の使用量にも気をつける必要があります。 料理に砂糖を加える場合は、できるだけ控えめにし、代わりに甘味料の使用を検討しましょう。 幼児期は、正しい食習慣を身につける大切な時期です。 糖分の適切な摂取は、健康的な成長につながります。
01幼児食に関する注意点
1-1アレルギー対応
幼児期のアレルギー対応は、食事管理の大切なポイントです。 まず、幼児のアレルギー症状を早期に発見することが重要です。 乳幼児期は食物アレルギーが多くみられるため、食事の際には注意深く観察し、症状が見られた場合は、早めに医療機関に相談することが大切でしょう。 次に、アレルギーの原因となる食材を特定し、除去することが重要です。 卵、乳製品、小麦、そば、落花生など、一般的なアレルギー引き金食材に気をつける必要があり、除去する際は、代替食材の選定も行い、栄養面での偏りを防ぐようにします。 また、調理の際も十分な気をつけが必要です。 アレルギー物質の交差汚染を防ぐため、調理器具の洗浄や調理動線に注意を払い、他の家族分と完全に分離して調理することが理想的です。 幼児期のアレルギー対応には細心の注意が必要ですが、適切な管理により、健康的な成長が期待できるでしょう。
1-1好き嫌いへの対応
幼児期の好き嫌いへの対応は、適切な食生活を送るうえで重要なポイントです。 まずは、幼児の好み・嫌いを理解し、尊重することが大切です。 無理に好きではない食べ物を摂取させるのではなく、子供の意向を確認しながら進めましょう。 次に、徐々に食べ物への慣れを促すことが効果的です。 嫌いな食材を少しずつ混ぜたり、調理方法を変えたりするなど、段階的にアプローチします。 嫌いな食材でも、楽しく食べられるようになるまで、根気よく取り組みましょう。 また、楽しい食事の時間を大切にすることも重要です。 家族揃って会話を弾ませたり、食事を楽しむ工夫をするなど、食事を楽しむ工夫をし、食事への良い思い出が、好き嫌いの改善につながります。 幼児期の好き嫌いへの対応には、時間と労力がかかりますが、バランスの取れた食生活を送るためには欠かせないポイントです。
1-1旬の食材の活用
幼児期の食事に旬の食材を活用することは、健康的な成長につながります。 旬の食材は、季節によって変わりますが、その時期に最も栄養価が高く、新鮮な状態で入手できます。 旬の食材を使うことで、幼児に必要な栄養素を効率的に取り入れることができるでしょう。 また、季節感のある食事は、子供の感性も育むことができます。 春には新鮮な野菜、夏には果物、秋には収穫物など、季節ならではの食材を楽しむことで、食への興味関心を高めることができるでしょう。 さらに、旬の食材を活用することで、食材費の節約にもつながり、その時期に一番豊富な食材を選ぶことで、無駄なく経済的な食事が可能になります。 幼児期は食生活の基盤が作られる大切な時期です。 旬の食材を活用し、楽しみながら栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。
1-1食品添加物への配慮
幼児期は成長が著しい時期であり、食品添加物への配慮が重要です。 食品添加物には、香料、保存料、着色料など様々な種類がありますが、それらの中にはアレルギー反応を引き起こすものや、健康への影響が懸念されるものもあり、幼児の体は成長過程にあるため、食品添加物の影響を受けやすい可能性があります。 そのため、幼児の食事作りには、添加物の少ない食材を選ぶことが大切です。 例えば、加工食品の代わりに新鮮な食材を使うことで、添加物の量を抑えることができます。 また、食品表示を確認し、添加物の種類や量に注意を払いましょう。 さらに、幼児の食事は家庭で手作りすることをおすすめします。 自分で調理することで、好みの食材を使い、添加物の量を管理することができます。 幼児期は、健全な食生活の基礎を築く大切な時期です。
01幼児食を食べるタイミング
離乳食から大人の食事までの間の食事である幼児食は、何を目安に食べさせればよいのでしょうか。
1-11~1歳半を過ぎるころ
幼児食を始めるのは、通常1~1歳半を過ぎるころから食べさせるものとされています。
目安としては、一日三度の食事に慣れていることや、奥歯で食べ物をすりつぶして飲み込むことができるようになっていること、水分などの飲み物をコップから飲めるようになっていることなどが挙げられます。
ただし、子どもの成長には個人差が大きいもの。年齢はあくまでもひとつの目安です。
そのため、子どもの成長に合わせて提供するのがよいでしょう。
1-21~2歳児の1食分のカロリー摂取目安は300kcal、3~5歳児の1食分のカロリー摂取目安は400kcal
幼児食は、離乳食を卒業したあと、大人と同じものが食べられるようにする準備期間。しかし、この時期は子どもの成長にも重要な時期です。そのため、しっかりした栄養を取らせたり、たくさん食事を与えたりといったことに目が行きがちですが、食べ過ぎると肥満も心配になるものです。
もし食べる量が分からないというときには、カロリーを基準にするという方法もあります。
一般的に、1~2歳児の1食分のカロリー摂取目安は300kcal、3~5歳児の1食分のカロリー摂取目安は400kcalといわれています。そのため、もし食べる量が分からない場合、これらのカロリーが足りているか、取りすぎていないかを考えるとよいでしょう。
ただし、このカロリーも目安のひとつ。綿密なカロリー計算はかなり面倒なものでもあるため、あくまでも基準のひとつと考えるとよいでしょう。
1-3食欲がない、食べ過ぎたときは翌日の食事で調整する
子ども限らず、人間はその日の体調や天候によって食欲が左右されるもの。また、環境によっても食欲が上下します。
特に幼児食は、子どもに食の楽しみを教えるという役割もあります。そのため、食べたくない子どもに無理に食べさせたり、食べたいという子どもから無理に食事を取り上げたりする必要はありません。
もし食欲がない、食べ過ぎていると感じたときには翌日の食事で調整するとよいでしょう。
02幼児食をつくるときのポイント
幼児食は大人と同じ食事を食べられるようになるための準備の期間です。そのため、幼児食を作るときには大人の食事とは異なるポイントに注意が必要です。
2-13食+おやつで1日の栄養を摂る
幼児食期の子どもはまだまだ胃腸が未発達です。そのため、一度にたくさん食べられないということも少なくありません。
そんなときには、食事だけでなく、おやつや間食で必要な栄養素を摂取する必要があります。
おやつというとできるだけ食べさせたくないと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、幼児食期にはおやつも立派な栄養源です。さらに規則正しい時間におやつや間食を与えることは、生活と身体のリズムを整える効果もあります。
2-2塩分を控える
塩分は人間が生きるうえで必要不可欠なものですが、取りすぎは身体によくありません。特に身体の小さな幼児の場合、大人よりも塩分摂取に注意する必要があります。
目安となるのは、1~2歳の男子では3グラム未満、女子では3.5グラム未満、3~5歳の男子では男子が4グラム未満、女子では4.5グラム未満。
また、この時期に塩分の強い食事を与えていると、大人になっても塩分の強い食事を好むようになってしまいます。その場合、生活習慣病などのリスクも高まるため、塩分摂取には注意を払ったほうがよいでしょう。
出汁や食材の味を活かすと、塩分が少なくても美味しい食事を提供することができます。
2-3歯ごたえに差をつける
子どもにとって、食材の味だけでなく歯ごたえも重要です。もし同じような歯ごたえや食感のものばかりだと、めりはりがなくなり食事が楽しくないと感じてしまうこともあります。
メニューの中に歯ごたえのあるものを少量でも加えると、食事に飽きることを防ぐことができます。
03幼児食に適した食材
それでは、実際の幼児食にはどのような食材が適しているのでしょうか。
3-1うどん
うどんは離乳食の初期から食べられる便利な食材。スーパーやコンビニで簡単に手に入り、メニューのアレンジも豊富なので、バランスの取れた食事を作るときに向いています。
かけうどんなどの場合には、最初に子ども用の薄味のものを作り、その後大人向けの味付けをすると、手間が少なくなるだけでなく、親子で同じメニューを食べることができます。
3-2緑黄色野菜…かぼちゃ、ほうれん草など
幼児食には豊富な栄養が必要ですが、おすすめはかぼちゃやほうれん草といった緑黄色野菜。
緑黄色野菜に含まれるビタミンAやカロテンは、粘膜を強化して風邪などの予防に役立ちます。特にかぼちゃは柔らかく、甘い食材なので子どもにもぴったりです。
3-3海藻類
海藻類も幼児食に向いた食材です。海藻には様々な栄養素が含まれていますが、特に食物繊維が豊富なので、腸内環境を改善して便秘を防止してくれます。
ただし、大きすぎる状態では子どもにとっては食べにくいため、できるだけ細かくして提供することが必要です。
04幼児食に適さない注意食材
大人にとっては普通のものでも、幼児食に使うときには注意したい食材もあります。
4-1加工食品
ソーセージやウインナーなどは子どもが好む食材ですが、予想以上に塩分が高いものもあります。また、これらの食材には保存料も含まれているものが多く、幼児食には不向きといえます。
幼児食の完了期に提供する場合にも、塩分の低いものや食品添加物不使用のものなどを選ぶか、手作りするとよいでしょう。
4-2噛みきれにくいもの
幼児食期の子どもは胃腸だけでなく、あごも未発達で咀嚼力も強くありません。そのため、もし髪切れにくいものを食べてしまうと、のどに詰まってしまったり、誤嚥してしまう可能性もあります。
そのため、いか、たこ、こんにゃくなどの髪切りにくい食材は避けたほうがよいでしょう。
もし食べさせる場合には、細かく刻んで提供することもできますが、あまり無理はせず、食べやすい食材を選ぶのが無難です。
4-3かまぼこ、ちくわ
かまぼこ・ちくわもソーセージやウインナーと同様に食品添加物や塩分が多く含まれています。
そのため幼児食期には避けたほうがよいでしょう。また、つなぎに卵が使われていることもあるため、アレルギーなどにも注意が必要です。
4-4糖質・脂質が多い物
ケーキ、スナック菓子、ファーストフードなどは子どもの好む食べ物ですが、あまり糖質や脂質が多い場合、肥満につながることもあります。
また、ジュースなどにも多くの糖分が含まれているため、摂取するときは量にも注意しましょう。
4-5細菌感染が心配されるもの
子どもはまだまだ細菌への抵抗力が弱いため、刺身などの生ものは避けたほうがよいでしょう。
また、卵を生で食べると細菌による食中毒の原因となることもあります。
01まとめ
幼児期は食習慣の基礎を築く大切な時期です。幼児食選びには特に注意が必要です。
軟らかく咀嚼しやすい食材を選ぶことが重要です。
肉や魚は細かく刻んだり、野菜は柔らかく煮込むなど、幼児の歯の発達に合わせた調理が求められます。
アレルギー物質や塩分、糖分などにも気を配る必要があります。
また、バランスの良い栄養摂取も大切です。
たんぱく質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなどを組み合わせて、幼児の健やかな成長を支えましょう。
さらに、食事の時間を楽しむことも重要です。
楽しい雰囲気を醸成し、幼児の食への興味と好奇心を引き出すことで、望ましい食習慣の形成につなげられます。
幼児食選びの注意点を理解し、幼児の健康的な成長を支援していきましょう。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。
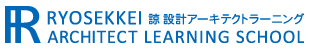
80,000人以上が受講申し込みしている諒設計アーキテクトラーニングの通信講座
あなたも早速受講して、資格を取得しましょう!
関連記事を見る
- 幼児の食育に関わる資格について
- 幼児食の鉄分の重要性!正しい摂取方法やおすすめレシピを紹介
- 幼児食に適した食材!適切な食事のポイントや注意点を解説
- 幼児食のそばデビューと注意点
- 幼児の食事マナーのしつけ方
- 幼児期の偏食について
- 幼児の牛乳の飲み方について
- 幼児のダイエットの目安は?やり方や注意点を伝授
- 風邪をひいたときの幼児食とは?食材やおすすめメニューを紹介
- 幼児食の味付けについての基本的な知識や注意点
- 幼児食についての基本的な知識!幼児食はいつからはじめる?
- 幼児食で上手に野菜を取り入れる!おいしく食べられるテクニックやコツ!
- 幼児期のお弁当におすすめの工夫やポイント
- 幼児期のおやつの目的や与えるポイント
- 幼児期に適切な食事の量や注意点
- 幼少期からの朝ごはんの習慣づくりとは?子供の心身の健やかな成長に!
- 幼児期に使用する食器の選び方!注意点やおすすめ食器素材を紹介
- これなら簡単!すぐに作れる幼児食の紹介や取り分けをする時のコツ
- 幼児食資格のおすすめ10選!最短2ヵ月で取得する方法も解説
1-11~1歳半を過ぎるころ
幼児食を始めるのは、通常1~1歳半を過ぎるころから食べさせるものとされています。
目安としては、一日三度の食事に慣れていることや、奥歯で食べ物をすりつぶして飲み込むことができるようになっていること、水分などの飲み物をコップから飲めるようになっていることなどが挙げられます。
ただし、子どもの成長には個人差が大きいもの。年齢はあくまでもひとつの目安です。
そのため、子どもの成長に合わせて提供するのがよいでしょう。
1-21~2歳児の1食分のカロリー摂取目安は300kcal、3~5歳児の1食分のカロリー摂取目安は400kcal
幼児食は、離乳食を卒業したあと、大人と同じものが食べられるようにする準備期間。しかし、この時期は子どもの成長にも重要な時期です。そのため、しっかりした栄養を取らせたり、たくさん食事を与えたりといったことに目が行きがちですが、食べ過ぎると肥満も心配になるものです。
もし食べる量が分からないというときには、カロリーを基準にするという方法もあります。
一般的に、1~2歳児の1食分のカロリー摂取目安は300kcal、3~5歳児の1食分のカロリー摂取目安は400kcalといわれています。そのため、もし食べる量が分からない場合、これらのカロリーが足りているか、取りすぎていないかを考えるとよいでしょう。
ただし、このカロリーも目安のひとつ。綿密なカロリー計算はかなり面倒なものでもあるため、あくまでも基準のひとつと考えるとよいでしょう。
1-3食欲がない、食べ過ぎたときは翌日の食事で調整する
子ども限らず、人間はその日の体調や天候によって食欲が左右されるもの。また、環境によっても食欲が上下します。
特に幼児食は、子どもに食の楽しみを教えるという役割もあります。そのため、食べたくない子どもに無理に食べさせたり、食べたいという子どもから無理に食事を取り上げたりする必要はありません。
もし食欲がない、食べ過ぎていると感じたときには翌日の食事で調整するとよいでしょう。
2-13食+おやつで1日の栄養を摂る
幼児食期の子どもはまだまだ胃腸が未発達です。そのため、一度にたくさん食べられないということも少なくありません。
そんなときには、食事だけでなく、おやつや間食で必要な栄養素を摂取する必要があります。
おやつというとできるだけ食べさせたくないと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、幼児食期にはおやつも立派な栄養源です。さらに規則正しい時間におやつや間食を与えることは、生活と身体のリズムを整える効果もあります。
2-2塩分を控える
塩分は人間が生きるうえで必要不可欠なものですが、取りすぎは身体によくありません。特に身体の小さな幼児の場合、大人よりも塩分摂取に注意する必要があります。
目安となるのは、1~2歳の男子では3グラム未満、女子では3.5グラム未満、3~5歳の男子では男子が4グラム未満、女子では4.5グラム未満。
また、この時期に塩分の強い食事を与えていると、大人になっても塩分の強い食事を好むようになってしまいます。その場合、生活習慣病などのリスクも高まるため、塩分摂取には注意を払ったほうがよいでしょう。
出汁や食材の味を活かすと、塩分が少なくても美味しい食事を提供することができます。
2-3歯ごたえに差をつける
子どもにとって、食材の味だけでなく歯ごたえも重要です。もし同じような歯ごたえや食感のものばかりだと、めりはりがなくなり食事が楽しくないと感じてしまうこともあります。
メニューの中に歯ごたえのあるものを少量でも加えると、食事に飽きることを防ぐことができます。
03幼児食に適した食材
それでは、実際の幼児食にはどのような食材が適しているのでしょうか。
3-1うどん
うどんは離乳食の初期から食べられる便利な食材。スーパーやコンビニで簡単に手に入り、メニューのアレンジも豊富なので、バランスの取れた食事を作るときに向いています。
かけうどんなどの場合には、最初に子ども用の薄味のものを作り、その後大人向けの味付けをすると、手間が少なくなるだけでなく、親子で同じメニューを食べることができます。
3-2緑黄色野菜…かぼちゃ、ほうれん草など
幼児食には豊富な栄養が必要ですが、おすすめはかぼちゃやほうれん草といった緑黄色野菜。
緑黄色野菜に含まれるビタミンAやカロテンは、粘膜を強化して風邪などの予防に役立ちます。特にかぼちゃは柔らかく、甘い食材なので子どもにもぴったりです。
3-3海藻類
海藻類も幼児食に向いた食材です。海藻には様々な栄養素が含まれていますが、特に食物繊維が豊富なので、腸内環境を改善して便秘を防止してくれます。
ただし、大きすぎる状態では子どもにとっては食べにくいため、できるだけ細かくして提供することが必要です。
04幼児食に適さない注意食材
大人にとっては普通のものでも、幼児食に使うときには注意したい食材もあります。
4-1加工食品
ソーセージやウインナーなどは子どもが好む食材ですが、予想以上に塩分が高いものもあります。また、これらの食材には保存料も含まれているものが多く、幼児食には不向きといえます。
幼児食の完了期に提供する場合にも、塩分の低いものや食品添加物不使用のものなどを選ぶか、手作りするとよいでしょう。
4-2噛みきれにくいもの
幼児食期の子どもは胃腸だけでなく、あごも未発達で咀嚼力も強くありません。そのため、もし髪切れにくいものを食べてしまうと、のどに詰まってしまったり、誤嚥してしまう可能性もあります。
そのため、いか、たこ、こんにゃくなどの髪切りにくい食材は避けたほうがよいでしょう。
もし食べさせる場合には、細かく刻んで提供することもできますが、あまり無理はせず、食べやすい食材を選ぶのが無難です。
4-3かまぼこ、ちくわ
かまぼこ・ちくわもソーセージやウインナーと同様に食品添加物や塩分が多く含まれています。
そのため幼児食期には避けたほうがよいでしょう。また、つなぎに卵が使われていることもあるため、アレルギーなどにも注意が必要です。
4-4糖質・脂質が多い物
ケーキ、スナック菓子、ファーストフードなどは子どもの好む食べ物ですが、あまり糖質や脂質が多い場合、肥満につながることもあります。
また、ジュースなどにも多くの糖分が含まれているため、摂取するときは量にも注意しましょう。
4-5細菌感染が心配されるもの
子どもはまだまだ細菌への抵抗力が弱いため、刺身などの生ものは避けたほうがよいでしょう。
また、卵を生で食べると細菌による食中毒の原因となることもあります。
01まとめ
幼児期は食習慣の基礎を築く大切な時期です。幼児食選びには特に注意が必要です。
軟らかく咀嚼しやすい食材を選ぶことが重要です。
肉や魚は細かく刻んだり、野菜は柔らかく煮込むなど、幼児の歯の発達に合わせた調理が求められます。
アレルギー物質や塩分、糖分などにも気を配る必要があります。
また、バランスの良い栄養摂取も大切です。
たんぱく質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなどを組み合わせて、幼児の健やかな成長を支えましょう。
さらに、食事の時間を楽しむことも重要です。
楽しい雰囲気を醸成し、幼児の食への興味と好奇心を引き出すことで、望ましい食習慣の形成につなげられます。
幼児食選びの注意点を理解し、幼児の健康的な成長を支援していきましょう。
3-1うどん
うどんは離乳食の初期から食べられる便利な食材。スーパーやコンビニで簡単に手に入り、メニューのアレンジも豊富なので、バランスの取れた食事を作るときに向いています。
かけうどんなどの場合には、最初に子ども用の薄味のものを作り、その後大人向けの味付けをすると、手間が少なくなるだけでなく、親子で同じメニューを食べることができます。
3-2緑黄色野菜…かぼちゃ、ほうれん草など
幼児食には豊富な栄養が必要ですが、おすすめはかぼちゃやほうれん草といった緑黄色野菜。
緑黄色野菜に含まれるビタミンAやカロテンは、粘膜を強化して風邪などの予防に役立ちます。特にかぼちゃは柔らかく、甘い食材なので子どもにもぴったりです。
3-3海藻類
海藻類も幼児食に向いた食材です。海藻には様々な栄養素が含まれていますが、特に食物繊維が豊富なので、腸内環境を改善して便秘を防止してくれます。
ただし、大きすぎる状態では子どもにとっては食べにくいため、できるだけ細かくして提供することが必要です。
4-1加工食品
ソーセージやウインナーなどは子どもが好む食材ですが、予想以上に塩分が高いものもあります。また、これらの食材には保存料も含まれているものが多く、幼児食には不向きといえます。
幼児食の完了期に提供する場合にも、塩分の低いものや食品添加物不使用のものなどを選ぶか、手作りするとよいでしょう。
4-2噛みきれにくいもの
幼児食期の子どもは胃腸だけでなく、あごも未発達で咀嚼力も強くありません。そのため、もし髪切れにくいものを食べてしまうと、のどに詰まってしまったり、誤嚥してしまう可能性もあります。
そのため、いか、たこ、こんにゃくなどの髪切りにくい食材は避けたほうがよいでしょう。
もし食べさせる場合には、細かく刻んで提供することもできますが、あまり無理はせず、食べやすい食材を選ぶのが無難です。
4-3かまぼこ、ちくわ
かまぼこ・ちくわもソーセージやウインナーと同様に食品添加物や塩分が多く含まれています。
そのため幼児食期には避けたほうがよいでしょう。また、つなぎに卵が使われていることもあるため、アレルギーなどにも注意が必要です。
4-4糖質・脂質が多い物
ケーキ、スナック菓子、ファーストフードなどは子どもの好む食べ物ですが、あまり糖質や脂質が多い場合、肥満につながることもあります。
また、ジュースなどにも多くの糖分が含まれているため、摂取するときは量にも注意しましょう。
4-5細菌感染が心配されるもの
子どもはまだまだ細菌への抵抗力が弱いため、刺身などの生ものは避けたほうがよいでしょう。
また、卵を生で食べると細菌による食中毒の原因となることもあります。
01まとめ
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。
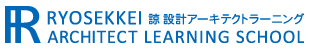
- 幼児の食育に関わる資格について
- 幼児食の鉄分の重要性!正しい摂取方法やおすすめレシピを紹介
- 幼児食に適した食材!適切な食事のポイントや注意点を解説
- 幼児食のそばデビューと注意点
- 幼児の食事マナーのしつけ方
- 幼児期の偏食について
- 幼児の牛乳の飲み方について
- 幼児のダイエットの目安は?やり方や注意点を伝授
- 風邪をひいたときの幼児食とは?食材やおすすめメニューを紹介
- 幼児食の味付けについての基本的な知識や注意点
- 幼児食についての基本的な知識!幼児食はいつからはじめる?
- 幼児食で上手に野菜を取り入れる!おいしく食べられるテクニックやコツ!
- 幼児期のお弁当におすすめの工夫やポイント
- 幼児期のおやつの目的や与えるポイント
- 幼児期に適切な食事の量や注意点
- 幼少期からの朝ごはんの習慣づくりとは?子供の心身の健やかな成長に!
- 幼児期に使用する食器の選び方!注意点やおすすめ食器素材を紹介
- これなら簡単!すぐに作れる幼児食の紹介や取り分けをする時のコツ
- 幼児食資格のおすすめ10選!最短2ヵ月で取得する方法も解説