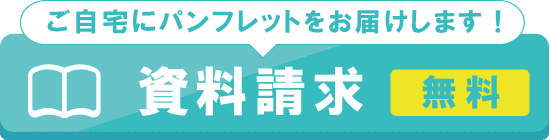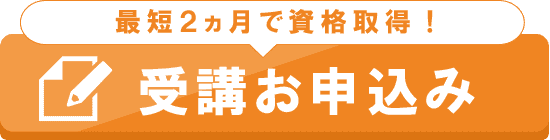紅茶の淹れ方や注意点とは?!初心者におすすめの基本を解説
紅茶は、初心者にも手軽にゆっくりと楽しめる魅力的な飲み物です。複雑な技術は必要ありません。最初は少しずつ味わいを確認しながら、自分の好みを見つけていくのがおすすめです。
まずは、優しい風味の紅茶をお試しください。人気の銘柄には、ダージリン、アッサム、セイロンなどがあります。これらはバランスの良いまろやかな味わいが特徴です。水温や浸出時間を調整して、自分好みの濃さや香りを作り上げていくのがおもしろい体験になるでしょう。
紅茶には種類や生産地によって味わいの違いがありますが、初めは煮出し時間を短めに設定し、様子を見ながら調整するのがよいでしょう。同じ銘柄でも、淹れ方によって印象はかなり変わってきます。ゆっくり試行錯誤を重ねて、自分の好みに合った淹れ方を見つけていきましょう。
ティータイムにはコーヒーや緑茶よりも紅茶がいいという方も少なくないことでしょう。どうせ飲むなら美味しい紅茶を飲みたいものですが、初心者が戸惑ってしまうのは、どんな紅茶を選び、どうやって淹れるかということ。今回は初心者におすすめの紅茶や、紅茶の基本的な淹れ方についてご紹介します。
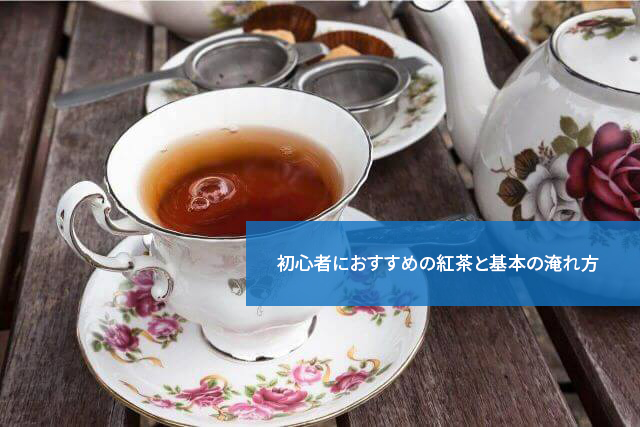
- 目次
- 1. 紅茶の基礎知識
- 1-1. 紅茶とは
- 1-2. 紅茶の製造過程
- 1-3. 紅茶の主な産地
- 2. 紅茶の種類とは?
- 2-1. 茶葉の主な品種と違い(アッサム種、中国種など)
- 2-2. オルゴノレプティック特性(香り、色、味わい)の違い
- 2-3. 代表的な銘柄(アールグレイ、ダージリン、ディンブラなど)
- 3. 紅茶の効果・効能
- 3-1. カフェインの含有量
- 3-2. ポリフェノールなどの健康成分
- 3-3. 気分転換や集中力アップ効果
- 4. 初心者におすすめの紅茶とは?
- 4-1. アールグレイ
- 4-2. ダージリン
- 4-3. アッサム
- 5. 紅茶の選び方で注意したいこと
- 5-1. 産地
- 5-2. 茶葉の形状
- 5-3. 有機JAS認証
- 5-4. 賞味期限
- 6. 紅茶の基本の淹れ方
- 6-1. 用意するもの
- 6-2. 茶葉の量
- 6-3. 湯温と抽出時間
- 7. 紅茶初心者におすすめの飲み方
- 8. 初心者でも出来る紅茶の淹れ方
- 9. 紅茶を買うときの注意点
- 10. まとめ
01紅茶の基礎知識
1-1紅茶とは
紅茶とは、茶の木の葉を発酵させて作られる飲み物です。 茶の木の若い葉と芽を摘み取り、発酵させることで、赤茶色の紅茶が作られます。発酵の度合いによって、香りや味わいが大きく変わってきます。 軽発酵の香紅茶は爽やかな味わい、中発酵の中国紅茶はコクのある円滑な味わい、深発酵のアッサム紅茶は濃厚な香りとコクが特徴的です。 紅茶にはカフェインが含まれ、リラックス効果や集中力アップが期待できます。日常的な飲み物から、おもてなしの席での活躍まで、幅広く活用されている飲料なのです。
1-1紅茶の製造過程
紅茶の製造過程は大きく4つの工程から成り立っています。 まず初めに、茶の木の若い葉と芽を丁寧に摘み取ります。この工程を「摘採」といいます。 次に、摘み取った葉を天日干しや熱風で水分を減らす「萎凋」の工程を行います。この工程で葉が柔らかくなり、発酵に適した状態になります。 そして、発酵させる「発酵」の工程に入ります。この工程で葉の成分が酸化し、紅茶特有の赤茶色や香り、コクが生まれます。発酵の度合いによって、味わいが大きく変わってきます。 最後に、発酵を止めるため「仕上げ」の熱処理を行います。この工程で、紅茶の風味が安定し、美味しく飲めるようになります。 以上の4つの工程を経て、私たちが日常的に楽しむ紅茶が完成するのです。製造過程の違いが、紅茶の多様な味わいを生み出しているのが特徴といえます。
1-1紅茶の主な産地
紅茶の主な産地は、主に東アジアを中心に世界各地に広がっています。 最も有名な産地の1つが、インドのアッサム地方です。アッサム紅茶は、深い発酵によりコクのある濃厚な味わいが特徴的です。 また、中国の福建省や四川省、雲南省なども有名な紅茶の産地です。中国産の紅茶は、発酵が中程度の「中国紅茶」と呼ばれ、まろやかで円滑な味わいが人気です。 さらに、スリランカ(旧セイロン)も世界的な紅茶産地として知られています。スリランカ産の紅茶は「セイロン紅茶」と呼ばれ、爽やかな香りと上品な味わいが特徴です。 その他にも、ケニア、インドネシア、台湾など、熱帯〜亜熱帯地域を中心に、多くの国や地域で紅茶が栽培されています。 産地によって気候や栽培環境が異なるため、紅茶にはそれぞれ特徴的な味わいが生まれるのが魅力といえるでしょう。紅茶を楽しむ際は、産地の違いにも注目してみるのも面白いかもしれません。
01紅茶の種類とは?
1-1茶葉の主な品種と違い(アッサム種、中国種など)
アッサム種 ● 特徴: 大型の茶の木、濃厚な香りとコクのある味わい ● 主な産地: インドのアッサム地方 中国種 ● 特徴: 小型の茶の木、上品な香りと穏やかな味わい ● 主な産地: 中国の南部地域 セイロン種 ● 特徴:大型の茶の木、マイルドで爽快な味わい ● 主な産地: スリランカ(旧セイロン) これらの品種の違いは、主に茶の木の形態と生育環境によるものです。アッサム種やセイロン種は大型で熱帯性、中国種は小型で亜熱帯性といった具合です。 また、同じ品種でも産地の気候や土壌条件によって、香りや味わいに違いが現れます。 このように、茶葉の品種と産地の違いが、紅茶の多様な風味を生み出しているのが特徴です。好みに合わせて、さまざまな産地の紅茶を楽しむことができます。
1-1オルゴノレプティック特性(香り、色、味わい)の違い
紅茶のオルゴノレプティック特性、つまり香り、色、味わいの違いは以下のように特徴づけられます。 香りについては、産地によって大きな違いが見られます。アッサム紅茶は濃厚でスパイシーな香り、中国紅茶は繊細で上品な香り、セイロン紅茶は爽やかで香り高いといった具合です。 色については、発酵の度合いによって大きく変わってきます。発酵が少ない紅茶は赤みがかった色合いで、発酵が進んだ紅茶は濃い赤茶色になります。 味わいも産地と発酵の度合いによって大きく異なります。アッサム紅茶はコクと渋みが強く、中国紅茶はまろやかで円滑な味わい、セイロン紅茶は爽快でほどよい渋みが特徴的です。 さらに、同じ産地の茶葉でも、栽培環境の違いによって微妙な味わいの違いが生まれます。例えば、同じ中国産でも福建茶と四川茶では、香りや風味が異なります。 このように、紅茶のオルゴノレプティック特性は、産地や栽培環境、発酵の度合いなどによって大きく変化します。それぞれの特徴を理解し、自分好みの紅茶を見つけていくのも楽しみの1つといえるでしょう。
1-1代表的な銘柄(アールグレイ、ダージリン、ディンブラなど)
紅茶の代表的な銘柄には以下のようなものがあります。 アールグレイ: アールグレイは、中国産の紅茶に bergamot(ベルガモット)の果皮の精油を加えて香りづけした紅茶です。柑橘系の爽やかな香りとマイルドな味わいが特徴で、世界的に有名な銘柄の1つです。ベルガモット香が紅茶の香りを引き立てます。 ダージリン: ダージリンは、インドのダージリン地方で栽培されるアッサム種の紅茶です。標高の高い気候条件で育つため、フルーティーな香りと繊細な味わいが特徴的です。ムスカテル香と呼ばれる独特の風味が魅力で、世界一の銘柄の1つと称されています。 ディンブラ: ディンブラはスリランカ(旧セイロン)の代表的な紅茶で、セイロン種が主体です。マイルドな香りと渋みのバランスが良く、爽やかな味わいが特徴的です。スリランカの中高地で栽培され、歴史的にも有名な銘柄の1つです。 このように、それぞれの産地や製造方法の違いから生み出される特徴的な香りや味わいが、紅茶の多様な魅力を生み出しています。これらの代表的な銘柄は、紅茶愛好家に広く知られる銘柄の一部にすぎません。
01紅茶の効果・効能
1-1カフェインの含有量
紅茶にはカフェインが含まれており、品種や産地、製造方法などによって、その含有量に違いがあります。 一般的に、紅茶1カップ(200ml)当たりのカフェイン含有量は30mg〜50mgといわれています。 これは、コーヒー1カップ(120ml)の95mg〜200mgと比べると、平均で1/4 程度の量です。 品種別では、アッサム種のダージリンやディンブラが最も高く、40mg前後が一般的です。 一方、シネンシス種のアールグレイは30mg前後と、やや低めの傾向にあります。 また、茶葉の部位によっても差があり、若い茶芽ほどカフェイン含有量が高くなります。 そのため、茶葉を丁寧に選別した高級紅茶はカフェイン量も少なめです。 一方で、紅茶を長時間煮出したり、水温が高いと、カフェインの溶出量が増加します。 カフェイン過敏の人は、濃い色の紅茶や長時間抽出したものを避けるのがよいでしょう。 このように、紅茶のカフェイン含有量は様々な要因によって変化しますが、一般的には適度な量が含まれており、コーヒーに比べると低めの傾向にあると言えます。
1-1ポリフェノールなどの健康成分
紅茶には、カフェインとともに様々な健康に良い成分が豊富に含まれています。主なものには以下のようなものがあります。 ポリフェノール 紅茶には、カテキンやテアフラビン、テアルビギンなどのポリフェノール化合物が多く含まれています。 これらのポリフェノールは強い抗酸化作用があり、がんや心臓病、認知症などの予防に効果があると報告されています。 ポリフェノールの含有量は、製造過程での発酵の度合いによって異なり、発酵の少ない緑茶やウーロン茶に多く含まれます。 アミノ酸 紅茶にはL-テアニンというアミノ酸が特徴的に含まれています。 L-テアニンには、リラックス効果や集中力の向上、免疫機能の亢進などの作用があるとされています。 L-テアニンはカフェインとうまく相乗効果を発揮し、落ち着いた気分をもたらすとも言われています。 ビタミン・ミネラル 紅茶にはビタミンC、ビタミンB群、鉄、マグネシウムなどのミネラルが含まれています。 これらの栄養素は、美肌効果や疲労回復、免疫力の向上などに寄与すると考えられています。 このように、紅茶にはカフェインだけでなく、ポリフェノールやアミノ酸、ビタミンなどの健康に良い成分が豊富に含まれています。適度な紅茶の摂取は、様々な健康面での効果が期待できるでしょう。
1-1気分転換や集中力アップ効果
紅茶には、気分転換や集中力アップといった効果が期待できる成分が含まれています。 まず、カフェインの効果として、覚醒作用や集中力の向上が挙げられます。カフェインは脳内のアデノシン受容体に作用し、覚醒物質の分泌を促進します。これにより、眠気を取り除き、集中力を高めることができます。ただし、過剰摂取は不眠や不安感の原因にもなるため、適量が重要です。 次に、L-テアニンの効果が注目されます。L-テアニンはアミノ酸の一種で、リラックス効果や集中力の向上が知られています。L-テアニンは脳内のGABA受容体に作用し、落ち着いた気分を生み出すと考えられています。また、カフェインとの相乗効果によって、リラックスしつつ集中力も高められるのが特徴です。 さらに、ポリフェノールにも気分転換効果が期待できます。ポリフェノールには抗酸化作用があり、ストレス軽減や気分改善に役立つと考えられています。特に、テアフラビンやテアルビギンなどの発酵産物は、リラックス効果が高いとされています。 これらの成分が組み合わさることで、紅茶は気分転換や集中力アップに役立つと言えます。適度な紅茶の飲用は、ストレス解消や生産性の向上に効果的かもしれません。ただし、個人差もあるため、自分に合った飲み方を見つけることが大切です。
01初心者におすすめの紅茶とは?
1-1アールグレイ
まずはベルガモットの上品な香りが特徴的で、紅茶の爽やかな風味を引き立てます。香りだけでなく、味わいもマイルドで程よい甘さがあるため、紅茶初心者でも飲みやすいのが大きな魅力です。 また、ミルクやレモンなどとの相性が良いため、アレンジの幅が広いのも特徴的。ミルクティーやアイスティーなど、様々な飲み方を楽しめます。 さらに、上品で洗練された印象があり、気分に合わせてティータイムを演出できるのも魅力の一つ。紅茶の楽しみ方を広げるのにぴったりの銘柄といえます。 初心者にもおすすめできる、香り高くマイルドな味わいが特徴のアールグレイは、紅茶の素晴らしさを感じられる良い入門茶といえるでしょう。
1-1ダージリン
ダージリン地方特有のフルーティーで爽やかな香りが魅力的。茶葉の色合いも美しく、視覚的にも楽しめます。 そして、マイルドで複雑な味わいは、食事との相性も良く、ティータイムをより豊かに演出してくれます。 さらに、茶園の標高や製造時期によって微妙に異なる個性を持つのも特徴。同じ産地でも異なる味わいを楽しめるのは大きな魅力です。 ダージリン紅茶は、紅茶の奥深さを知ることができる銘柄。初心者から上級者まで、幅広く愛されている高品質な紅茶です。
1-1アッサム
濃厚なマイルドな味わいが特徴で、ミルクティーなどに最適です。初心者でも飲みやすく、コクのある深い味わいが楽しめます。 また、地域によって特徴が異なるアッサム茶は、幅広い品揃えがあるため、自分好みの1品を見つけやすいのも魅力的。 さらに、ほのかな甘みと香りがあり、爽やかな後味も特徴的。紅茶の定番的な味わいを求める初心者にピッタリです。
01紅茶の選び方で注意したいこと
1-1産地
紅茶の品質は、産地の気候や土壌条件によって大きく影響されます。理想的な条件は温暖で湿潤な気候と肥沃な土壌です。こういった環境で育った茶葉は、豊かな風味と深みのある味わいを持っています。 一方、高地地域の紅茶は特徴的な風味を持つことが知られています。日較差の大きな気候条件により、茶葉の成長過程で複雑な化学変化が起こるためです。このような地域の紅茶は、上品さと爽やかさが際立ちます。 産地によって最適な摘採時期も異なります。初春の「一番茶」は繊細で上品な味わい、夏の「二番茶」は濃厚な風味となるのが一般的です。生産者は気候条件を見極めながら、最適なタイミングで茶葉を摘み取っています。 同じ産地の中でも、製茶工場の製造方法によって味わいが変わってきます。発酵の度合いや乾燥方法の違いなどが、風味の特徴に大きな影響を与えるのです。手摘みや手作業にこだわる小規模茶園の製品は、より個性的な味わいを持つ傾向にあります。 以上のように、紅茶の産地を選ぶ際は、気候や土壌、摘採時期、製造方法など、様々な要素を総合的に検討する必要があります。
1-1茶葉の形状
紅茶の茶葉の形状は、製造方法によって大きく異なります。最も一般的なのが「ブロークン」と呼ばれる形状で、丸くて均一な小さな茶葉です。ブロークンは飲みやすく、使い勝手が良いのが特徴です。 一方で「ファンシー」と呼ばれる長めの茶葉も存在します。ファンシーは香り豊かで、複雑な味わいが楽しめます。茶葉が丸くなっていないため、見た目にも趣がある製品です。 さらに、手摘みで製造された「ダストリーフ」と呼ばれる茶葉もあります。ダストリーフは非常に細かく、風味が濃厚です。機械化されたブロークンと比べ、手作業ならではの個性が感じられます。 このように、紅茶の茶葉の形状は製造方法によってそれぞれ特徴があり、好みに合わせて選ぶことができます。丸くて均一なブロークンから、個性的なファンシーやダストリーフまで、様々なラインナップの中から自分に合った一品を見つけましょう。
1-1有機JAS認証
有機JAS認証を取得している紅茶は、化学合成農薬や化学肥料を一切使用せず、環境に配慮した持続可能な生産方式が採用されています。このため、安全性が高く、安心して飲むことができます。 有機JAS認証は、農林水産大臣の定める日本農林規格に基づいて、第三者機関によって厳格に審査されます。認証を取得するには、生産から製造、流通に至るまで、厳しい基準をクリアする必要があります。消費者に対して「環境に優しい」「安全性が高い」ということを保証するものです。化学合成品を一切使用しない有機栽培の茶葉は、より自然の味わいを楽しめるでしょう。 一方で、有機JAS認証を取得していない製品であっても、同様の生産方式を採用している場合があります。ラベルの表示だけでなく、生産者の取り組みについても確認するのがよいでしょう。 有機JAS認証は紅茶選びの一つのポイントとなりますが、最終的には自分の好みに合った製品を見つけることが重要です。有機JAS認証を参考に、安全性と環境配慮の観点から紅茶を選んでみてください。
1-1賞味期限
紅茶は時間の経過とともに風味が変化していきます。新鮮なうちに飲むことがおいしさの秘訣です。そのため、紅茶を購入する際は賞味期限を確認し、できるだけ新しい製品を選ぶことが大切です。 一般的に、紅茶の賞味期限は製造日から1年程度とされています。ただし、製造方法や保存方法によってはそれ以上長期保存できる場合もあります。密閉容器に入った茶葉や、真空パックされた製品は比較的長持ちします。 一方で、開封後は酸素に触れることで酸化が進み、風味が劣化していきます。密閉保存し、なるべく早く飲み切ることをおすすめします。 紅茶は新鮮なうちが一番おいしいですが、賞味期限内であれば風味の劣化は気にしなくても大丈夫です。ただし、長期保存された製品は避けたほうがよいでしょう。 賞味期限を確認し、できるだけ新しい製品を選ぶことで、紅茶本来の風味を最大限に楽しめるはずです。自分の好みに合った紅茶との出会いが待っているかもしれません。
01紅茶の基本の淹れ方
1-1用意するもの
紅茶を淹れるために必要な基本的な道具は、ティーポットと湯呑みです。ティーポットは陶器やガラス、金属製のものなど、素材によって様々な種類があります。好みの素材やデザインのものを選びましょう。 ティーサーバーやストレーナー、ティースプーンなどの小物も便利です。ストレーナーを使えば、茶葉の残渣を受け止めて綺麗な紅茶を楽しめます。また、ティースプーンがあれば茶葉の量を量ったり、湯呑みに注ぐときに役立ちます。 さらに、茶葉を計量するための計量スプーンや、紅茶の温度を確認するための湯温計など、お気に入りの道具を揃えるのも楽しみの一つです。好みのスタイルで気分に合わせて準備することで、より楽しい時間が過ごせるはずです。
1-1茶葉の量
紅茶の基本的な茶葉の量の目安は、1人分あたり3g前後です。ただし、好みの濃さによって調整することも可能です。濃い目が好きな人は4gほど、薄めが好きな人は2gほどがよいでしょう。 茶葉の量を調整する際のコツは、急須のサイズに合わせることです。急須が大きい場合は多めの茶葉を、小さい急須では少なめの茶葉を使うとよいでしょう。 また、ブレンドの紅茶やファンシーなど、茶葉の形状によっても適量が異なります。粒子が細かいものは少なめ、葉の形が大きいものは多めに使うと良いでしょう。 紅茶の楽しみ方は人それぞれ異なるため、自分の好みに合わせて茶葉の量を調整することをおすすめします。試行錯誤しながら、最高においしい紅茶を見つけましょう。
1-1湯温と抽出時間
紅茶の最適な湯温は95度前後です。この温度で茶葉をじっくりと抽出することで、紅茶本来の風味を引き出すことができます。 抽出時間は3分〜5分程度が一般的ですが、お好みによって調整しましょう。時間が短い場合は風味が弱く、長すぎると渋みが強くなりすぎてしまいます。 中国産の紅茶は3分、アッサム紅茶は5分程度が目安と言われています。ただし、同じ産地の紅茶でも製造方法によって異なるため、自分で試しながら最適な抽出時間を見つけることをおすすめします。 湯温と抽出時間を適切に設定することで、紅茶本来の豊かな風味を最大限に引き出せます。お気に入りの急須やティーポットを使い、好みの濃さに調整しながら、心地よい時間を過ごしましょう。
01紅茶初心者におすすめの飲み方
紅茶初心者にとって、大切なのは飲み方です。どうすれば初心者でも美味しい紅茶を楽しむことができるのでしょうか。
1-1最初はティーバッグから
まず初心者におすすめしたいのが、簡単にティーバッグを利用して紅茶を楽しむ方法です。ティーバッグといえば、美味しくない、インスタントといったイメージがありますが、ティーバッグでも、パッケージに書かれた淹れ方をきちんと守ることで、きちんと紅茶を楽しむことができます。実際、紅茶大国として知られているイギリスでも、普段楽しむ紅茶はほとんどがティーバッグ。もちろんきちんとポットとリーフで紅茶を淹れることはありますが、それはお客さんを招いたり、ホテルのティーサロンでお茶を楽しんだりと言った場合に限られます。
特に最近は日本でも、一般的なスーパーでも売られているティーバッグの種類が非常に豊富になっているため、自分好みの紅茶を見つけることができるでしょう。
1-2濃くて渋いときはお湯を足す
紅茶があまり好きではないという人の中には、紅茶独特の渋みを敬遠する方も少なくありません。その場合、抽出時間が長すぎて、濃くて渋い風味が出過ぎているという場合があります。また、茶葉の種類によってはどうしても渋みの強いものもあります。そういった場合、おすすめなのが「お湯を足す」という方法です。すでに抽出された紅茶にお湯を足すというと、ルール違反のように思われるかもしれませんが、実はこれは珍しいことではありません。むしろ、紅茶にこだわりが強い人の中には、自分なりにベストな香りや渋みを持っている人が多く、そういう人はお湯を足すことで自分好みの紅茶の状態に近づけることがあります。もし、紅茶が渋いと感じるなら、お湯を少しずつ足すことで、好みの味にカスタムすることがおすすめです。
1-3ミルクティーにして飲む
もし紅茶の渋みがどうしてもダメという場合、ミルクティーにしてみるのはいかがでしょうか。濃い目に出した紅茶にたっぷりの砂糖を淹れたミルクティーは、イギリスでも代表的な飲み物のひとつ。ミルクティーは飲みやすいだけでなく、紅茶本来の魅力を引き出してくれる飲み方。特に少しミルクを温めると、さらなるおいしさを楽しむことができます。
02初心者でも出来る紅茶の淹れ方
紅茶をきちんと淹れるというと、知識やテクニックが必要に思えるかもしれませんが、実際はそうではありません。必要な道具を、ちょっとしたコツを覚えておくだけで、誰でも簡単に、おいしい紅茶を淹れることができます。
2-1必要な道具、材料
紅茶を淹れるときに必要なのは、お湯を沸かす道具と紅茶を抽出するポット、そして茶葉の三つです。といっても専用のものを購入する必要はありません。
たとえば、お湯を沸かすのは、どこの家庭にもあるヤカンを使えばOKです。ただし、このときひとつだけ注意したいのは、鉄製のやかんは使わないということ。鉄製のやかんを使うと、やかんから流出した鉄分が紅茶に含まれるタンニンと反応、黒ずんだ色の紅茶になってしまいます。さらに、紅茶自体の味も変わってしまうため、できれば鉄製のやかんは避けたほうがいいでしょう。
また、ポットはどのようなものでも構いませんが、できればガラス製の容量の多いものがおすすめです。容量が多いものは、ポットの中で紅茶の茶葉がきちんと循環することで、本来の風味を抽出することができます。
このほかにも、茶葉の量を計るティーメジャーなどがあると便利です。
2-2基本的な淹れ方
紅茶を淹れるときは、まず新鮮なお水を使用しましょう。新鮮なお水には酸素がたっぷり含まれているので、紅茶の風味や香りを存分に引き出すことができます。
紅茶を淹れるには、軟水が適しているとされますが、日本の場合、ほとんどの地域で水道の蛇口から出るのは軟水なので、それをそのまま沸かせば問題はありません。逆に、高価なミネラルウォーターなどは硬水が多いため、使用するときには注意が必要です。紅茶を淹れるためのお湯を沸かすときには、熱湯であることが重要。しっかりと湯気が出て、お湯が沸騰するのを確認しましょう。
次に、沸騰したお湯をティーポットに注ぎ、お湯が冷めないようにティーポットを温めておきます。
ティーポットが温まったら、茶葉を淹れますが、そのまま飲むストレートティーの場合には4~5グラム、ミルクティーの場合には濃い目が良いため、6~8グラムが目安になります。ティーメジャーなら、ストレートティーはスプーン一杯分、ミルクティーはスプーン一杯半から二杯となります。
茶葉を入れたら、そこにお湯を注ぎます。そして蓋をして蒸らしますが、ダージリンなら五分、他の茶葉なら三分が基本の時間です。これ以上、長くても短くても美味しい紅茶を楽しむことはできないので、少々面倒でも、ここはきちんとタイマーで時間を計ったほうがよいでしょう。
蒸らしの時間が終われば、いよいよ紅茶をカップに注ぎますが、この段階では、ポットの中では紅茶の濃度に違いがあります。そのため、スプーンなどを使用して、上下を軽く混ぜて全体を均一にしておきましょう。ただし、あまり乱暴にやりすぎると紅茶が苦くなってしまうことがあるので注意しましょう。
紅茶を淹れるのは難しいというイメージがありますが、実はそれほど難しいものではありません。必要なのは、しっかりお湯を沸かす、茶葉や時間を計るといったちょっとしたポイント。ここさえ押さえておけば、誰でも美味しい紅茶を淹れることができます。
03紅茶を買うときの注意点
美味しい紅茶を楽しむときには、淹れ方だけでなく紅茶を買うときにもちょっとした注意が必要です。
3-1パッケージに傷みがないか
スーパーなどで紅茶を買うときには、パッケージに傷や穴がないかを確認しましょう。紅茶は乾燥している茶葉ですが、実は非常に劣化しやすく、すぐに風味や香りが抜けてしまいます。パッケージに傷みがある場合、すでに紅茶としての美味しさが失われている場合があります。もし紅茶を購入するときには、鮮度が保てるように、密閉できるアルミパック入りのものがおすすめです。
3-2大容量より2週間ぐらいで飲みきれる量がベスト
紅茶を購入するとき、大容量のほうが価格が安いため、ついついそちらを買い求めてしまいがちですが、よほど大量に紅茶を飲む家庭ではない限り、大容量のものはどうしてもあまりがちになってしまいます。そうすると、茶葉から香りや旨みが抜けてしまい、美味しい紅茶が楽しめません。少々割高になっても、二週間程度で飲み切れる量を購入すると、最後まで美味しい状態の紅茶を楽しむことができます。
3-3賞味期限で鮮度をみる
すでに説明したように、紅茶は鮮度が大切。そのためのヒントになるのが賞味期限です。もし賞味期限が近付いている場合、すでにかなりの時間が経過していることが考えられます。そのため、美味しい紅茶を楽しみたいという場合には、賞味期限に余裕があるものを選ぶとよいでしょう。
01まとめ
まず、初心者におすすめの紅茶としては、バランスのとれた味わいのアッサムやダージリンなどが良いでしょう。これらの産地の紅茶は、渋みや苦みが控えめで、ミルクや砂糖を加えることでより美味しく楽しめます。
次に、紅茶の基本的な淹れ方ですが、ポイントは「適温の湯」と「十分な抽出時間」です。沸騰した直後の湯ではなく、95度前後の温度が最適です。また、茶葉を3分以上浸けることで、紅茶本来の深い香りと旨みが引き出されます。
ミルクの使い方ですが、紅茶を注いだ後、最後にミルクを加えるのがコツです。ミルクの量は、紅茶の3割程度が目安ですが、好みによって調整しましょう。
砂糖の使い方についても、少量から始め、自分好みの甘さに調整するのがおいしい飲み方のポイントです。特に、苦みや渋みの強い紅茶には砂糖が良く合います。
最後に、茶葉の保管方法ですが、光や空気、湿気を避けて、密閉容器で冷暗所に保管することが大切です。茶葉は時間と共に酸化が進むため、できるだけ早く使い切るのが望ましいでしょう。
以上が、初心者におすすめの紅茶とおいしい淹れ方のポイントのまとめです。これらのことを意識しながら、自分好みの紅茶の楽しみ方を見つけていきましょう。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。
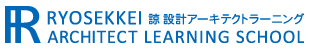
80,000人以上が受講申し込みしている諒設計アーキテクトラーニングの通信講座
あなたも早速受講して、資格を取得しましょう!
関連記事を見る
- 紅茶の誕生と歴史と文化を詳しく解説
- 紅茶の基本知識とは?趣味として始める紅茶の世界!
- 紅茶を飲む時の注意すべきポイントと基本マナーとは?
- 紅茶の道具と選ぶときのポイントとは
- 紅茶の茶葉の種類とは?分類方法や種類別の詳しい特徴を紹介
- 紅茶の持つ健康効果とは? 様々な効能が期待できる紅茶の魅力!
- 紅茶に関わる仕事と資格とは
- 家庭でできる紅茶の作り方と注意点
- 紅茶をブレンドする目的とは?実践的な紅茶ブレンドの方法を解説
- 紅茶の淹れ方や注意点とは?!初心者におすすめの基本を解説
- 水筒で紅茶を楽しむ為に、これだけは絶対に知っておきたい4項目
- 紅茶にレモンを入れると色が薄くなる不思議
- クリームダウンを防げば、アイスティーはもっとおいしくなる!
- 簡単にできる紅茶クッキーのレシピを3つご紹介
- 紅茶には身体にいい効能がいっぱい!
- 紅茶と相性のいいお菓子・食べ物について
- 紅茶のおとも「ミルクと砂糖」について
- 紅茶とハーブティーの違い
- 紅茶で服を染めてみよう!紅茶染めの楽しみ
- 紅茶を入れる道具についてのポイント
- 紅茶とお酒を合わせて楽しむ方法
- 紅茶を使ったカクテル
- ティーカップに持ち手が付いたわけ
- 紅茶を飲んでちょっと休憩する時に使ってみたい英語表現
- 紅茶に入れるもの
- 紅茶の保存容器いろいろ
- 初心者でも簡単!紅茶染め
- 紅茶の種類とは?紅茶の専門家になるための紅茶資格!
- 紅茶資格おすすめ7選!資格の種類や取得方法・活用法を解説!
1-1最初はティーバッグから
まず初心者におすすめしたいのが、簡単にティーバッグを利用して紅茶を楽しむ方法です。ティーバッグといえば、美味しくない、インスタントといったイメージがありますが、ティーバッグでも、パッケージに書かれた淹れ方をきちんと守ることで、きちんと紅茶を楽しむことができます。実際、紅茶大国として知られているイギリスでも、普段楽しむ紅茶はほとんどがティーバッグ。もちろんきちんとポットとリーフで紅茶を淹れることはありますが、それはお客さんを招いたり、ホテルのティーサロンでお茶を楽しんだりと言った場合に限られます。
特に最近は日本でも、一般的なスーパーでも売られているティーバッグの種類が非常に豊富になっているため、自分好みの紅茶を見つけることができるでしょう。
1-2濃くて渋いときはお湯を足す
紅茶があまり好きではないという人の中には、紅茶独特の渋みを敬遠する方も少なくありません。その場合、抽出時間が長すぎて、濃くて渋い風味が出過ぎているという場合があります。また、茶葉の種類によってはどうしても渋みの強いものもあります。そういった場合、おすすめなのが「お湯を足す」という方法です。すでに抽出された紅茶にお湯を足すというと、ルール違反のように思われるかもしれませんが、実はこれは珍しいことではありません。むしろ、紅茶にこだわりが強い人の中には、自分なりにベストな香りや渋みを持っている人が多く、そういう人はお湯を足すことで自分好みの紅茶の状態に近づけることがあります。もし、紅茶が渋いと感じるなら、お湯を少しずつ足すことで、好みの味にカスタムすることがおすすめです。
1-3ミルクティーにして飲む
もし紅茶の渋みがどうしてもダメという場合、ミルクティーにしてみるのはいかがでしょうか。濃い目に出した紅茶にたっぷりの砂糖を淹れたミルクティーは、イギリスでも代表的な飲み物のひとつ。ミルクティーは飲みやすいだけでなく、紅茶本来の魅力を引き出してくれる飲み方。特に少しミルクを温めると、さらなるおいしさを楽しむことができます。
2-1必要な道具、材料
紅茶を淹れるときに必要なのは、お湯を沸かす道具と紅茶を抽出するポット、そして茶葉の三つです。といっても専用のものを購入する必要はありません。
たとえば、お湯を沸かすのは、どこの家庭にもあるヤカンを使えばOKです。ただし、このときひとつだけ注意したいのは、鉄製のやかんは使わないということ。鉄製のやかんを使うと、やかんから流出した鉄分が紅茶に含まれるタンニンと反応、黒ずんだ色の紅茶になってしまいます。さらに、紅茶自体の味も変わってしまうため、できれば鉄製のやかんは避けたほうがいいでしょう。
また、ポットはどのようなものでも構いませんが、できればガラス製の容量の多いものがおすすめです。容量が多いものは、ポットの中で紅茶の茶葉がきちんと循環することで、本来の風味を抽出することができます。
このほかにも、茶葉の量を計るティーメジャーなどがあると便利です。
2-2基本的な淹れ方
紅茶を淹れるときは、まず新鮮なお水を使用しましょう。新鮮なお水には酸素がたっぷり含まれているので、紅茶の風味や香りを存分に引き出すことができます。
紅茶を淹れるには、軟水が適しているとされますが、日本の場合、ほとんどの地域で水道の蛇口から出るのは軟水なので、それをそのまま沸かせば問題はありません。逆に、高価なミネラルウォーターなどは硬水が多いため、使用するときには注意が必要です。紅茶を淹れるためのお湯を沸かすときには、熱湯であることが重要。しっかりと湯気が出て、お湯が沸騰するのを確認しましょう。
次に、沸騰したお湯をティーポットに注ぎ、お湯が冷めないようにティーポットを温めておきます。
ティーポットが温まったら、茶葉を淹れますが、そのまま飲むストレートティーの場合には4~5グラム、ミルクティーの場合には濃い目が良いため、6~8グラムが目安になります。ティーメジャーなら、ストレートティーはスプーン一杯分、ミルクティーはスプーン一杯半から二杯となります。
茶葉を入れたら、そこにお湯を注ぎます。そして蓋をして蒸らしますが、ダージリンなら五分、他の茶葉なら三分が基本の時間です。これ以上、長くても短くても美味しい紅茶を楽しむことはできないので、少々面倒でも、ここはきちんとタイマーで時間を計ったほうがよいでしょう。
蒸らしの時間が終われば、いよいよ紅茶をカップに注ぎますが、この段階では、ポットの中では紅茶の濃度に違いがあります。そのため、スプーンなどを使用して、上下を軽く混ぜて全体を均一にしておきましょう。ただし、あまり乱暴にやりすぎると紅茶が苦くなってしまうことがあるので注意しましょう。
紅茶を淹れるのは難しいというイメージがありますが、実はそれほど難しいものではありません。必要なのは、しっかりお湯を沸かす、茶葉や時間を計るといったちょっとしたポイント。ここさえ押さえておけば、誰でも美味しい紅茶を淹れることができます。
03紅茶を買うときの注意点
美味しい紅茶を楽しむときには、淹れ方だけでなく紅茶を買うときにもちょっとした注意が必要です。
3-1パッケージに傷みがないか
スーパーなどで紅茶を買うときには、パッケージに傷や穴がないかを確認しましょう。紅茶は乾燥している茶葉ですが、実は非常に劣化しやすく、すぐに風味や香りが抜けてしまいます。パッケージに傷みがある場合、すでに紅茶としての美味しさが失われている場合があります。もし紅茶を購入するときには、鮮度が保てるように、密閉できるアルミパック入りのものがおすすめです。
3-2大容量より2週間ぐらいで飲みきれる量がベスト
紅茶を購入するとき、大容量のほうが価格が安いため、ついついそちらを買い求めてしまいがちですが、よほど大量に紅茶を飲む家庭ではない限り、大容量のものはどうしてもあまりがちになってしまいます。そうすると、茶葉から香りや旨みが抜けてしまい、美味しい紅茶が楽しめません。少々割高になっても、二週間程度で飲み切れる量を購入すると、最後まで美味しい状態の紅茶を楽しむことができます。
3-3賞味期限で鮮度をみる
すでに説明したように、紅茶は鮮度が大切。そのためのヒントになるのが賞味期限です。もし賞味期限が近付いている場合、すでにかなりの時間が経過していることが考えられます。そのため、美味しい紅茶を楽しみたいという場合には、賞味期限に余裕があるものを選ぶとよいでしょう。
01まとめ
まず、初心者におすすめの紅茶としては、バランスのとれた味わいのアッサムやダージリンなどが良いでしょう。これらの産地の紅茶は、渋みや苦みが控えめで、ミルクや砂糖を加えることでより美味しく楽しめます。
次に、紅茶の基本的な淹れ方ですが、ポイントは「適温の湯」と「十分な抽出時間」です。沸騰した直後の湯ではなく、95度前後の温度が最適です。また、茶葉を3分以上浸けることで、紅茶本来の深い香りと旨みが引き出されます。
ミルクの使い方ですが、紅茶を注いだ後、最後にミルクを加えるのがコツです。ミルクの量は、紅茶の3割程度が目安ですが、好みによって調整しましょう。
砂糖の使い方についても、少量から始め、自分好みの甘さに調整するのがおいしい飲み方のポイントです。特に、苦みや渋みの強い紅茶には砂糖が良く合います。
最後に、茶葉の保管方法ですが、光や空気、湿気を避けて、密閉容器で冷暗所に保管することが大切です。茶葉は時間と共に酸化が進むため、できるだけ早く使い切るのが望ましいでしょう。
以上が、初心者におすすめの紅茶とおいしい淹れ方のポイントのまとめです。これらのことを意識しながら、自分好みの紅茶の楽しみ方を見つけていきましょう。
3-1パッケージに傷みがないか
スーパーなどで紅茶を買うときには、パッケージに傷や穴がないかを確認しましょう。紅茶は乾燥している茶葉ですが、実は非常に劣化しやすく、すぐに風味や香りが抜けてしまいます。パッケージに傷みがある場合、すでに紅茶としての美味しさが失われている場合があります。もし紅茶を購入するときには、鮮度が保てるように、密閉できるアルミパック入りのものがおすすめです。
3-2大容量より2週間ぐらいで飲みきれる量がベスト
紅茶を購入するとき、大容量のほうが価格が安いため、ついついそちらを買い求めてしまいがちですが、よほど大量に紅茶を飲む家庭ではない限り、大容量のものはどうしてもあまりがちになってしまいます。そうすると、茶葉から香りや旨みが抜けてしまい、美味しい紅茶が楽しめません。少々割高になっても、二週間程度で飲み切れる量を購入すると、最後まで美味しい状態の紅茶を楽しむことができます。
3-3賞味期限で鮮度をみる
すでに説明したように、紅茶は鮮度が大切。そのためのヒントになるのが賞味期限です。もし賞味期限が近付いている場合、すでにかなりの時間が経過していることが考えられます。そのため、美味しい紅茶を楽しみたいという場合には、賞味期限に余裕があるものを選ぶとよいでしょう。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。
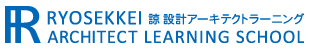
- 紅茶の誕生と歴史と文化を詳しく解説
- 紅茶の基本知識とは?趣味として始める紅茶の世界!
- 紅茶を飲む時の注意すべきポイントと基本マナーとは?
- 紅茶の道具と選ぶときのポイントとは
- 紅茶の茶葉の種類とは?分類方法や種類別の詳しい特徴を紹介
- 紅茶の持つ健康効果とは? 様々な効能が期待できる紅茶の魅力!
- 紅茶に関わる仕事と資格とは
- 家庭でできる紅茶の作り方と注意点
- 紅茶をブレンドする目的とは?実践的な紅茶ブレンドの方法を解説
- 紅茶の淹れ方や注意点とは?!初心者におすすめの基本を解説
- 水筒で紅茶を楽しむ為に、これだけは絶対に知っておきたい4項目
- 紅茶にレモンを入れると色が薄くなる不思議
- クリームダウンを防げば、アイスティーはもっとおいしくなる!
- 簡単にできる紅茶クッキーのレシピを3つご紹介
- 紅茶には身体にいい効能がいっぱい!
- 紅茶と相性のいいお菓子・食べ物について
- 紅茶のおとも「ミルクと砂糖」について
- 紅茶とハーブティーの違い
- 紅茶で服を染めてみよう!紅茶染めの楽しみ
- 紅茶を入れる道具についてのポイント
- 紅茶とお酒を合わせて楽しむ方法
- 紅茶を使ったカクテル
- ティーカップに持ち手が付いたわけ
- 紅茶を飲んでちょっと休憩する時に使ってみたい英語表現
- 紅茶に入れるもの
- 紅茶の保存容器いろいろ
- 初心者でも簡単!紅茶染め
- 紅茶の種類とは?紅茶の専門家になるための紅茶資格!
- 紅茶資格おすすめ7選!資格の種類や取得方法・活用法を解説!