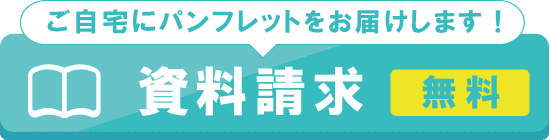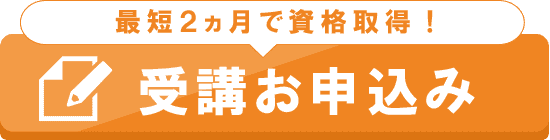紅茶
紅茶の歴史と文化
記事作成日:2024.07.04
ゆったりとしたティータイムに紅茶は欠かせないものです。こだわりの茶葉やカップで過ごすひとときは何にも勝るものですが、それではこの紅茶はいつごろから楽しまれているものなのでしょうか。今回は知っておくと楽しい紅茶の歴史や文化についてご紹介します。

01紅茶が誕生したのはいつ?
紅茶というと、まず頭に浮かぶのがイギリスです。イギリスには多くの紅茶のメーカーが存在し、市民の間にもアフタヌーンティーなど、紅茶を楽しむ文化は浸透しています。
しかし、実はお茶を楽しむ文化の発祥は中国にあります。
もともと、お茶の原産地は中国の南部、現在の雲南省からチベットにかけての山岳地帯。一説によると、紀元前二千七百年ごろには、茶葉は不老長寿に効く万病薬として、中国の伝説上の存在である神農皇帝により発見されたとも伝わっています。その後も霊薬として身分の高い人々の間で珍重されていたお茶ですが、やがて四世紀ごろになると本格的な栽培が始まり、七世紀ごろになると貴族階級の間で飲み物として広がるようになりました。また、八世紀の中頃には、中国で世界最初の専門書が出版されるなどお茶の文化が広がっていきます。このときに飲まれていたのは、お茶の葉をお湯によって抽出した、現在の緑茶に似たものでしたが、やがてお茶の生産が盛んになり、一般の人々の間でもお茶を飲む習慣が広がった十世紀から十三世紀にかけて、お茶の葉を発酵させ、それまでとは違う味わいを楽しむことができる発酵茶が登場します。
通常、紅茶やウーロン茶、緑茶は種類が違うものと考えられがちですが、実は根っこは同じもの。緑茶はお茶を発酵させずそのまま楽しむもので、発酵の度合いが深まるにしたがって、ウーロン茶、紅茶となり、色も味わいも変わっていきます。
やがて、中国で発展したお茶は大航海時代に入った十七世紀にはヨーロッパに伝えられます。最初に中国産のお茶が上陸したのがオランダでした。当時のオランダの東インド会社が中国産のお茶を持ち帰り、その後ヨーロッパ全体にお茶を飲む習慣が広がっていきました。
02イギリスで紅茶文化が発達
大航海時代になると、中国だけでなくヨーロッパ全体に広がった紅茶ですが、それではなぜヨーロッパの中でもイギリスが紅茶の国というイメージになったのでしょうか。
これには、当時の国際情勢が大きく関係しています。
十七世紀の中頃、ポルトガルのキャサリン王女がイギリス王室のチャールズ二世の元に嫁ぎます。当時は、ポルトガルは世界中に進出、各地に植民地を抱えていました。そんな大国であったポルトガルのキャサリン王女が英国王室に嫁ぐにあたって持ち込んだのが、大量の紅茶と砂糖。紅茶も砂糖も、当時は非常にぜいたくで高価な品物で、それらを大量に買うためには莫大な財力が必要でした。もしかすると、キャサリン王女がこれらを持ち込むことによって、ポルトガルの国威を知らしめる効果を狙ったのかもしれません。
さらに、キャサリン王女が紅茶を持ち込む前までは、ヨーロッパでは紅茶は東洋から来た万病に効く霊薬という、いわば神秘的な薬の一種という存在でした。しかしキャサリン妃によって、紅茶に砂糖を入れて楽しむことによって、お茶を飲むという習慣が社交の一環としてイギリスの貴族社会に広がっていきます。そのため、紅茶の人気が一気に高まりますが、そこで問題も生まれます。それは当時の輸入体制。
当時はオランダの東インド会社が紅茶の貿易を独占していましたが、イギリスにとっては非常に不利な状況でした。そこでイギリスがオランダからのお茶の輸入を禁じる法律を作ったことをきっかけに、第三次英蘭戦争が勃発します。イギリスはこの戦争に勝利、お茶の輸入の権利を奪うとともに、中国・福建省のアモイを拠点として、大規模なお茶の輸入を開始します。このお茶の輸入が、その後の大英帝国の繁栄を支えることになるのですが、その後、イギリスはお茶の貿易の独占を廃止、この頃には上流階級の間ではすっかり紅茶を楽しむ文化が広がっていきます。
その後、ヨーロッパ諸国の中でも真っ先に産業革命を果たしたイギリスでは、上流階級だけでなく、中産階級にも紅茶の文化が広がり、人々の生活に定着するようになりました。さらに十九世紀に入ってからはイギリスは植民地であるインドやスリランカでのお茶の栽培に成功、これにより、お茶の生産量は拡大し、イギリスといえば紅茶というイメージが定着するようになりました。この英国のお茶文化を代表するのがアフタヌーンティーです。アフタヌーンティーは午後四時ごろから五時ごろにかけての夕方の時間帯に、紅茶とともにお菓子や軽食を楽しむお茶会で、十九世紀の後半、上流階級の人々の間で、気軽な社交を目的に始まった文化だと言われています。
アフタヌーンティーといえば、誰もが思い浮かべるのが三段にお皿が重ねられたケーキスタンド。正式には、一番下のお皿がサンドイッチ、真ん中にフルーツなどを使用したケーキ、一番上にスコーンなどの焼き菓子が載せられたスタンドは、まさにアフタヌーンティーを楽しむにふさわしいリッチな雰囲気です。アフタヌーンティーではカップの持ち方や料理を食べる順序などの作法も決まっていますが、現在では従来の作法にこだわらない自由なスタイルのものも登場しています。
また、イギリスにはアフタヌーンティー以外にも朝ベッドに入ったままや、ベッドサイドで紅茶を楽しむ「アーリーモーニングティー」、朝食とともに紅茶を楽しむ「ブレックファストティー」、料理とともに紅茶を飲む「ハイティー」、夕食後のくつろぎの時間に行われる「アフターディナーティー」など様々な紅茶の習慣があり、生活の中に深く紅茶の文化が浸透していることがうかがえます。
03紅茶が日本へ
それでは、紅茶が日本に入ってきたのは、いつ頃になってからなのでしょうか。
言うまでもなく、お茶を楽しむ文化は日本に根付いていましたが、あくまでも未発酵のお茶が中心。一部の地域では発酵茶が生産されていましたが、それはあくまでも少数で、明治になる以前は、長崎の出島など、一部地域で楽しまれているものでした。
しかし、明治になると日本はヨーロッパ諸国との貿易を活発化、それとともに日本にも紅茶がもたらされます。最初に日本で大掛かりに紅茶を販売したのが、輸入食材を扱っていた明治屋。明治屋が日本初の海外産紅茶として、リプトン紅茶を輸入、販売したところ流行の最先端の飲み物として瞬く間に上流階級の人々の人気を獲得。当時のリプトン紅茶は、スリランカで大規模な茶園経営を行い、イギリス王室の御用達ともなる世界最大の紅茶メーカー。日本でも大人気となったリプトンは、昭和の始めには日本で初のティーハウスを京都にオープンさせるなど、庶民の間にも広がっていきます。
その後、戦争が終わるとティーバッグの自動包装機械の導入により、日本国内でもティーバッグ紅茶の生産が開始、外国産紅茶の輸入が自由化されたこともあり、日本でも本格的な紅茶が楽しめるようになりました。
04まとめ
紅茶を楽しむとき、茶葉やカップの知識はもちろん、紅茶にまつわる歴史や文化を知っていればさらに楽しみが広がります。もしもっと紅茶を楽しみたい、そう思った方は、紅茶について少し勉強してみると、もっとティータイムが楽しめるかもしれませんね。
紅茶というと、まず頭に浮かぶのがイギリスです。イギリスには多くの紅茶のメーカーが存在し、市民の間にもアフタヌーンティーなど、紅茶を楽しむ文化は浸透しています。
しかし、実はお茶を楽しむ文化の発祥は中国にあります。
もともと、お茶の原産地は中国の南部、現在の雲南省からチベットにかけての山岳地帯。一説によると、紀元前二千七百年ごろには、茶葉は不老長寿に効く万病薬として、中国の伝説上の存在である神農皇帝により発見されたとも伝わっています。その後も霊薬として身分の高い人々の間で珍重されていたお茶ですが、やがて四世紀ごろになると本格的な栽培が始まり、七世紀ごろになると貴族階級の間で飲み物として広がるようになりました。また、八世紀の中頃には、中国で世界最初の専門書が出版されるなどお茶の文化が広がっていきます。このときに飲まれていたのは、お茶の葉をお湯によって抽出した、現在の緑茶に似たものでしたが、やがてお茶の生産が盛んになり、一般の人々の間でもお茶を飲む習慣が広がった十世紀から十三世紀にかけて、お茶の葉を発酵させ、それまでとは違う味わいを楽しむことができる発酵茶が登場します。
通常、紅茶やウーロン茶、緑茶は種類が違うものと考えられがちですが、実は根っこは同じもの。緑茶はお茶を発酵させずそのまま楽しむもので、発酵の度合いが深まるにしたがって、ウーロン茶、紅茶となり、色も味わいも変わっていきます。
やがて、中国で発展したお茶は大航海時代に入った十七世紀にはヨーロッパに伝えられます。最初に中国産のお茶が上陸したのがオランダでした。当時のオランダの東インド会社が中国産のお茶を持ち帰り、その後ヨーロッパ全体にお茶を飲む習慣が広がっていきました。
しかし、実はお茶を楽しむ文化の発祥は中国にあります。
もともと、お茶の原産地は中国の南部、現在の雲南省からチベットにかけての山岳地帯。一説によると、紀元前二千七百年ごろには、茶葉は不老長寿に効く万病薬として、中国の伝説上の存在である神農皇帝により発見されたとも伝わっています。その後も霊薬として身分の高い人々の間で珍重されていたお茶ですが、やがて四世紀ごろになると本格的な栽培が始まり、七世紀ごろになると貴族階級の間で飲み物として広がるようになりました。また、八世紀の中頃には、中国で世界最初の専門書が出版されるなどお茶の文化が広がっていきます。このときに飲まれていたのは、お茶の葉をお湯によって抽出した、現在の緑茶に似たものでしたが、やがてお茶の生産が盛んになり、一般の人々の間でもお茶を飲む習慣が広がった十世紀から十三世紀にかけて、お茶の葉を発酵させ、それまでとは違う味わいを楽しむことができる発酵茶が登場します。
通常、紅茶やウーロン茶、緑茶は種類が違うものと考えられがちですが、実は根っこは同じもの。緑茶はお茶を発酵させずそのまま楽しむもので、発酵の度合いが深まるにしたがって、ウーロン茶、紅茶となり、色も味わいも変わっていきます。
やがて、中国で発展したお茶は大航海時代に入った十七世紀にはヨーロッパに伝えられます。最初に中国産のお茶が上陸したのがオランダでした。当時のオランダの東インド会社が中国産のお茶を持ち帰り、その後ヨーロッパ全体にお茶を飲む習慣が広がっていきました。
大航海時代になると、中国だけでなくヨーロッパ全体に広がった紅茶ですが、それではなぜヨーロッパの中でもイギリスが紅茶の国というイメージになったのでしょうか。
これには、当時の国際情勢が大きく関係しています。
十七世紀の中頃、ポルトガルのキャサリン王女がイギリス王室のチャールズ二世の元に嫁ぎます。当時は、ポルトガルは世界中に進出、各地に植民地を抱えていました。そんな大国であったポルトガルのキャサリン王女が英国王室に嫁ぐにあたって持ち込んだのが、大量の紅茶と砂糖。紅茶も砂糖も、当時は非常にぜいたくで高価な品物で、それらを大量に買うためには莫大な財力が必要でした。もしかすると、キャサリン王女がこれらを持ち込むことによって、ポルトガルの国威を知らしめる効果を狙ったのかもしれません。
さらに、キャサリン王女が紅茶を持ち込む前までは、ヨーロッパでは紅茶は東洋から来た万病に効く霊薬という、いわば神秘的な薬の一種という存在でした。しかしキャサリン妃によって、紅茶に砂糖を入れて楽しむことによって、お茶を飲むという習慣が社交の一環としてイギリスの貴族社会に広がっていきます。そのため、紅茶の人気が一気に高まりますが、そこで問題も生まれます。それは当時の輸入体制。
当時はオランダの東インド会社が紅茶の貿易を独占していましたが、イギリスにとっては非常に不利な状況でした。そこでイギリスがオランダからのお茶の輸入を禁じる法律を作ったことをきっかけに、第三次英蘭戦争が勃発します。イギリスはこの戦争に勝利、お茶の輸入の権利を奪うとともに、中国・福建省のアモイを拠点として、大規模なお茶の輸入を開始します。このお茶の輸入が、その後の大英帝国の繁栄を支えることになるのですが、その後、イギリスはお茶の貿易の独占を廃止、この頃には上流階級の間ではすっかり紅茶を楽しむ文化が広がっていきます。
その後、ヨーロッパ諸国の中でも真っ先に産業革命を果たしたイギリスでは、上流階級だけでなく、中産階級にも紅茶の文化が広がり、人々の生活に定着するようになりました。さらに十九世紀に入ってからはイギリスは植民地であるインドやスリランカでのお茶の栽培に成功、これにより、お茶の生産量は拡大し、イギリスといえば紅茶というイメージが定着するようになりました。この英国のお茶文化を代表するのがアフタヌーンティーです。アフタヌーンティーは午後四時ごろから五時ごろにかけての夕方の時間帯に、紅茶とともにお菓子や軽食を楽しむお茶会で、十九世紀の後半、上流階級の人々の間で、気軽な社交を目的に始まった文化だと言われています。
アフタヌーンティーといえば、誰もが思い浮かべるのが三段にお皿が重ねられたケーキスタンド。正式には、一番下のお皿がサンドイッチ、真ん中にフルーツなどを使用したケーキ、一番上にスコーンなどの焼き菓子が載せられたスタンドは、まさにアフタヌーンティーを楽しむにふさわしいリッチな雰囲気です。アフタヌーンティーではカップの持ち方や料理を食べる順序などの作法も決まっていますが、現在では従来の作法にこだわらない自由なスタイルのものも登場しています。
また、イギリスにはアフタヌーンティー以外にも朝ベッドに入ったままや、ベッドサイドで紅茶を楽しむ「アーリーモーニングティー」、朝食とともに紅茶を楽しむ「ブレックファストティー」、料理とともに紅茶を飲む「ハイティー」、夕食後のくつろぎの時間に行われる「アフターディナーティー」など様々な紅茶の習慣があり、生活の中に深く紅茶の文化が浸透していることがうかがえます。
これには、当時の国際情勢が大きく関係しています。
十七世紀の中頃、ポルトガルのキャサリン王女がイギリス王室のチャールズ二世の元に嫁ぎます。当時は、ポルトガルは世界中に進出、各地に植民地を抱えていました。そんな大国であったポルトガルのキャサリン王女が英国王室に嫁ぐにあたって持ち込んだのが、大量の紅茶と砂糖。紅茶も砂糖も、当時は非常にぜいたくで高価な品物で、それらを大量に買うためには莫大な財力が必要でした。もしかすると、キャサリン王女がこれらを持ち込むことによって、ポルトガルの国威を知らしめる効果を狙ったのかもしれません。
さらに、キャサリン王女が紅茶を持ち込む前までは、ヨーロッパでは紅茶は東洋から来た万病に効く霊薬という、いわば神秘的な薬の一種という存在でした。しかしキャサリン妃によって、紅茶に砂糖を入れて楽しむことによって、お茶を飲むという習慣が社交の一環としてイギリスの貴族社会に広がっていきます。そのため、紅茶の人気が一気に高まりますが、そこで問題も生まれます。それは当時の輸入体制。
当時はオランダの東インド会社が紅茶の貿易を独占していましたが、イギリスにとっては非常に不利な状況でした。そこでイギリスがオランダからのお茶の輸入を禁じる法律を作ったことをきっかけに、第三次英蘭戦争が勃発します。イギリスはこの戦争に勝利、お茶の輸入の権利を奪うとともに、中国・福建省のアモイを拠点として、大規模なお茶の輸入を開始します。このお茶の輸入が、その後の大英帝国の繁栄を支えることになるのですが、その後、イギリスはお茶の貿易の独占を廃止、この頃には上流階級の間ではすっかり紅茶を楽しむ文化が広がっていきます。
その後、ヨーロッパ諸国の中でも真っ先に産業革命を果たしたイギリスでは、上流階級だけでなく、中産階級にも紅茶の文化が広がり、人々の生活に定着するようになりました。さらに十九世紀に入ってからはイギリスは植民地であるインドやスリランカでのお茶の栽培に成功、これにより、お茶の生産量は拡大し、イギリスといえば紅茶というイメージが定着するようになりました。この英国のお茶文化を代表するのがアフタヌーンティーです。アフタヌーンティーは午後四時ごろから五時ごろにかけての夕方の時間帯に、紅茶とともにお菓子や軽食を楽しむお茶会で、十九世紀の後半、上流階級の人々の間で、気軽な社交を目的に始まった文化だと言われています。
アフタヌーンティーといえば、誰もが思い浮かべるのが三段にお皿が重ねられたケーキスタンド。正式には、一番下のお皿がサンドイッチ、真ん中にフルーツなどを使用したケーキ、一番上にスコーンなどの焼き菓子が載せられたスタンドは、まさにアフタヌーンティーを楽しむにふさわしいリッチな雰囲気です。アフタヌーンティーではカップの持ち方や料理を食べる順序などの作法も決まっていますが、現在では従来の作法にこだわらない自由なスタイルのものも登場しています。
また、イギリスにはアフタヌーンティー以外にも朝ベッドに入ったままや、ベッドサイドで紅茶を楽しむ「アーリーモーニングティー」、朝食とともに紅茶を楽しむ「ブレックファストティー」、料理とともに紅茶を飲む「ハイティー」、夕食後のくつろぎの時間に行われる「アフターディナーティー」など様々な紅茶の習慣があり、生活の中に深く紅茶の文化が浸透していることがうかがえます。
03紅茶が日本へ
それでは、紅茶が日本に入ってきたのは、いつ頃になってからなのでしょうか。
言うまでもなく、お茶を楽しむ文化は日本に根付いていましたが、あくまでも未発酵のお茶が中心。一部の地域では発酵茶が生産されていましたが、それはあくまでも少数で、明治になる以前は、長崎の出島など、一部地域で楽しまれているものでした。
しかし、明治になると日本はヨーロッパ諸国との貿易を活発化、それとともに日本にも紅茶がもたらされます。最初に日本で大掛かりに紅茶を販売したのが、輸入食材を扱っていた明治屋。明治屋が日本初の海外産紅茶として、リプトン紅茶を輸入、販売したところ流行の最先端の飲み物として瞬く間に上流階級の人々の人気を獲得。当時のリプトン紅茶は、スリランカで大規模な茶園経営を行い、イギリス王室の御用達ともなる世界最大の紅茶メーカー。日本でも大人気となったリプトンは、昭和の始めには日本で初のティーハウスを京都にオープンさせるなど、庶民の間にも広がっていきます。
その後、戦争が終わるとティーバッグの自動包装機械の導入により、日本国内でもティーバッグ紅茶の生産が開始、外国産紅茶の輸入が自由化されたこともあり、日本でも本格的な紅茶が楽しめるようになりました。
04まとめ
紅茶を楽しむとき、茶葉やカップの知識はもちろん、紅茶にまつわる歴史や文化を知っていればさらに楽しみが広がります。もしもっと紅茶を楽しみたい、そう思った方は、紅茶について少し勉強してみると、もっとティータイムが楽しめるかもしれませんね。
それでは、紅茶が日本に入ってきたのは、いつ頃になってからなのでしょうか。
言うまでもなく、お茶を楽しむ文化は日本に根付いていましたが、あくまでも未発酵のお茶が中心。一部の地域では発酵茶が生産されていましたが、それはあくまでも少数で、明治になる以前は、長崎の出島など、一部地域で楽しまれているものでした。
しかし、明治になると日本はヨーロッパ諸国との貿易を活発化、それとともに日本にも紅茶がもたらされます。最初に日本で大掛かりに紅茶を販売したのが、輸入食材を扱っていた明治屋。明治屋が日本初の海外産紅茶として、リプトン紅茶を輸入、販売したところ流行の最先端の飲み物として瞬く間に上流階級の人々の人気を獲得。当時のリプトン紅茶は、スリランカで大規模な茶園経営を行い、イギリス王室の御用達ともなる世界最大の紅茶メーカー。日本でも大人気となったリプトンは、昭和の始めには日本で初のティーハウスを京都にオープンさせるなど、庶民の間にも広がっていきます。
その後、戦争が終わるとティーバッグの自動包装機械の導入により、日本国内でもティーバッグ紅茶の生産が開始、外国産紅茶の輸入が自由化されたこともあり、日本でも本格的な紅茶が楽しめるようになりました。
言うまでもなく、お茶を楽しむ文化は日本に根付いていましたが、あくまでも未発酵のお茶が中心。一部の地域では発酵茶が生産されていましたが、それはあくまでも少数で、明治になる以前は、長崎の出島など、一部地域で楽しまれているものでした。
しかし、明治になると日本はヨーロッパ諸国との貿易を活発化、それとともに日本にも紅茶がもたらされます。最初に日本で大掛かりに紅茶を販売したのが、輸入食材を扱っていた明治屋。明治屋が日本初の海外産紅茶として、リプトン紅茶を輸入、販売したところ流行の最先端の飲み物として瞬く間に上流階級の人々の人気を獲得。当時のリプトン紅茶は、スリランカで大規模な茶園経営を行い、イギリス王室の御用達ともなる世界最大の紅茶メーカー。日本でも大人気となったリプトンは、昭和の始めには日本で初のティーハウスを京都にオープンさせるなど、庶民の間にも広がっていきます。
その後、戦争が終わるとティーバッグの自動包装機械の導入により、日本国内でもティーバッグ紅茶の生産が開始、外国産紅茶の輸入が自由化されたこともあり、日本でも本格的な紅茶が楽しめるようになりました。
紅茶を楽しむとき、茶葉やカップの知識はもちろん、紅茶にまつわる歴史や文化を知っていればさらに楽しみが広がります。もしもっと紅茶を楽しみたい、そう思った方は、紅茶について少し勉強してみると、もっとティータイムが楽しめるかもしれませんね。
この講座は!プロの監修を受けています!
講座のテキスト、問題集や添削課題と共に、プロの先生によって監修されています。

片野圭子 先生
紅茶のけいこ運営
1979年生まれ。茨城県つくば市出身。紅茶専門店のスタッフを経験。その後紅茶メインの小さなお茶会を開催。 現在は日本ティーコンシェルジュ協会つくば校を開校。ティーコンシェルジュとしてお稽古教室や資格講座、お茶会を開催。

70,000人以上が受講申し込みしている諒設計アーキテクトラーニングの通信講座
あなたも早速受講して、資格を取得しましょう!
関連記事を見る
- 紅茶の歴史と文化
- 紅茶の基本知識
- 紅茶を飲む時の正しいマナー
- 紅茶の道具と選ぶときのポイントとは
- 紅茶の茶葉の種類と特徴
- 紅茶の持つ健康効果とは
- 紅茶に関わる仕事と資格とは
- 家庭でできる紅茶の作り方と注意点
- 紅茶をブレンドする目的とブレンドの方法
- 初心者におすすめの紅茶と基本の淹れ方
- 水筒で紅茶を楽しむ為に、これだけは絶対に知っておきたい4項目
- 紅茶にレモンを入れると色が薄くなる不思議
- クリームダウンを防げば、アイスティーはもっとおいしくなる!
- 簡単にできる紅茶クッキーのレシピを3つご紹介
- 紅茶には身体にいい効能がいっぱい!
- 紅茶と相性のいいお菓子・食べ物について
- 紅茶のおとも「ミルクと砂糖」について
- 紅茶とハーブティーの違い
- 紅茶で服を染めてみよう!紅茶染めの楽しみ
- 紅茶を入れる道具についてのポイント
- 紅茶とお酒を合わせて楽しむ方法
- 紅茶を使ったカクテル
- ティーカップに持ち手が付いたわけ
- 紅茶を飲んでちょっと休憩する時に使ってみたい英語表現
- 紅茶に入れるもの
- 紅茶の保存容器いろいろ
- 初心者でも簡単!紅茶染め
- 紅茶の専門家になるための紅茶資格について
- 紅茶資格おすすめ7選!資格の種類や取得方法・活用法を解説!