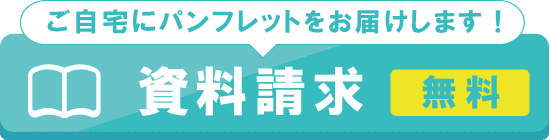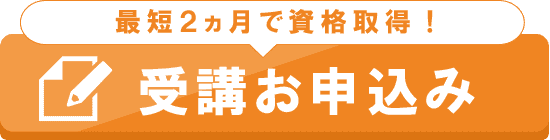紅茶の基本知識
紅茶は日常生活で味わうだけでなく、趣味としても楽しむことができます。紅茶の種類や、紅茶を淹れるときに必要なものを揃えていく時間は忙しい生活をリセットするのに最適。さらに紅茶の趣味は、将来の仕事に活かせる可能性もあります。今回は趣味から始める紅茶の基本的な知識や、将来の可能性などについてご紹介します。

- 目次
01基本的な紅茶のはじめ方
紅茶は歴史の古いもので、紅茶を淹れる作法や道具など、なんとなく敷居の高さを感じることもあります。では、趣味として紅茶を始めるときには、どこからスタートするのがよいのでしょうか。
1-1お店の紅茶めぐりをする
趣味としての紅茶を始めるとき、おすすめしたいのが紅茶の専門店をめぐってみること。ほとんどの喫茶店やカフェであれば、紅茶を扱っているものですが、紅茶専門店では種類豊富な茶葉が常に用意されています。また、お店のスタッフも非常に知識があるため、ちょっと気になったことを質問すればすぐに答えが返ってくるのも魅力のひとつ。本を読んだり、ネットを見たりしてもある程度の知識は身に付くものですが、実際に紅茶を日常的に扱っている人から話を聞くことで、より深い知識を得ることができます。
紅茶専門店で味わう紅茶は普段のものとはきっと一味ちがうはず。よく名前を聞く茶葉にも旬があり、季節によって美味しいものも異なるため、自分好みの紅茶を探しているという人にもおすすめです。お店によっては茶葉の販売を行っているところもあるため、自分で気に入ったものや、店員さんにおすすめしてもらったものを購入して帰る、紅茶を淹れるときの分量や方法、蒸らす時間などのコツを聞いてみるのもよいかもしれません。
1-2自分で淹れて紅茶を飲んでみる
専門店で紅茶を味わったあとは、自分で紅茶を実際に淹れてみましょう。
といっても紅茶を飲んだことがないという人はほとんどいないかもしれません。でも、多くの場合、ティーバッグをカップに入れてお湯を注いでいるということが多いかもしれません。しかし、実はティーバッグでも正しい淹れ方があります。一度はパッケージの裏などの説明をしっかり読んで、正しい淹れ方をしてみると、味の違いに驚いてしまうはず。また、最近ではごく普通のスーパーでも、複数の茶葉がティーバッグで売られています。その味や種類の違いを楽しんでみるのもよいでしょう。
ティーバッグで紅茶の魅力を発見したら、次はやはりリーフでお茶を淹れてみましょう。
02紅茶を淹れるのに必要な物
では、茶葉から紅茶を淹れる場合には、どのような道具が必要になるのでしょうか。
2-1茶葉
まず紅茶を淹れるときには、茶葉が必要になります。茶葉はスーパーや輸入食料品のお店でも購入することができますが、おすすめは、紅茶の専門店で購入すること。というのも、乾燥している茶葉でも鮮度が非常に重要で、鮮度が落ちた茶葉を使った場合、紅茶の味や香りを楽しむことができません。茶葉の管理は非常に繊細で難しいものですが、紅茶専門店では、茶葉の管理が適切に行われているため、家庭でも新鮮な茶葉を使用して紅茶を淹れることができます。なお、茶葉を選ぶときには店員さんに相談に乗ってもらうことがベスト。初心者でも飲みやすい渋みや香りが控え目なもの、逆にしっかりと旨みなどが楽しめるもの、華やかな香りのものなど、専門店では様々な種類の茶葉が扱われているため、自分の好みを伝えて相談に乗ってもらうとよいでしょう。
2-2ケトル
紅茶を淹れるときに必要なのがお湯です。それを沸かすのがケトル。ケトルはどこの家庭にもあるものですが、このときに大切なのは、酸素がしっかり含まれている新鮮なお水を短時間できちんと沸騰させるということ。
たとえば、銅のケトルは熱伝導率が良く、短期間でお湯が沸くのでおすすめです。そのほかにも、出力の高い電気式のケトルもよいでしょう。
もちろん、このためにケトルを買う必要はありませんが、注意したいのは鉄製のケトルを使用している場合。鉄製のケトルでお湯を沸かした場合、水の中に鉄分が流れ出して紅茶の中のタンニンと結合、紅茶の色が悪くなってしまいます。また、味自体も鉄の味が出てしまうため、風味が本来のものとは変わってしまいます。そのため、紅茶を淹れるときには、鉄製のケトルは避けたほうがよいでしょう。
2-3ポット
ポットは茶葉から紅茶を抽出するときに必要になります。このポットが紅茶を淹れるときには実はかなり重要。というのも、美味しい紅茶を淹れるためには、ポットの中で茶葉が踊るようにジャンピングすることが必要になりますが、容量が小さすぎる、形が悪いといった場合、紅茶の茶葉がポットの中で上手くジャンピングすることができず、上手く紅茶を抽出することができません。特に、ガラス以外の素材で出来ていると、きちんとジャンピングができているかどうか確認できないため、最初はガラス素材のポットを使用するのがおすすめです。
また、ポットを選ぶときに注意したいのが茶こし。茶こしは茶葉を切るときに必要になるもので、ポットについていると便利ですが、茶こしの形状によっては茶葉のジャンピングの妨げになることもあります。特に筒状の茶こしがついているポットは茶葉が動かなくなってしまうため、避けたほうがよいでしょう。上手くジャンピングを行うためには、ふたと茶こしが一体になっているものがおすすめです。
なお、紅茶のポットには抽出用のポットと、サーブ用のポットがありますが、最初は適量の抽出用のポットを用意して、一杯ごとに飲み切るのがよいでしょう。
2-4ティーカップ
少しゴージャスにティータイムを楽しみたいという場合、ティーカップに凝るのもおすすめです。特に、飲み口が薄い場合と厚い場合では紅茶の味にも影響があることもあります。といっても、高級なカップを揃える必要はありません。もし気に入ったものがあれば、薄手のものを買い求めて味の違いを確かめてみるのもよいでしょう。
2-5タイマー
紅茶の抽出時間を計るために必要になるのがタイマーです。紅茶は繊細なもので、長く置いておけばきちんと抽出できるかといえばそうではありません。長い時間茶葉をお湯に浸しておくと、紅茶本来の旨みや香りを損なってしまうこともあります。また、抽出時間が身近過ぎる場合、きちんと風味や香りを抽出することができません。
そのため、紅茶を抽出するときにはタイマーの使用がおすすめですが、特別に購入する必要はなく、キッチンタイマーや時計、スマホのタイマーなどで十分です。そのときは、三分、五分といった単位で計測できるものがおすすめです。
1-1お店の紅茶めぐりをする
趣味としての紅茶を始めるとき、おすすめしたいのが紅茶の専門店をめぐってみること。ほとんどの喫茶店やカフェであれば、紅茶を扱っているものですが、紅茶専門店では種類豊富な茶葉が常に用意されています。また、お店のスタッフも非常に知識があるため、ちょっと気になったことを質問すればすぐに答えが返ってくるのも魅力のひとつ。本を読んだり、ネットを見たりしてもある程度の知識は身に付くものですが、実際に紅茶を日常的に扱っている人から話を聞くことで、より深い知識を得ることができます。
紅茶専門店で味わう紅茶は普段のものとはきっと一味ちがうはず。よく名前を聞く茶葉にも旬があり、季節によって美味しいものも異なるため、自分好みの紅茶を探しているという人にもおすすめです。お店によっては茶葉の販売を行っているところもあるため、自分で気に入ったものや、店員さんにおすすめしてもらったものを購入して帰る、紅茶を淹れるときの分量や方法、蒸らす時間などのコツを聞いてみるのもよいかもしれません。
1-2自分で淹れて紅茶を飲んでみる
専門店で紅茶を味わったあとは、自分で紅茶を実際に淹れてみましょう。
といっても紅茶を飲んだことがないという人はほとんどいないかもしれません。でも、多くの場合、ティーバッグをカップに入れてお湯を注いでいるということが多いかもしれません。しかし、実はティーバッグでも正しい淹れ方があります。一度はパッケージの裏などの説明をしっかり読んで、正しい淹れ方をしてみると、味の違いに驚いてしまうはず。また、最近ではごく普通のスーパーでも、複数の茶葉がティーバッグで売られています。その味や種類の違いを楽しんでみるのもよいでしょう。
ティーバッグで紅茶の魅力を発見したら、次はやはりリーフでお茶を淹れてみましょう。
2-1茶葉
まず紅茶を淹れるときには、茶葉が必要になります。茶葉はスーパーや輸入食料品のお店でも購入することができますが、おすすめは、紅茶の専門店で購入すること。というのも、乾燥している茶葉でも鮮度が非常に重要で、鮮度が落ちた茶葉を使った場合、紅茶の味や香りを楽しむことができません。茶葉の管理は非常に繊細で難しいものですが、紅茶専門店では、茶葉の管理が適切に行われているため、家庭でも新鮮な茶葉を使用して紅茶を淹れることができます。なお、茶葉を選ぶときには店員さんに相談に乗ってもらうことがベスト。初心者でも飲みやすい渋みや香りが控え目なもの、逆にしっかりと旨みなどが楽しめるもの、華やかな香りのものなど、専門店では様々な種類の茶葉が扱われているため、自分の好みを伝えて相談に乗ってもらうとよいでしょう。
2-2ケトル
紅茶を淹れるときに必要なのがお湯です。それを沸かすのがケトル。ケトルはどこの家庭にもあるものですが、このときに大切なのは、酸素がしっかり含まれている新鮮なお水を短時間できちんと沸騰させるということ。
たとえば、銅のケトルは熱伝導率が良く、短期間でお湯が沸くのでおすすめです。そのほかにも、出力の高い電気式のケトルもよいでしょう。
もちろん、このためにケトルを買う必要はありませんが、注意したいのは鉄製のケトルを使用している場合。鉄製のケトルでお湯を沸かした場合、水の中に鉄分が流れ出して紅茶の中のタンニンと結合、紅茶の色が悪くなってしまいます。また、味自体も鉄の味が出てしまうため、風味が本来のものとは変わってしまいます。そのため、紅茶を淹れるときには、鉄製のケトルは避けたほうがよいでしょう。
2-3ポット
ポットは茶葉から紅茶を抽出するときに必要になります。このポットが紅茶を淹れるときには実はかなり重要。というのも、美味しい紅茶を淹れるためには、ポットの中で茶葉が踊るようにジャンピングすることが必要になりますが、容量が小さすぎる、形が悪いといった場合、紅茶の茶葉がポットの中で上手くジャンピングすることができず、上手く紅茶を抽出することができません。特に、ガラス以外の素材で出来ていると、きちんとジャンピングができているかどうか確認できないため、最初はガラス素材のポットを使用するのがおすすめです。
また、ポットを選ぶときに注意したいのが茶こし。茶こしは茶葉を切るときに必要になるもので、ポットについていると便利ですが、茶こしの形状によっては茶葉のジャンピングの妨げになることもあります。特に筒状の茶こしがついているポットは茶葉が動かなくなってしまうため、避けたほうがよいでしょう。上手くジャンピングを行うためには、ふたと茶こしが一体になっているものがおすすめです。
なお、紅茶のポットには抽出用のポットと、サーブ用のポットがありますが、最初は適量の抽出用のポットを用意して、一杯ごとに飲み切るのがよいでしょう。
2-4ティーカップ
少しゴージャスにティータイムを楽しみたいという場合、ティーカップに凝るのもおすすめです。特に、飲み口が薄い場合と厚い場合では紅茶の味にも影響があることもあります。といっても、高級なカップを揃える必要はありません。もし気に入ったものがあれば、薄手のものを買い求めて味の違いを確かめてみるのもよいでしょう。
2-5タイマー
紅茶の抽出時間を計るために必要になるのがタイマーです。紅茶は繊細なもので、長く置いておけばきちんと抽出できるかといえばそうではありません。長い時間茶葉をお湯に浸しておくと、紅茶本来の旨みや香りを損なってしまうこともあります。また、抽出時間が身近過ぎる場合、きちんと風味や香りを抽出することができません。
そのため、紅茶を抽出するときにはタイマーの使用がおすすめですが、特別に購入する必要はなく、キッチンタイマーや時計、スマホのタイマーなどで十分です。そのときは、三分、五分といった単位で計測できるものがおすすめです。
03将来の可能性って?
最初は趣味で紅茶を始めたとしても、それが高じて仕事にしてしまう人も少なくありません。では、紅茶にはどのような可能性があるのでしょうか。
まず多いのが、紅茶の知識を生かして、紅茶専門店や喫茶店などで働くことです。特に紅茶専門店では、知識豊富な人材を必要としています。最初はお店で経験を積み、やがては独立というのも夢ではありません。
また、紅茶には「紅茶アナリスト」「紅茶コーディネーター」などの資格もあります。これらは紅茶の知識や淹れ方の技能についての資格なので、もし紅茶関連のビジネスを始めたり、紅茶の趣味を仕事にしたりという場合、取得しておくと非常に役立つことでしょう。
04まとめ
趣味としても、将来の可能性を広げる意味でも、紅茶は注目の存在です。もし興味が出てきたという方は、思い切って紅茶について学んでみるのはいかがでしょうか。
まず多いのが、紅茶の知識を生かして、紅茶専門店や喫茶店などで働くことです。特に紅茶専門店では、知識豊富な人材を必要としています。最初はお店で経験を積み、やがては独立というのも夢ではありません。
また、紅茶には「紅茶アナリスト」「紅茶コーディネーター」などの資格もあります。これらは紅茶の知識や淹れ方の技能についての資格なので、もし紅茶関連のビジネスを始めたり、紅茶の趣味を仕事にしたりという場合、取得しておくと非常に役立つことでしょう。
この講座は!プロの監修を受けています!


- 紅茶の歴史と文化
- 紅茶の基本知識
- 紅茶を飲む時の正しいマナー
- 紅茶の道具と選ぶときのポイントとは
- 紅茶の茶葉の種類と特徴
- 紅茶の持つ健康効果とは
- 紅茶に関わる仕事と資格とは
- 家庭でできる紅茶の作り方と注意点
- 紅茶をブレンドする目的とブレンドの方法
- 初心者におすすめの紅茶と基本の淹れ方
- 水筒で紅茶を楽しむ為に、これだけは絶対に知っておきたい4項目
- 紅茶にレモンを入れると色が薄くなる不思議
- クリームダウンを防げば、アイスティーはもっとおいしくなる!
- 簡単にできる紅茶クッキーのレシピを3つご紹介
- 紅茶には身体にいい効能がいっぱい!
- 紅茶と相性のいいお菓子・食べ物について
- 紅茶のおとも「ミルクと砂糖」について
- 紅茶とハーブティーの違い
- 紅茶で服を染めてみよう!紅茶染めの楽しみ
- 紅茶を入れる道具についてのポイント
- 紅茶とお酒を合わせて楽しむ方法
- 紅茶を使ったカクテル
- ティーカップに持ち手が付いたわけ
- 紅茶を飲んでちょっと休憩する時に使ってみたい英語表現
- 紅茶に入れるもの
- 紅茶の保存容器いろいろ
- 初心者でも簡単!紅茶染め
- 紅茶の専門家になるための紅茶資格について
- 紅茶資格おすすめ7選!資格の種類や取得方法・活用法を解説!