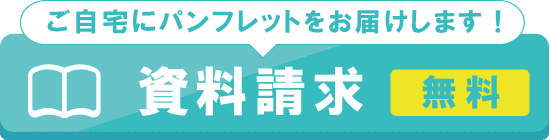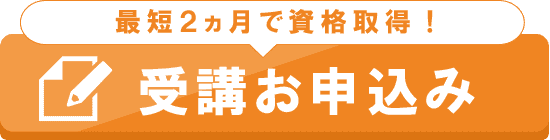お菓子の分類方法は?お菓子の用途別選び方や人気ランキング!
お菓子はその種類や用途によってさまざまな楽しみ方があります。
例えば、パーティーやイベント向けのお菓子、日常のおやつ、贈り物など、シーンに応じて選ぶことができます。
また、甘さや食感、見た目の美しさも重要な要素です。
そこで今回は、お菓子の分類方法は?お菓子の用途別選び方や人気ランキングについて詳しく解説していきます。
お菓子の世界はとても奥が深いもの。種類も非常に豊富で、一説には数万種類に及ぶとも言われています。さらにお菓子の分類には歴史や製法、原料などによっても分類することができます。今回はお菓子作りで用いられるお菓子の分類や名称についてご紹介します。

- 目次
- 1. お菓子の種類とは?基本的な分類方法
- 1-1. 洋菓子と和菓子の違い
- 1-2. 生菓子、焼き菓子、冷菓の種類
- 1-3. チョコレートやクッキー、タルトの特徴
- 2. お菓子の用途別選び方
- 2-1. 手土産に最適なお菓子
- 2-2. 特別なシーンに向けたお菓子ランキング
- 2-3. 家族や友人への贈り物に適した商品
- 3. 人気のあるお菓子のランキング
- 3-1. 2025年注目のお菓子
- 3-2. オンラインショップでの人気商品
- 3-3. SNSで話題のお菓子
- 4. お菓子の選び方:サイズとパッケージ
- 4-1. 贈答用の菓子折りの選び方
- 4-2. 個包装のメリットとデメリット
- 4-3. 家族用とパーティー用のサイズ感
- 5. お菓子の材料と風味の違い
- 5-1. 砂糖やバターが与える影響
- 5-2. 生地・スポンジの食感とコク
- 5-3. 原材料によるお菓子の特徴
- 6. お菓子の保存と配送方法
- 6-1. 冷菓と生菓子の保存方法
- 6-2. オンラインショップでの配送の注意点
- 6-3. 返品やキャンセルの手続き
- 7. お菓子作りの基本: レシピと方法
- 7-1. 簡単にできるお菓子レシピ集
- 7-2. オーブンを使った焼き菓子の作り方
- 7-3. 和菓子の作り方解説
- 8. お菓子の分類基準
- 9. 洋菓子の分類
- 10. 和菓子の分類
- 11. 用途別分類
- 12. まとめ
01お菓子の種類とは?基本的な分類方法
1-1洋菓子と和菓子の違い
お菓子の種類は大きく分けて「洋菓子」と「和菓子」に分類されます。 洋菓子は、主に小麦粉やバター、砂糖を使ったもので、ケーキやクッキー、パイなどが含まれます。 クリームやフルーツを使ったデザートが多く、見た目も華やかです。 一方、和菓子は、米粉やあんこ、もちなど、日本の伝統的な材料を使っています。 団子や大福、羊羹などが代表的で、季節感や文化を重んじた形状や味わいが特徴です。 このように、洋菓子と和菓子は使用する材料や製法、見た目に大きな違いがあり、それぞれの文化を反映しています。
1-1生菓子、焼き菓子、冷菓の種類
お菓子は大きく「生菓子」「焼き菓子」「冷菓」に分類されます。 生菓子は、主に新鮮な材料を使い、製造後すぐに食べるお菓子です。 焼き菓子は、オーブンで焼くことで製造されるお菓子です。 風味が凝縮され、さくっとした食感が楽しめます。 冷菓は、冷やして楽しむお菓子で、アイスクリームやゼリーが含まれます。 暑い季節にぴったりで、さっぱりとした味わいが特徴です。 このように、お菓子は製法や食感によって多様な楽しみ方ができます。
1-1チョコレートやクッキー、タルトの特徴
お菓子にはさまざまな種類があり、特にチョコレート、クッキー、タルトは人気があります。 チョコレートは、カカオ豆から作られる甘いお菓子で、ミルクチョコレートやダークチョコレート、ホワイトチョコレートなど多様な種類があります。 滑らかな口どけと豊かな風味が特徴で、トリュフや板チョコとしても楽しめるでしょう。 クッキーは、小麦粉、砂糖、バターを主成分とし、焼き上げたお菓子です。 サクサクした食感が魅力で、チョコチップクッキーやオートミールクッキーなど、様々なフレーバーがあります。 手軽に食べられるのも人気の理由です。 タルトは、サクサクの生地にクリームやフルーツを乗せたお菓子です。 フルーツタルトやチョコレートタルトがあり、見た目も美しく、甘さと酸味のバランスが楽しめます。 これらのお菓子は、それぞれ異なる味わいや食感で、多くの人に愛されています。
01お菓子の用途別選び方
1-1手土産に最適なお菓子
手土産に最適なお菓子は、相手の好みやシーンに合わせて選ぶと喜ばれます。 まず、洋菓子は華やかさがあり、特にケーキやクッキーは人気です。 次に、和菓子もおすすめです。 季節感を感じられる和菓子は、特にお茶うけにいいでしょう。 大福や羊羹は、甘さ控えめで食べやすく、年齢を問わず好まれます。 また、地域限定の特産品も良い選択肢です。 その土地ならではのお菓子は、話題にもなり、贈る相手に特別感を伝えられます。 例えば、地元の名物スイーツや伝統的なお菓子などが該当します。 最後に、アレルギーや食事制限に配慮することも大切です。 相手の好みや状況に応じて、お菓子を選ぶことで、より心のこもった手土産になります。
1-1特別なシーンに向けたお菓子ランキング
特別なシーンに向けたお菓子ランキングを紹介します。 1.ケーキ 誕生日や記念日には、デコレーションケーキが喜ばれます。 フルーツやクリームが美しいものを選ぶと、特別感が増します。 2.チョコレート バレンタインやホワイトデーには、高級なチョコレートが最適。 トリュフやアソートセットは、見た目も豪華でプレゼントにぴったりです。 3.和菓子 結婚式やお祝いには、季節を感じる和菓子がおすすめ。 上品な大福や羊羹は、特別な気持ちを伝えられます。 4.タルト お茶会や女子会には、フルーツタルトが人気。 色とりどりのフルーツが乗ったタルトは、華やかで見た目も楽しめます。 5.マカロン おしゃれなシーンには、マカロンが最適。 カラフルで可愛らしい見た目が、特別な気分を演出します。 これらのお菓子は、シーンに合わせて選ぶことで、特別な瞬間をより一層引き立ててくれます。
1-1家族や友人への贈り物に適した商品
家族や友人への贈り物に適したお菓子は、相手の好みやシーンに合わせて選ぶことが大切です。 1.焼き菓子 クッキーやマドレーヌは人気があります。 個包装のものを選べば、シェアしやすく、食べやすさも魅力です。 2.チョコレート 高級チョコレートの詰め合わせは特別感があります。 好きなフレーバーを選んで贈ると、喜ばれること間違いなしです。 3.和菓子 季節感を感じられる和菓子もおすすめ。 特に、ひな祭りや端午の節句に合わせた和菓子は、家庭の温かさを伝えます。 4.アイスクリーム 夏の贈り物には、アイスクリームのギフトセットが最適。 冷凍便で届けられるものを選ぶと、手軽に楽しんでもらえます。 5.フルーツタルト おしゃれで華やかなフルーツタルトは、集まりやパーティーにぴったり。 見た目の美しさが、贈り物としての価値を高めます。 これらのお菓子は、心を込めて選ぶことで、家族や友人への思いやりを伝えることができます。
01人気のあるお菓子のランキング
1-12025年注目のお菓子
2025年注目のお菓子ランキングを紹介します。 1.チョコレート 高級感あるアートチョコレートがトレンド。 見た目が美しく、味も多様なフレーバーが楽しめるものが人気です。 2.マカロン カラフルで可愛らしいマカロンは、インスタ映えも抜群。 新しいフレーバーや季節限定のものが続々登場しています。 3.和菓子 健康志向の高まりから、あんこや抹茶を使った和菓子が再評価されています。 特に、低糖質の和菓子が注目されています。 4.フルーツスイーツ 新鮮なフルーツを使ったタルトやゼリーが人気。 自然な甘さと彩りが魅力で、ヘルシー志向の人々に支持されています。 5.スナック菓子 グルテンフリーやビーガン対応のスナック菓子が増加中。 健康的でありながら、おいしさを追求した商品が注目されています。 これらのお菓子は、トレンドに敏感な人々に支持され、2025年のスイーツシーンを彩ることでしょう。
1-1オンラインショップでの人気商品
オンラインショップでの人気お菓子ランキングを紹介します。 1.チョコレートギフト 高級ブランドのチョコレートセットが大人気。 特にバレンタインやホワイトデーに、ギフトとして選ばれることが多いです。 2.焼き菓子アソート クッキーやマドレーヌ、フィナンシェなどの詰め合わせが人気。 個包装でシェアしやすく、贈り物にも最適です。 3.スナック菓子 健康志向から、グルテンフリーやオーガニックのスナック菓子が注目されています。 手軽に楽しめる点が魅力です。 4.和菓子セット 季節感を大切にした和菓子の詰め合わせが好評です。 特に抹茶やあんこを使った商品が人気です。 5.フルーツゼリー 自然な甘さと美しい見た目が特徴のフルーツゼリーが、特に夏に人気。おしゃれなパッケージも魅力です。 これらのお菓子は、オンラインで手軽に購入できるため、多くの人に支持されています。 特別な日や贈り物にもぴったりです。
1-1SNSで話題のお菓子
SNSで話題のお菓子ランキングを紹介します。 1.マカロン カラフルで可愛らしい見た目がSNS映えし、特に新しいフレーバーやデコレーションが注目されています。 インスタグラムでシェアされることが多いです。 2.チョコレートボンボン アートのような美しいチョコレートボンボンは、特別な贈り物にも最適。 ユニークなデザインやフレーバーが話題を呼んでいます。 3.フルーツタルト 新鮮なフルーツを使ったタルトは、その見た目の美しさから多くのいいねを集めています。季節ごとのアート感が人気です。 4.和菓子アート 季節感を大切にした和菓子がSNSで注目されています。 特に、可愛らしいデザインの大福やお干菓子がトレンドです。 5.スナック菓子 新しい味やユニークな食感のスナック菓子が次々と登場。 特に、期間限定商品は話題になりやすいです。 これらのお菓子は、見た目やユニークさがSNSでのシェアを促し、多くの人々に愛されています。
01お菓子の選び方:サイズとパッケージ
1-1贈答用の菓子折りの選び方
贈答用の菓子折りを選ぶ際には、サイズとパッケージに注意が必要です。 まず、サイズですが、贈る相手やシーンに応じて選ぶことが大切です。 少人数向けには小さめの菓子折り、大勢の方には大きめのものが適しています。 また、シェアしやすさも考慮に入れましょう。 次に、パッケージも重要です。 華やかで美しいデザインや季節感を感じさせるパッケージは、受け取ったときの喜びを増します。 高級感のある箱やラッピングが特別感を演出します。 さらに、内容にも気を配りましょう。 和菓子や洋菓子のアソートは、さまざまな好みに対応できるため安心です。 アレルギーや食事制限に配慮することも忘れずに。 最後に、用途を考慮することも大切です。 お祝い事やお礼、手土産など、贈る目的に合わせたお菓子を選ぶことで、より心のこもった贈り物になります。 これらのポイントを押さえて、素敵な菓子折りを選びましょう。
1-1個包装のメリットとデメリット
お菓子を選ぶ際、サイズやパッケージは重要なポイントです。 個包装のお菓子には、いくつかのメリットとデメリットがあります。 メリットとしては、まず衛生面が挙げられます。 個包装なので、手を汚さずに食べられ、シェアもしやすいです。 また、持ち運びが便利で、いつでもどこでも楽しむことができます。 さらに、食べ過ぎを防ぎやすいのもポイントです。 一方、デメリットも存在します。 個包装は、包装材が多くなり、環境に負担をかけることがあります。 また、コストがかかりやすく、同じ量のお菓子でも大袋に比べて高くなることがあるでしょう。 お菓子を選ぶ際は、これらの要素を考慮して、自分のライフスタイルや好みに合ったものを選ぶことが大切です。
1-1家族用とパーティー用のサイズ感
お菓子を選ぶ際、サイズやパッケージは重要なポイントです。 特に家族用やパーティー用では、適切なサイズ感が求められます。 家族用のお菓子は、日常的に楽しむことを考慮し、比較的大きなパッケージが便利です。 例えば、ファミリーパックや大袋は、コストパフォーマンスが良く、子どもたちや大人が気軽に食べられます。 また、ストックしやすく、買い物の回数を減らせるのも魅力です。 小分けの個包装や色とりどりの詰め合わせは、ゲストが選びやすく、シェアしやすいです。 適量を用意することで、無駄を減らし、みんなが楽しめる雰囲気を作ることができます。 お菓子選びでは、目的に応じたサイズ感を意識することが、楽しい時間を演出する鍵です。
01お菓子の材料と風味の違い
1-1砂糖やバターが与える影響
お菓子の味わいは、使用する材料によって大きく変わるでしょう。 特に砂糖とバターは、風味や食感に重要な役割を果たします。 砂糖は甘みを加えるだけでなく、焼き上げる際にカラメル化し、香ばしい風味を生み出します。 また、砂糖の量によってしっとり感やサクサク感が変わり、少ないとパサつきやすく多すぎるとべたつくことがあるでしょう。 バターはリッチな風味を与え、まろやかな口当たりを実現します。 バターの脂肪分が生地を柔らかくし、焼き上がりに風味を加えるのです。 冷やして固めるお菓子では、バターの質が特に重要で、風味や食感に影響を与えます。 砂糖とバターの使い方を工夫することで、さまざまな風味や食感のお菓子が楽しめます。 お菓子作りでは、これらの材料の特性を理解することが、理想の味を引き出すポイントです。
1-1生地・スポンジの食感とコク
お菓子の生地やスポンジの食感とコクは、使用する材料や作り方によって異なり、これらの要素は最終的な味わいや食べごたえに大きく影響します。 生地の食感は、小麦粉の種類や混ぜ方、焼き温度によって変わります。 強力粉を使うと、弾力のあるもちっとした食感が生まれ、一方、薄力粉を使うと、軽やかでふんわりとした仕上がりになるでしょう。 また、卵をしっかり泡立てることで、エアリーな食感が得られるでしょう。 コクは、バターやクリーム、卵の量によって決まり、特にバターはリッチな風味を加え、口の中でとろけるような感覚を生み出し、卵の黄身もコクを増し、しっとりとした仕上がりに寄与します。 これらの材料を適切に組み合わせることで、理想的な生地やスポンジが完成します。 お菓子作りでは、食感とコクのバランスを考えることが、満足度を高めるポイントです。
1-1原材料によるお菓子の特徴
お菓子の原材料は、その特徴や風味を大きく左右します。 使用する材料によって、味わいや食感が異なるため、選ぶ際にはそれぞれの特性を理解することが重要です。 小麦粉は、種類によって食感が変わります。 薄力粉は軽やかでふんわりした生地に、強力粉は弾力のある食感を生み出し、これによりケーキやパン、クッキーなど、さまざまなお菓子が作られるでしょう。 砂糖は甘さだけでなく、焼き色や食感にも影響します。 グラニュー糖はカリッとした食感を、粉糖はしっとりとした仕上がりをもたらし、バターや油脂はコクや風味を加え、生地をしっとりさせます。 バターは特有の香りを持ち、心地よい口溶けを実現し、卵は、風味を豊かにし、ふんわり感を増すでしょう。 また、乳製品はクリーミーさを加え、リッチな味わいを生み出します。 これらの原材料を組み合わせることで、さまざまなお菓子が楽しめます。 選ぶ材料によって、個性的なお菓子が作れるのが魅力です。
01お菓子の保存と配送方法
1-1冷菓と生菓子の保存方法
お菓子の保存方法は、種類によって異なります。 特に冷菓と生菓子は、それぞれに適した保存方法が重要です。 冷菓は、アイスクリームや冷たいデザートを指します。 冷蔵庫ではなく、必ず冷凍庫で保存することが大切です。 温度が上がると、食感が変わり、風味が損なわれることがあります。 冷凍時は、密閉容器に入れるか、ラップでしっかり包むことで、乾燥や異臭を防ぐことができるでしょう。 また、解凍する際は、冷蔵庫でゆっくり行うと、なめらかな食感が保たれます。 生菓子は、和菓子やケーキなどが含まれます。 これらは冷蔵庫で保存する必要があるでしょう。 直射日光を避け、湿気の少ない場所で保存することがポイントです。 生菓子は傷みやすいため、できるだけ早く食べることをお勧めします。 保存する際は、密閉容器に入れるか、ラップで包むことで、乾燥や風味の劣化を防げます。
1-1オンラインショップでの配送の注意点
オンラインショップでお菓子を購入する際、配送にはいくつかの注意点があります。 これを理解することで、品質を保ちながら楽しむことができます。 まず、温度管理が重要です。 特に生菓子や冷菓は温度に敏感で、常温での配送は避けるべきです。 冷蔵便や冷凍便を選ぶことで、品質を保ち、傷みを防ぐことができます。 次に、梱包の状態を確認しましょう。 お菓子が衝撃で壊れないよう、しっかりとした梱包がされているかをチェックします。 また、湿気から守るための防湿材や保冷材が使用されているかも重要です。 さらに、配送日時を指定できる場合は、受け取れる日を選ぶことが大切です。 長期間の不在で受け取れないと、品質が劣化する恐れがあります。 最後に、賞味期限にも注意を払いましょう。 特に短いものは早めに消費する必要があります。
1-1返品やキャンセルの手続き
オンラインショップでお菓子を購入した際、返品やキャンセルの手続きについて知っておくことは大切です。 これにより、トラブルを避けることができます。 まず、返品やキャンセルのポリシーを確認しましょう。 多くのショップでは、商品の到着後一定期間内に返品が可能ですが、条件が異なる場合があります。 特に食品の場合、未開封であることが求められることが多いです。 次に、返品手続きの方法を理解しておきましょう。 通常は、カスタマーサポートに連絡し、返品の理由を伝えます。 その後、必要な手続きを案内されるので、指示に従いましょう。 また、返送時の送料についても確認が必要です。 多くの場合、返品にかかる送料は自己負担となることがありますが、商品の不具合や誤配送の場合はショップが負担することがあります。 最後に、キャンセルのタイミングも重要です。 発送準備が整った後のキャンセルは難しいため、早めに手続きを行うことが推奨されます。
01お菓子作りの基本: レシピと方法
1-1簡単にできるお菓子レシピ集
お菓子作りは楽しく、簡単にできるレシピがたくさんあります。 ここでは、手軽に作れるお菓子のレシピをいくつか紹介します。 1. クッキー ・材料:小麦粉200g、砂糖100g、バター100g、卵1個、バニラエッセンス少々 ・方法:バターと砂糖を混ぜ、卵を加えます。 小麦粉をふるい入れ、混ぜたら、オーブンで180℃で約15分焼きます。 2. ホットケーキ ・材料:薄力粉200g、砂糖30g、牛乳150ml、卵1個、ベーキングパウダー小さじ2 ・方法:材料を混ぜ、フライパンで両面を焼きます。 お好みでメープルシロップをかけて楽しんでください。 3. ヨーグルトムース ・材料:ヨーグルト200g、生クリーム200ml、砂糖50g、ゼラチン5g ・方法:ゼラチンを水で溶かし、よく混ぜたヨーグルトと生クリームと合わせます。 冷やし固めて完成です。 これらは初心者でも簡単に作れるレシピです。
1-1オーブンを使った焼き菓子の作り方
オーブンを使った焼き菓子は、手軽で美味しいお菓子作りの楽しみです。 ここでは、基本的な焼き菓子の作り方を紹介します。 基本のスポンジケーキ ・材料 ・薄力粉 100g ・砂糖 100g ・卵 3個 ・バター 30g(溶かす) ・牛乳 30ml ・作り方 1.準備 オーブンを170℃に予熱します。 型にクッキングシートを敷くか、バターを塗ります。 2.卵を泡立てる ボウルに卵と砂糖を入れ、白っぽくなるまで泡立てます。 約5〜7分。 3.材料を混ぜる 薄力粉をふるい入れ、さっくりと混ぜます。 溶かしたバターと牛乳も加え、均一になるまで混ぜます。 4.焼く 生地を型に流し込み、170℃のオーブンで約25〜30分焼きます。 焼き上がったら、型から外して冷まします。 このスポンジケーキは、クリームやフルーツをトッピングして楽しめます。 オーブンで焼くお菓子は、香ばしい香りとともに、家庭で特別なひとときを演出します。
1-1和菓子の作り方解説
和菓子作りは、伝統的な技法とシンプルな材料を使った楽しいプロセスです。 ここでは、基本的な和菓子「大福」の作り方を紹介します。 大福の作り方 ・材料 ・白玉粉 100g ・水 120ml ・砂糖 30g ・あんこ(こしあんまたは粒あん)適量 ・片栗粉(まぶし用) ・作り方 1.生地を作る ボウルに白玉粉、砂糖、水を入れ、よく混ぜます。 ダマがなくなるまで混ぜるのがポイントです。 2.蒸す 混ぜた生地を耐熱皿に流し込み、ラップをして電子レンジで約2〜3分加熱します。 途中で混ぜ、再度加熱します。生地が透明感を持つまで加熱します。 3.成形 蒸した生地を片栗粉をまぶした台に取り出し、冷まします。 冷めたら、適当な大きさに分け、あんこを包みます。 手に片栗粉をつけながら、形を整えます。 4.仕上げ できあがった大福は、片栗粉をまぶしてくっつかないようにします。 この大福は、あんこの甘さともちもちした食感が楽しめる、シンプルで美味しい和菓子です。
01お菓子の分類基準
お菓子の分類には様々な目的があり、分類の方法も目的によって異なります。ではお菓子の分類にはどのような基準があるのでしょうか。
1-1大分類・中分類
お菓子は非常に大きく分けると、いつ日本に伝わったかという歴史的な背景によって分類されます。
それが、和菓子と洋菓子の違い。
ただし、和菓子といってもその中には日本に昔から伝わる伝統的なものや、奈良時代や平安時代に中国から伝来したもの、安土桃山時代にポルトガルなどから渡来したものなど、ルーツは様々。そのため、一般に和菓子というときには、明治以前から日本に存在したお菓子を指しています。
一方、洋菓子の場合は明治維新以降、欧米の文化が導入されると同時に日本に伝わったものを意味します。
といっても、これはあくまでもひとつの基準。
たとえばカステラは室町時代にポルトガル人によって長崎に伝えられたお菓子だと言われていますが、和菓子・洋菓子の双方に分類されることがあります。
また、お菓子には保存性による分類が行われることもあります。
これらは生菓子、半生菓子、干菓子などの分類です。
この分類は水分がどの程度お菓子に残っているかによる区別で、それによって扱いが変わって来るため、歴史的な背景による分類以上に重要なもの。
一般的には、水分が30パーセント以上のものは生菓子、30パーセントから10パーセントのものは半生菓子、10パーセント以下のものは干菓子と分類されます。
なお、食品衛生法ではさらにこの区別は厳密になります。食品衛生法の場合、生菓子は「出来上がり直後に40パーセント以上の水分を保有する菓子類」「あん、クリーム、ジャム、寒天やこれに類似するものを用いた菓子で、出来上がり直後に30パーセント以上の水分を保有するもの」とされています。
1-2小分類
お菓子についてさらに細かく分類する場合、「製造方法による分類」「原料による分類」「使用目的による分類」があります。
製造方法による分類は、お菓子を作るときに蒸す、焼くなどどのような製法を用いるかという分類。
原料による分類は、うるち米や豆など、原料の違いによる分類です。
使用目的による分類は、それが食事や副食に食べられるものか、おつまみに食べられるものかなどによる分類です。
02洋菓子の分類
それでは、洋菓子の分類を細かく見ていきましょう。
2-1一般分類
洋菓子は含有する水分量によって洋生菓子、洋半生菓子、洋干菓子の三種類に分類されます。
またそれぞれどのような生地や素材を使用するかによってさらに細かい分類が行われます。
2-2洋生菓子
洋生菓子は水分量が30パーセントを超えるもので、ケーキのほとんどがこれに当てはまります。
2-3スポンジケーキ類
ケーキの素材としてもっとも一般的なのがスポンジケーキです。このスポンジケーキ類にはショートケーキ、ロールケーキ、デコレーションケーキなどが含まれます。
2-4バターケーキ類
バターケーキは原料にバターを用いたケーキで、パウンドケーキやフルーツケーキ、バウムクーヘン、チーズケーキなどが含まれます。
2-5シュ-菓子類
シュー菓子類はシュー生地を用いたもので、シュークリームやエクレアなどを指しています。
2-6発酵菓子類
発酵菓子類は生地を発酵させる菓子で、サバランやデニッシュペストリー、ババなどが含まれます。
2-7フィュタ-ジュ類
フィュタ-ジュとは生地にバターの層を作りそれを重ねていくものです。フィュタ-ジュ類にはタルトやミルフィーユ、アップルパイなどが含まれています。
2-8ワッフル類
ワッフル類は小麦粉に砂糖を混ぜて焼き、厚く二つ折りにしたもの。いわゆるワッフルがこれに当てはまります。
2-9デザート菓子
デザート菓子はパンケーキやクレープ、ゼリー、ムースなど、いわゆるデザートとして一般的なお菓子です。
2-10料理菓子
料理菓子はお菓子と料理の中間に位置するもので、ピザパイ、ミートパイなどが当てはまります。
2-11洋半生菓子
洋半生菓子は洋菓子の中で含まれる水分量が10パーセントから30パーセントのもの。たとえばカップケーキなどが当てはまります。また、これまで見てきたように、使用する素材によってスポンジケーキ類やバターケーキ類、発酵菓子類、タルト・タルトレット類の一部もこの洋半生菓子となります。
洋半生菓子の代表的なものが砂糖漬類。フルーツなどを砂糖漬けすることで水分を抜き、保存性を高めたお菓子も洋半生菓子に分類されます。
2-12洋干菓子
洋干菓子は、洋菓子の中でも含まれる水分量が10パーセントを下回るものを指しています。
2-13キャンデー類
キャンデー類は砂糖を煮詰めて製造するあめ菓子で、ドロップやキャラメル、ヌガー、ゼリービーンズがここに分類されます。
2-14チョコレート類
チョコレート類は原料にチョコレートを使用したもので、通常の固形のチョコだけでなく、ビスケットなどをチョコでコーティングしたものも含まれます。
2-15チューインガム類
チューインガム類は糖類や香料などを原料としたガムベースを用いたお菓子のこと。味のついたガムや風船ガムなどを指しています。
2-16ビスケット類
ビスケット類は小麦粉にバター、卵、牛乳を使用して焼いたお菓子です。ビスケット類にはビスケットやクラッカー、ウエハース、甲板などが含まれています。
2-17スナック類
スナックとは軽い食事を意味している言葉で、スナック類にはポテトチップスやコーンチップスなど、塩味で間食に食べられるものを指します。
03和菓子の分類
和菓子にも洋菓子と同様、水分量や原料などによって様々な分類が行われます。
3-1一般分類
一方、和菓子の細かい分類はどのようなものなのでしょうか。
3-2和生菓子
和生菓子の分類は次のようになっています。
3-3もち菓子
もち菓子はもち米やうるち米、またはその加工品を主原料にしたもので、おはぎや大福、柏餅、羽二重持ちなどがあります。
3-4蒸菓子
蒸し菓子は原料を成形、蒸しあげて作るお菓子のことです。蒸し菓子にはかるかんやういろう、ゆべしなどがあります。
3-5焼き菓子
焼き菓子は材料を焼き上げることで作るお菓子で、どら焼きやきんつば、月餅、栗まんじゅうなどがあります。
3-6流し菓子
流し菓子は寒天や砂糖などを型に流して成形して作るお菓子です。ようかんや水ようかんなどがこれに当たります。
3-7練り菓子
練り菓子はあんやもち粉につなぎを加えて練り上げたもの。ねりきりやぎゅうひなどが含まれます。
3-8揚げ菓子
揚げ菓子は油で揚げて作るお菓子。あんドーナツなどが代表的な存在です。
3-9和半生菓子
和半生菓子の分類は次のようになっています。
3-10あん菓子
和半生菓子のあん菓子では石衣が有名です。石衣は半乾きの案に糖衣を掛けたお菓子です。
3-11おか菓子
おか菓子は別に作ったお菓子を組み合わせたもの。最中やすはま、かのこなどがおか菓子に当たります。
3-12焼き菓子
和半生菓子の焼き菓子では、桃山、黄味雲平などが有名です。
3-13流し菓子
和半生菓子の流し菓子にはより水分を抜いて日持ちするようにしたきんぎょくやようかんなどがあります。
3-14練り菓子
和半生菓子の練り菓子も、流し菓子と同じく練り菓子の水分を抜いたものです。
3-15砂糖漬け菓子
砂糖漬け菓子は甘納豆や文旦漬けなどがあります。
・和干菓子
和干菓子の分類は次のようになっています。
3-16打菓子
打菓子とは、栗粉やきな粉などに糖分を混ぜて木型に詰めて成型したもの。らくがんなどがこれに当たります。
3-17押し菓子
押し菓子は打ち菓子に練り案などを加えたもの。塩がまなどが押し菓子に含まれます。
3-18掛け菓子
掛け菓子は炒り豆やビスケットに甘味を掛けたもの。ひなあられなどが掛け菓子に分類されます。
3-19焼き菓子
焼き菓子は温度などを調整してより水分を少なくしたもの。丸ボーロや小麦せんべいなどです。
3-20あめ菓子
あめ菓子は砂糖に水飴を加えて固めたものです。いわゆる「飴」がここに分類されます。
3-21揚げ菓子
揚げ菓子は材料を油で揚げたもので、かりんとうなどがこれに当たります。
3-22豆菓子
豆菓子は豆を原料にしたもので、節分に用いる炒り豆などです。
3-23米菓
米菓はうるち米を用いたせんべいや、もち米を用いたあられなどが有名です。
04用途別分類
和菓子の中には、使用する用途によって呼び名が異なるものがあります。
4-1並生菓子
並生菓子は日常のお茶受けのお菓子に使われるもので、年間の行事などに使われるお菓子もここに分類されます。
4-2上生菓子
上生菓子は高価な生菓子で、自然の風景や季節を表現したものや、抽象的なデザインが用いられます。
4-3茶席菓子
茶席菓子は主に茶会に用いられるもので、生菓子と干菓子の両方が含まれます。
4-4式または引菓子
式または引菓子は結婚式や葬儀などに用いられる引き出物などのお菓子です。
4-5まき(蒔)菓子
まき(蒔)菓子は長唄や舞踊などの発表会のお土産として使われるお菓子です。
4-6工芸菓子
工芸菓子は観賞用のお菓子。食用の材料を用いて、写実的に表現が行われます。
01まとめ
お菓子は大きく分けて、和菓子、洋菓子、スナック菓子の3種類があります。
それぞれの用途に応じて選ぶことが重要です。
例えば、和菓子は贈り物やおもてなしに最適で、洋菓子はパーティーや特別な日にぴったり。
スナック菓子は手軽なおやつとして人気です。
また、人気ランキングでは、チョコレートやクッキー、ゼリーなどが上位にランクインしています。
用途やシーンを考慮して選ぶことで、より楽しめるお菓子ライフを送ることができます。
お気に入りのお菓子を見つけてみましょう。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。
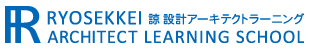
80,000人以上が受講申し込みしている諒設計アーキテクトラーニングの通信講座
あなたも早速受講して、資格を取得しましょう!
関連記事を見る
- 生クリームの選び方とは?ホイップクリームとの違いを徹底解説
- 賞味期間は?方法は?手作り焼き菓子の日持ちと保存方法について
- 手作り菓子を販売する方法とお菓子作り用語完全ガイド!
- お菓子作りに役立つクリームの種類とは?特徴や選び方・代替品!
- お菓子作りで失敗しないためのコツ!材料選びから焼き上げまで徹底解説
- ジャムとコンフィチュールの種類と違い?製法から使い分けまで!
- お菓子作りに使用する洋酒とは?お酒の役割や種類・メリットを解説!
- お菓子作りの基本道具と材料の選び方!初心者向けの道具!
- お菓子作りに使うバターとは?無塩バターを選んだほうがいい理由!
- お菓子の分類方法は?お菓子の用途別選び方や人気ランキング!
- お菓子作りに使用する砂糖とは?粉糖の種類と魅力を徹底解説!
- お菓子作りの資格と勉強方法について
1-1大分類・中分類
お菓子は非常に大きく分けると、いつ日本に伝わったかという歴史的な背景によって分類されます。
それが、和菓子と洋菓子の違い。
ただし、和菓子といってもその中には日本に昔から伝わる伝統的なものや、奈良時代や平安時代に中国から伝来したもの、安土桃山時代にポルトガルなどから渡来したものなど、ルーツは様々。そのため、一般に和菓子というときには、明治以前から日本に存在したお菓子を指しています。
一方、洋菓子の場合は明治維新以降、欧米の文化が導入されると同時に日本に伝わったものを意味します。
といっても、これはあくまでもひとつの基準。
たとえばカステラは室町時代にポルトガル人によって長崎に伝えられたお菓子だと言われていますが、和菓子・洋菓子の双方に分類されることがあります。
また、お菓子には保存性による分類が行われることもあります。
これらは生菓子、半生菓子、干菓子などの分類です。
この分類は水分がどの程度お菓子に残っているかによる区別で、それによって扱いが変わって来るため、歴史的な背景による分類以上に重要なもの。
一般的には、水分が30パーセント以上のものは生菓子、30パーセントから10パーセントのものは半生菓子、10パーセント以下のものは干菓子と分類されます。
なお、食品衛生法ではさらにこの区別は厳密になります。食品衛生法の場合、生菓子は「出来上がり直後に40パーセント以上の水分を保有する菓子類」「あん、クリーム、ジャム、寒天やこれに類似するものを用いた菓子で、出来上がり直後に30パーセント以上の水分を保有するもの」とされています。
1-2小分類
お菓子についてさらに細かく分類する場合、「製造方法による分類」「原料による分類」「使用目的による分類」があります。
製造方法による分類は、お菓子を作るときに蒸す、焼くなどどのような製法を用いるかという分類。
原料による分類は、うるち米や豆など、原料の違いによる分類です。
使用目的による分類は、それが食事や副食に食べられるものか、おつまみに食べられるものかなどによる分類です。
2-1一般分類
洋菓子は含有する水分量によって洋生菓子、洋半生菓子、洋干菓子の三種類に分類されます。
またそれぞれどのような生地や素材を使用するかによってさらに細かい分類が行われます。
2-2洋生菓子
洋生菓子は水分量が30パーセントを超えるもので、ケーキのほとんどがこれに当てはまります。
2-3スポンジケーキ類
ケーキの素材としてもっとも一般的なのがスポンジケーキです。このスポンジケーキ類にはショートケーキ、ロールケーキ、デコレーションケーキなどが含まれます。
2-4バターケーキ類
バターケーキは原料にバターを用いたケーキで、パウンドケーキやフルーツケーキ、バウムクーヘン、チーズケーキなどが含まれます。
2-5シュ-菓子類
シュー菓子類はシュー生地を用いたもので、シュークリームやエクレアなどを指しています。
2-6発酵菓子類
発酵菓子類は生地を発酵させる菓子で、サバランやデニッシュペストリー、ババなどが含まれます。
2-7フィュタ-ジュ類
フィュタ-ジュとは生地にバターの層を作りそれを重ねていくものです。フィュタ-ジュ類にはタルトやミルフィーユ、アップルパイなどが含まれています。
2-8ワッフル類
ワッフル類は小麦粉に砂糖を混ぜて焼き、厚く二つ折りにしたもの。いわゆるワッフルがこれに当てはまります。
2-9デザート菓子
デザート菓子はパンケーキやクレープ、ゼリー、ムースなど、いわゆるデザートとして一般的なお菓子です。
2-10料理菓子
料理菓子はお菓子と料理の中間に位置するもので、ピザパイ、ミートパイなどが当てはまります。
2-11洋半生菓子
洋半生菓子は洋菓子の中で含まれる水分量が10パーセントから30パーセントのもの。たとえばカップケーキなどが当てはまります。また、これまで見てきたように、使用する素材によってスポンジケーキ類やバターケーキ類、発酵菓子類、タルト・タルトレット類の一部もこの洋半生菓子となります。
洋半生菓子の代表的なものが砂糖漬類。フルーツなどを砂糖漬けすることで水分を抜き、保存性を高めたお菓子も洋半生菓子に分類されます。
2-12洋干菓子
洋干菓子は、洋菓子の中でも含まれる水分量が10パーセントを下回るものを指しています。
2-13キャンデー類
キャンデー類は砂糖を煮詰めて製造するあめ菓子で、ドロップやキャラメル、ヌガー、ゼリービーンズがここに分類されます。
2-14チョコレート類
チョコレート類は原料にチョコレートを使用したもので、通常の固形のチョコだけでなく、ビスケットなどをチョコでコーティングしたものも含まれます。
2-15チューインガム類
チューインガム類は糖類や香料などを原料としたガムベースを用いたお菓子のこと。味のついたガムや風船ガムなどを指しています。
2-16ビスケット類
ビスケット類は小麦粉にバター、卵、牛乳を使用して焼いたお菓子です。ビスケット類にはビスケットやクラッカー、ウエハース、甲板などが含まれています。
2-17スナック類
スナックとは軽い食事を意味している言葉で、スナック類にはポテトチップスやコーンチップスなど、塩味で間食に食べられるものを指します。
03和菓子の分類
和菓子にも洋菓子と同様、水分量や原料などによって様々な分類が行われます。
3-1一般分類
一方、和菓子の細かい分類はどのようなものなのでしょうか。
3-2和生菓子
和生菓子の分類は次のようになっています。
3-3もち菓子
もち菓子はもち米やうるち米、またはその加工品を主原料にしたもので、おはぎや大福、柏餅、羽二重持ちなどがあります。
3-4蒸菓子
蒸し菓子は原料を成形、蒸しあげて作るお菓子のことです。蒸し菓子にはかるかんやういろう、ゆべしなどがあります。
3-5焼き菓子
焼き菓子は材料を焼き上げることで作るお菓子で、どら焼きやきんつば、月餅、栗まんじゅうなどがあります。
3-6流し菓子
流し菓子は寒天や砂糖などを型に流して成形して作るお菓子です。ようかんや水ようかんなどがこれに当たります。
3-7練り菓子
練り菓子はあんやもち粉につなぎを加えて練り上げたもの。ねりきりやぎゅうひなどが含まれます。
3-8揚げ菓子
揚げ菓子は油で揚げて作るお菓子。あんドーナツなどが代表的な存在です。
3-9和半生菓子
和半生菓子の分類は次のようになっています。
3-10あん菓子
和半生菓子のあん菓子では石衣が有名です。石衣は半乾きの案に糖衣を掛けたお菓子です。
3-11おか菓子
おか菓子は別に作ったお菓子を組み合わせたもの。最中やすはま、かのこなどがおか菓子に当たります。
3-12焼き菓子
和半生菓子の焼き菓子では、桃山、黄味雲平などが有名です。
3-13流し菓子
和半生菓子の流し菓子にはより水分を抜いて日持ちするようにしたきんぎょくやようかんなどがあります。
3-14練り菓子
和半生菓子の練り菓子も、流し菓子と同じく練り菓子の水分を抜いたものです。
3-15砂糖漬け菓子
砂糖漬け菓子は甘納豆や文旦漬けなどがあります。
・和干菓子
和干菓子の分類は次のようになっています。
3-16打菓子
打菓子とは、栗粉やきな粉などに糖分を混ぜて木型に詰めて成型したもの。らくがんなどがこれに当たります。
3-17押し菓子
押し菓子は打ち菓子に練り案などを加えたもの。塩がまなどが押し菓子に含まれます。
3-18掛け菓子
掛け菓子は炒り豆やビスケットに甘味を掛けたもの。ひなあられなどが掛け菓子に分類されます。
3-19焼き菓子
焼き菓子は温度などを調整してより水分を少なくしたもの。丸ボーロや小麦せんべいなどです。
3-20あめ菓子
あめ菓子は砂糖に水飴を加えて固めたものです。いわゆる「飴」がここに分類されます。
3-21揚げ菓子
揚げ菓子は材料を油で揚げたもので、かりんとうなどがこれに当たります。
3-22豆菓子
豆菓子は豆を原料にしたもので、節分に用いる炒り豆などです。
3-23米菓
米菓はうるち米を用いたせんべいや、もち米を用いたあられなどが有名です。
04用途別分類
和菓子の中には、使用する用途によって呼び名が異なるものがあります。
4-1並生菓子
並生菓子は日常のお茶受けのお菓子に使われるもので、年間の行事などに使われるお菓子もここに分類されます。
4-2上生菓子
上生菓子は高価な生菓子で、自然の風景や季節を表現したものや、抽象的なデザインが用いられます。
4-3茶席菓子
茶席菓子は主に茶会に用いられるもので、生菓子と干菓子の両方が含まれます。
4-4式または引菓子
式または引菓子は結婚式や葬儀などに用いられる引き出物などのお菓子です。
4-5まき(蒔)菓子
まき(蒔)菓子は長唄や舞踊などの発表会のお土産として使われるお菓子です。
4-6工芸菓子
工芸菓子は観賞用のお菓子。食用の材料を用いて、写実的に表現が行われます。
01まとめ
お菓子は大きく分けて、和菓子、洋菓子、スナック菓子の3種類があります。
それぞれの用途に応じて選ぶことが重要です。
例えば、和菓子は贈り物やおもてなしに最適で、洋菓子はパーティーや特別な日にぴったり。
スナック菓子は手軽なおやつとして人気です。
また、人気ランキングでは、チョコレートやクッキー、ゼリーなどが上位にランクインしています。
用途やシーンを考慮して選ぶことで、より楽しめるお菓子ライフを送ることができます。
お気に入りのお菓子を見つけてみましょう。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。
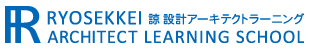
80,000人以上が受講申し込みしている諒設計アーキテクトラーニングの通信講座
あなたも早速受講して、資格を取得しましょう!
関連記事を見る
- 生クリームの選び方とは?ホイップクリームとの違いを徹底解説
- 賞味期間は?方法は?手作り焼き菓子の日持ちと保存方法について
- 手作り菓子を販売する方法とお菓子作り用語完全ガイド!
- お菓子作りに役立つクリームの種類とは?特徴や選び方・代替品!
- お菓子作りで失敗しないためのコツ!材料選びから焼き上げまで徹底解説
- ジャムとコンフィチュールの種類と違い?製法から使い分けまで!
- お菓子作りに使用する洋酒とは?お酒の役割や種類・メリットを解説!
- お菓子作りの基本道具と材料の選び方!初心者向けの道具!
- お菓子作りに使うバターとは?無塩バターを選んだほうがいい理由!
- お菓子の分類方法は?お菓子の用途別選び方や人気ランキング!
- お菓子作りに使用する砂糖とは?粉糖の種類と魅力を徹底解説!
- お菓子作りの資格と勉強方法について
3-1一般分類
一方、和菓子の細かい分類はどのようなものなのでしょうか。
3-2和生菓子
和生菓子の分類は次のようになっています。
3-3もち菓子
もち菓子はもち米やうるち米、またはその加工品を主原料にしたもので、おはぎや大福、柏餅、羽二重持ちなどがあります。
3-4蒸菓子
蒸し菓子は原料を成形、蒸しあげて作るお菓子のことです。蒸し菓子にはかるかんやういろう、ゆべしなどがあります。
3-5焼き菓子
焼き菓子は材料を焼き上げることで作るお菓子で、どら焼きやきんつば、月餅、栗まんじゅうなどがあります。
3-6流し菓子
流し菓子は寒天や砂糖などを型に流して成形して作るお菓子です。ようかんや水ようかんなどがこれに当たります。
3-7練り菓子
練り菓子はあんやもち粉につなぎを加えて練り上げたもの。ねりきりやぎゅうひなどが含まれます。
3-8揚げ菓子
揚げ菓子は油で揚げて作るお菓子。あんドーナツなどが代表的な存在です。
3-9和半生菓子
和半生菓子の分類は次のようになっています。
3-10あん菓子
和半生菓子のあん菓子では石衣が有名です。石衣は半乾きの案に糖衣を掛けたお菓子です。
3-11おか菓子
おか菓子は別に作ったお菓子を組み合わせたもの。最中やすはま、かのこなどがおか菓子に当たります。
3-12焼き菓子
和半生菓子の焼き菓子では、桃山、黄味雲平などが有名です。
3-13流し菓子
和半生菓子の流し菓子にはより水分を抜いて日持ちするようにしたきんぎょくやようかんなどがあります。
3-14練り菓子
和半生菓子の練り菓子も、流し菓子と同じく練り菓子の水分を抜いたものです。
3-15砂糖漬け菓子
砂糖漬け菓子は甘納豆や文旦漬けなどがあります。
・和干菓子
和干菓子の分類は次のようになっています。
3-16打菓子
打菓子とは、栗粉やきな粉などに糖分を混ぜて木型に詰めて成型したもの。らくがんなどがこれに当たります。
3-17押し菓子
押し菓子は打ち菓子に練り案などを加えたもの。塩がまなどが押し菓子に含まれます。
3-18掛け菓子
掛け菓子は炒り豆やビスケットに甘味を掛けたもの。ひなあられなどが掛け菓子に分類されます。
3-19焼き菓子
焼き菓子は温度などを調整してより水分を少なくしたもの。丸ボーロや小麦せんべいなどです。
3-20あめ菓子
あめ菓子は砂糖に水飴を加えて固めたものです。いわゆる「飴」がここに分類されます。
3-21揚げ菓子
揚げ菓子は材料を油で揚げたもので、かりんとうなどがこれに当たります。
3-22豆菓子
豆菓子は豆を原料にしたもので、節分に用いる炒り豆などです。
3-23米菓
米菓はうるち米を用いたせんべいや、もち米を用いたあられなどが有名です。
04用途別分類
和菓子の中には、使用する用途によって呼び名が異なるものがあります。
4-1並生菓子
並生菓子は日常のお茶受けのお菓子に使われるもので、年間の行事などに使われるお菓子もここに分類されます。
4-2上生菓子
上生菓子は高価な生菓子で、自然の風景や季節を表現したものや、抽象的なデザインが用いられます。
4-3茶席菓子
茶席菓子は主に茶会に用いられるもので、生菓子と干菓子の両方が含まれます。
4-4式または引菓子
式または引菓子は結婚式や葬儀などに用いられる引き出物などのお菓子です。
4-5まき(蒔)菓子
まき(蒔)菓子は長唄や舞踊などの発表会のお土産として使われるお菓子です。
4-6工芸菓子
工芸菓子は観賞用のお菓子。食用の材料を用いて、写実的に表現が行われます。
01まとめ
お菓子は大きく分けて、和菓子、洋菓子、スナック菓子の3種類があります。
それぞれの用途に応じて選ぶことが重要です。
例えば、和菓子は贈り物やおもてなしに最適で、洋菓子はパーティーや特別な日にぴったり。
スナック菓子は手軽なおやつとして人気です。
また、人気ランキングでは、チョコレートやクッキー、ゼリーなどが上位にランクインしています。
用途やシーンを考慮して選ぶことで、より楽しめるお菓子ライフを送ることができます。
お気に入りのお菓子を見つけてみましょう。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。
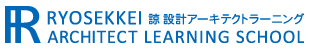
80,000人以上が受講申し込みしている諒設計アーキテクトラーニングの通信講座
あなたも早速受講して、資格を取得しましょう!
関連記事を見る
- 生クリームの選び方とは?ホイップクリームとの違いを徹底解説
- 賞味期間は?方法は?手作り焼き菓子の日持ちと保存方法について
- 手作り菓子を販売する方法とお菓子作り用語完全ガイド!
- お菓子作りに役立つクリームの種類とは?特徴や選び方・代替品!
- お菓子作りで失敗しないためのコツ!材料選びから焼き上げまで徹底解説
- ジャムとコンフィチュールの種類と違い?製法から使い分けまで!
- お菓子作りに使用する洋酒とは?お酒の役割や種類・メリットを解説!
- お菓子作りの基本道具と材料の選び方!初心者向けの道具!
- お菓子作りに使うバターとは?無塩バターを選んだほうがいい理由!
- お菓子の分類方法は?お菓子の用途別選び方や人気ランキング!
- お菓子作りに使用する砂糖とは?粉糖の種類と魅力を徹底解説!
- お菓子作りの資格と勉強方法について
4-1並生菓子
並生菓子は日常のお茶受けのお菓子に使われるもので、年間の行事などに使われるお菓子もここに分類されます。
4-2上生菓子
上生菓子は高価な生菓子で、自然の風景や季節を表現したものや、抽象的なデザインが用いられます。
4-3茶席菓子
茶席菓子は主に茶会に用いられるもので、生菓子と干菓子の両方が含まれます。
4-4式または引菓子
式または引菓子は結婚式や葬儀などに用いられる引き出物などのお菓子です。
4-5まき(蒔)菓子
まき(蒔)菓子は長唄や舞踊などの発表会のお土産として使われるお菓子です。
4-6工芸菓子
工芸菓子は観賞用のお菓子。食用の材料を用いて、写実的に表現が行われます。
- 通信講座の諒設計アーキテクトラーニング編集部
-
280講座以上の資格取得できる通信講座を運営する諒設計アーキテクトラーニング編集部が運営するコラムです。心理カウンセラー、ドッグトレーナー、リンパケアセラピストなど、実践的で需要の高い資格を提供しており、学習者は自分のペースで学べる柔軟なカリキュラムを受けることができます。専門知識を短期間で習得できるよう設計されており、仕事や趣味に役立つスキルを身につけることが可能です。
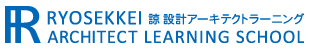
- 生クリームの選び方とは?ホイップクリームとの違いを徹底解説
- 賞味期間は?方法は?手作り焼き菓子の日持ちと保存方法について
- 手作り菓子を販売する方法とお菓子作り用語完全ガイド!
- お菓子作りに役立つクリームの種類とは?特徴や選び方・代替品!
- お菓子作りで失敗しないためのコツ!材料選びから焼き上げまで徹底解説
- ジャムとコンフィチュールの種類と違い?製法から使い分けまで!
- お菓子作りに使用する洋酒とは?お酒の役割や種類・メリットを解説!
- お菓子作りの基本道具と材料の選び方!初心者向けの道具!
- お菓子作りに使うバターとは?無塩バターを選んだほうがいい理由!
- お菓子の分類方法は?お菓子の用途別選び方や人気ランキング!
- お菓子作りに使用する砂糖とは?粉糖の種類と魅力を徹底解説!
- お菓子作りの資格と勉強方法について