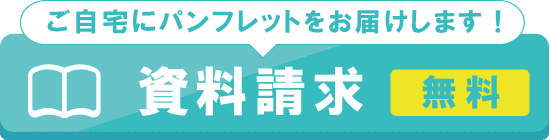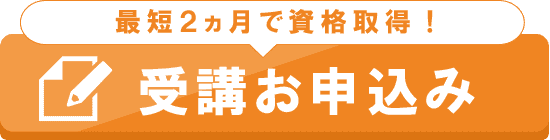知っておけばもっと楽しくなる!刺繍の歴史について
場所を問わず、手軽に楽しめる手芸として人気の刺繍。実は刺繍には非常に長い歴史があります。さらに世界各地で楽しまれている刺繍は、それぞれの場所で特徴も異なります。刺繍の歴史を知っておくと、趣味としての刺繍の楽しみも倍増するもの。今回は刺繍の歴史についてご紹介します。

- 目次
01刺繍の歴史
刺繍の歴史は非常に古いものだと言われています。いつどんな形で刺繍が行われるようになったのかという正確な起源は不明ですが、エジプトのピラミッドからもビーズ刺繍を行った布が発見されたこともあり、人類の文化とも深いつながりがあるとも言われています。
また、古代エジプトの時代には多くくのステッチが存在したとも言われています。
やがて刺繍は世界中に広がっていきますが、それぞれの国や文化によって、様々なバリエーションが生まれるようになりました。
02ヨーロッパ刺繍
刺繍の本場といえばヨーロッパ。ヨーロッパの刺繍は、単なる手芸というよりも、ひとつの文化として発展していきました。
2-1ヨーロッパ刺繍の歴史
古代エジプトから伝わった刺繍の技法は、古代オリエントで盛んに行われるようになり、バビロニア人によって様々なステッチが完成されたと言われています。さらに刺繍が大きな発展を迎えたのがローマ。ローマでは身分の高い人が用いる衣装などに刺繍が行われ、ヘレニズム文化、ビザンチン時代へと受け継がれていく中で、刺繍は僧院や宮廷など、文化の中心地でのシンボルとして重視されていきます。
さらに時代が進み、教会の影響力が強くなると、刺繍は進行を表すものとして珍重されるようになりました。
特に聖職者の衣装は重要な役割を与えられるようになり、儀式などでは豪華絢爛な刺繍を施した衣装が用いられるようになります。
十七世紀ごろになると、フランスの宮廷を中心として、刺繍は衣装だけでなく、装飾品や家具などにも広がっていきます。
というのも、当時の刺繍は高貴な身分を表すもの。手間や素材を集めるためには莫大な資金が必要で、それらの刺繍をぜいたくに使えるということは権力と富の象徴となり、特権階級のステイタスシンボルとしても認められるようになりました。
同時に織物貿易が行われるようになると、刺繍の技術はヨーロッパ全土に伝わっていきます。十八世紀に入ると、これらの豪華な刺繍は衰退、逆に簡単な刺繍が庶民の間に広がっていきます。
やがて刺繍は民族衣装にも用いられるようになり、民族ごとの文化や世界観などが加わり、さらに豊かな刺繍文化として現代に受け継がれていきます。
2-2ヨーロッパ刺繍の代表例
ヨーロッパ刺繍の代表的な存在がフランス刺繍。フランス刺繍はフランス人女性のたしなみとして広がったもので、あらゆる刺繍の基本として現代でも大きな人気があります。
また、民族衣装として有名なのがハンガリー刺繍。ハンガリー刺繍は白い布と白い糸で行い、布を立体的に見せるという特徴があります。
同じように民族衣装として知られているのがスイス刺繍。スイス刺繍は細かい花などをモチーフにしたかわいらしさが特徴です。
その他にも、布の織り糸を切り抜くことで透かしを作ったノルウェーのハルダンゲル地方で親しまれるハーダンガー刺繍なども高い人気を集めています。
03中国刺繍
エジプトとともに、刺繍のルーツのひとつと言われているのが中国刺繍。中国刺繍は広大な中国大陸の地方ごとに異なる特徴を持っています。
3-1中国刺繍の歴史
中国刺繍は約三千年という古い歴史を誇っていますが、その中でも重要な存在となるのがインド。
インドの人々はエジプトに綿を伝えたことでも知られていますが、金や銀を混ぜた華やかな刺繍糸もインドにルーツを持っています。
これらの豪華な糸が中国へと伝わり、身分の高い人々の衣装として愛用されるようになりました。
また、刺繍は官吏の服にも階級を表すものとして使用され、様々な動物や模様が描かれるようになります。これらは工芸品としても受け継がれ、現代でも中国の各地では美術品として精巧な刺繍が好まれています。
3-2中国四大刺繍
中国には、地域によって特徴の異なる刺繍が存在し、これらは「中国四大刺繍」と呼ばれています。現代でも、衣装やインテリア、舞台の装飾などに用いられることもあります。
3-3蘇州の「蘇繍」
中国の刺繍の中でももっとも古い歴史を持っていると言われるのが、蘇州で行われている「蘇繍」です。蘇繍は二千六百年以上の歴史があると言われ、宋の時代にはすでに大きな規模を誇るようになっていました。その後、明の時代に独特な技術などが確立、さらに広く人々の間に伝わるようになりました。清の時代になると、蘇繍の勢いは頂点を迎え、当時の皇帝やその親族の衣装にはほとんど蘇繍が使用されていたほど。
そんな蘇繍の特徴は両面に刺繍を施すことで、表から見ても裏から見ても糸の結び目が見えないようになっています。
さらに一本の絹糸を三十本以上に分けて刺繍を行うことで、繊細で上品な模様や色合いを表現、その美しさは「東方の真珠」として世界的にも知られています。
3-4広州の「粤繍」
広東省を中心とした広州で有名な刺繍が広州の「粤繍」です。粤繍はその地名から「広繍」と呼ばれることがあるもので、特に広東省に三百年前から行われていた刺繍を刺すこともあります。
粤繍の刺繍は模様が非常に複雑で、色鮮やかな点が特徴と言われています。そんな粤繍の中でも代表的な存在とされるのが汕頭刺繍です。
また、吸水性や吸湿性の高い綿や麻の生地を用いることが多く、実用性が高いことから、現在でも世界中に多くのファンを持っています。
3-5湖南の「湘繍」
湖南省長沙市を中心に、周辺の地域で多く行われている刺繍が「湘繍」です。湘繍は湖南省に古くから伝わっている刺繍に、蘇繍や粤繍の持っている特徴や長所を加えて完成されたもの。
絹の糸で縫い取りを行っているだけでなく、複雑な針の運び方を行うため、絵柄の力強さとリアリティのある質感を特徴としています。
モチーフとして用いられるのは古典的な中国画で、獅子や虎、花などが色彩豊かに描かれるため、ヨーロッパでも高い人気を誇っています。
3-6四川の「蜀繍」
四川省成都を中心に行われているのが「蜀繍」と呼ばれる刺繍です。蜀繍は「川繍」と呼ばれることもあり、写実的に表現された植物や動物などが知られています。特に色が鮮やかで立体感があり、絵画のように光や色を重視しているため、芸術品としても認められているものも少なくありません。
絵柄には人物や風景をモチーフにしたものも多く、大きな作品では様々な変化が楽しめることから、写真のようだと言われることもあり、根強い人気がある刺繍です。
04日本の刺繍
世界の中でも趣味として刺繍の人気が高いのが日本です。では、日本の刺繍にはどのような歴史があるのでしょうか。
4-1日本には中国から刺繍が伝わったと言われる
日本の刺繍のルーツは五世紀ごろ。インドから中国を経由して伝えられた「繍仏」が起源だと言われています。
「繍仏」とは、刺繍によって仏像を表現するもので、仏教が伝来するとともに、数多く作られるようになりました。その時代の代表的なものが、奈良の中宮寺に伝わる「天寿国曼荼羅繍帳」。これは若くして死去した聖徳太子を傷むために推古天皇が作らせたと伝わるもので、日本の刺繍の歴史の中でも特に重要な存在とされています。
また、日本の刺繍の発展に大きな役割を果たしたのが遣唐使。遣唐使は、奈良時代から平安時代にかけて、当時は唐と呼ばれた中国に派遣された使節団のことですが、この遣唐使が多くの刺繍を中国からもたらしたことで、日本の刺繍はさらに発展していきました。
4-2日本刺繍の種類
その後、日本の刺繍は着物や帯、日本人形、芸能の衣装などに用いられるようになり、全国へと広まっていきます。
日本刺繍の特徴は絹の糸を使い、両手を使って指していくことと、生産地によって呼び名や特徴が異なること。実は日本各地には、それぞれの特徴を持った刺繍が伝えられています。
4-3京繍(きょうぬい)
京都府京都市周辺で生産されている刺繍は「京繍」と呼ばれています。京繍のルーツは都が平安京に遷都された時代までさかのぼると言われています。
当時、平安京に都を移す際、京都に刺繍専門の職人ばかりを集めた「織部司」という機関が設置され、彼らが貴族の衣装や武士の武具などを作り始めたのがきっかけだと言われています。京繍の特徴は、絹や麻の布地に、絹糸、金糸、銀糸などを使用した豪華な点。京繍では十五種類以上の特殊な技法が使用され、それらの伝統は今日にも受け継がれています。
4-4加賀繍(かがぬい)
「加賀繍」は石川県金沢市を中心に行われている刺繍です。加賀繍の起源は室町時代初期。当時、仏教の不況と共に、仏具や僧侶の袈裟といった品々を作るため、京都から刺繍の技術が伝えられました。
当時の加賀は北海道と大阪とを結ぶ日本海海運の重要な存在だった北前船の寄港地として発展、豊かな経済力を背景に、加賀繍も独自の発展を遂げていきました。
加賀繍の特徴は絹糸や金糸・銀糸を使った立体感のある絵柄。加賀繍は現代でも芸能や生活の中に溶け込んだ存在です。
4-5江戸繍(えどぬい)
江戸繍は江戸を中心に広がった刺繍のことを指しています。江戸繍が生まれたのは江戸時代の中期。当時、経済力を蓄えた町人階級がそれまでの衣装に飽き足らず、染色技術に豪華な刺繍を加えて生み出した新しい着物が始まりとされています。
豪華な江戸繍は幕府によって取り締まりの対象となることもありましたが、江戸の繁栄とともに、江戸繍も受け継がれていきます。
江戸繍の特徴は、絵画のような精密さ。職人によって考え抜かれた糸や色合いなどによって、精密に縫い上げられていきます。
4-6東北で古くから伝わる刺し子
刺繍は貴族や宗教など特権階級だけのものではありません。日本の庶民に愛されてきた刺繍が「刺し子」。刺し子は着物や布などを長持ちさせるために生み出されたもので、青森県津軽の「こぎん刺し」、青森県南部の「菱刺し」、山形県庄内の「庄内刺し子」は、日本三大刺し子と呼ばれて、現在でも親しまれています。
05まとめ
世界各地に広がる刺繍文化。それぞれの国によって歴史も特徴も様々です。さらに現代では、アートとしての刺繍も生まれています。刺繍を楽しむときには、その背景の歴史や文化などを思い出してみてはいかが?
また、古代エジプトの時代には多くくのステッチが存在したとも言われています。
やがて刺繍は世界中に広がっていきますが、それぞれの国や文化によって、様々なバリエーションが生まれるようになりました。
2-1ヨーロッパ刺繍の歴史
古代エジプトから伝わった刺繍の技法は、古代オリエントで盛んに行われるようになり、バビロニア人によって様々なステッチが完成されたと言われています。さらに刺繍が大きな発展を迎えたのがローマ。ローマでは身分の高い人が用いる衣装などに刺繍が行われ、ヘレニズム文化、ビザンチン時代へと受け継がれていく中で、刺繍は僧院や宮廷など、文化の中心地でのシンボルとして重視されていきます。
さらに時代が進み、教会の影響力が強くなると、刺繍は進行を表すものとして珍重されるようになりました。
特に聖職者の衣装は重要な役割を与えられるようになり、儀式などでは豪華絢爛な刺繍を施した衣装が用いられるようになります。
十七世紀ごろになると、フランスの宮廷を中心として、刺繍は衣装だけでなく、装飾品や家具などにも広がっていきます。
というのも、当時の刺繍は高貴な身分を表すもの。手間や素材を集めるためには莫大な資金が必要で、それらの刺繍をぜいたくに使えるということは権力と富の象徴となり、特権階級のステイタスシンボルとしても認められるようになりました。
同時に織物貿易が行われるようになると、刺繍の技術はヨーロッパ全土に伝わっていきます。十八世紀に入ると、これらの豪華な刺繍は衰退、逆に簡単な刺繍が庶民の間に広がっていきます。
やがて刺繍は民族衣装にも用いられるようになり、民族ごとの文化や世界観などが加わり、さらに豊かな刺繍文化として現代に受け継がれていきます。
2-2ヨーロッパ刺繍の代表例
ヨーロッパ刺繍の代表的な存在がフランス刺繍。フランス刺繍はフランス人女性のたしなみとして広がったもので、あらゆる刺繍の基本として現代でも大きな人気があります。
また、民族衣装として有名なのがハンガリー刺繍。ハンガリー刺繍は白い布と白い糸で行い、布を立体的に見せるという特徴があります。
同じように民族衣装として知られているのがスイス刺繍。スイス刺繍は細かい花などをモチーフにしたかわいらしさが特徴です。
その他にも、布の織り糸を切り抜くことで透かしを作ったノルウェーのハルダンゲル地方で親しまれるハーダンガー刺繍なども高い人気を集めています。
03中国刺繍
エジプトとともに、刺繍のルーツのひとつと言われているのが中国刺繍。中国刺繍は広大な中国大陸の地方ごとに異なる特徴を持っています。
3-1中国刺繍の歴史
中国刺繍は約三千年という古い歴史を誇っていますが、その中でも重要な存在となるのがインド。
インドの人々はエジプトに綿を伝えたことでも知られていますが、金や銀を混ぜた華やかな刺繍糸もインドにルーツを持っています。
これらの豪華な糸が中国へと伝わり、身分の高い人々の衣装として愛用されるようになりました。
また、刺繍は官吏の服にも階級を表すものとして使用され、様々な動物や模様が描かれるようになります。これらは工芸品としても受け継がれ、現代でも中国の各地では美術品として精巧な刺繍が好まれています。
3-2中国四大刺繍
中国には、地域によって特徴の異なる刺繍が存在し、これらは「中国四大刺繍」と呼ばれています。現代でも、衣装やインテリア、舞台の装飾などに用いられることもあります。
3-3蘇州の「蘇繍」
中国の刺繍の中でももっとも古い歴史を持っていると言われるのが、蘇州で行われている「蘇繍」です。蘇繍は二千六百年以上の歴史があると言われ、宋の時代にはすでに大きな規模を誇るようになっていました。その後、明の時代に独特な技術などが確立、さらに広く人々の間に伝わるようになりました。清の時代になると、蘇繍の勢いは頂点を迎え、当時の皇帝やその親族の衣装にはほとんど蘇繍が使用されていたほど。
そんな蘇繍の特徴は両面に刺繍を施すことで、表から見ても裏から見ても糸の結び目が見えないようになっています。
さらに一本の絹糸を三十本以上に分けて刺繍を行うことで、繊細で上品な模様や色合いを表現、その美しさは「東方の真珠」として世界的にも知られています。
3-4広州の「粤繍」
広東省を中心とした広州で有名な刺繍が広州の「粤繍」です。粤繍はその地名から「広繍」と呼ばれることがあるもので、特に広東省に三百年前から行われていた刺繍を刺すこともあります。
粤繍の刺繍は模様が非常に複雑で、色鮮やかな点が特徴と言われています。そんな粤繍の中でも代表的な存在とされるのが汕頭刺繍です。
また、吸水性や吸湿性の高い綿や麻の生地を用いることが多く、実用性が高いことから、現在でも世界中に多くのファンを持っています。
3-5湖南の「湘繍」
湖南省長沙市を中心に、周辺の地域で多く行われている刺繍が「湘繍」です。湘繍は湖南省に古くから伝わっている刺繍に、蘇繍や粤繍の持っている特徴や長所を加えて完成されたもの。
絹の糸で縫い取りを行っているだけでなく、複雑な針の運び方を行うため、絵柄の力強さとリアリティのある質感を特徴としています。
モチーフとして用いられるのは古典的な中国画で、獅子や虎、花などが色彩豊かに描かれるため、ヨーロッパでも高い人気を誇っています。
3-6四川の「蜀繍」
四川省成都を中心に行われているのが「蜀繍」と呼ばれる刺繍です。蜀繍は「川繍」と呼ばれることもあり、写実的に表現された植物や動物などが知られています。特に色が鮮やかで立体感があり、絵画のように光や色を重視しているため、芸術品としても認められているものも少なくありません。
絵柄には人物や風景をモチーフにしたものも多く、大きな作品では様々な変化が楽しめることから、写真のようだと言われることもあり、根強い人気がある刺繍です。
04日本の刺繍
世界の中でも趣味として刺繍の人気が高いのが日本です。では、日本の刺繍にはどのような歴史があるのでしょうか。
4-1日本には中国から刺繍が伝わったと言われる
日本の刺繍のルーツは五世紀ごろ。インドから中国を経由して伝えられた「繍仏」が起源だと言われています。
「繍仏」とは、刺繍によって仏像を表現するもので、仏教が伝来するとともに、数多く作られるようになりました。その時代の代表的なものが、奈良の中宮寺に伝わる「天寿国曼荼羅繍帳」。これは若くして死去した聖徳太子を傷むために推古天皇が作らせたと伝わるもので、日本の刺繍の歴史の中でも特に重要な存在とされています。
また、日本の刺繍の発展に大きな役割を果たしたのが遣唐使。遣唐使は、奈良時代から平安時代にかけて、当時は唐と呼ばれた中国に派遣された使節団のことですが、この遣唐使が多くの刺繍を中国からもたらしたことで、日本の刺繍はさらに発展していきました。
4-2日本刺繍の種類
その後、日本の刺繍は着物や帯、日本人形、芸能の衣装などに用いられるようになり、全国へと広まっていきます。
日本刺繍の特徴は絹の糸を使い、両手を使って指していくことと、生産地によって呼び名や特徴が異なること。実は日本各地には、それぞれの特徴を持った刺繍が伝えられています。
4-3京繍(きょうぬい)
京都府京都市周辺で生産されている刺繍は「京繍」と呼ばれています。京繍のルーツは都が平安京に遷都された時代までさかのぼると言われています。
当時、平安京に都を移す際、京都に刺繍専門の職人ばかりを集めた「織部司」という機関が設置され、彼らが貴族の衣装や武士の武具などを作り始めたのがきっかけだと言われています。京繍の特徴は、絹や麻の布地に、絹糸、金糸、銀糸などを使用した豪華な点。京繍では十五種類以上の特殊な技法が使用され、それらの伝統は今日にも受け継がれています。
4-4加賀繍(かがぬい)
「加賀繍」は石川県金沢市を中心に行われている刺繍です。加賀繍の起源は室町時代初期。当時、仏教の不況と共に、仏具や僧侶の袈裟といった品々を作るため、京都から刺繍の技術が伝えられました。
当時の加賀は北海道と大阪とを結ぶ日本海海運の重要な存在だった北前船の寄港地として発展、豊かな経済力を背景に、加賀繍も独自の発展を遂げていきました。
加賀繍の特徴は絹糸や金糸・銀糸を使った立体感のある絵柄。加賀繍は現代でも芸能や生活の中に溶け込んだ存在です。
4-5江戸繍(えどぬい)
江戸繍は江戸を中心に広がった刺繍のことを指しています。江戸繍が生まれたのは江戸時代の中期。当時、経済力を蓄えた町人階級がそれまでの衣装に飽き足らず、染色技術に豪華な刺繍を加えて生み出した新しい着物が始まりとされています。
豪華な江戸繍は幕府によって取り締まりの対象となることもありましたが、江戸の繁栄とともに、江戸繍も受け継がれていきます。
江戸繍の特徴は、絵画のような精密さ。職人によって考え抜かれた糸や色合いなどによって、精密に縫い上げられていきます。
4-6東北で古くから伝わる刺し子
刺繍は貴族や宗教など特権階級だけのものではありません。日本の庶民に愛されてきた刺繍が「刺し子」。刺し子は着物や布などを長持ちさせるために生み出されたもので、青森県津軽の「こぎん刺し」、青森県南部の「菱刺し」、山形県庄内の「庄内刺し子」は、日本三大刺し子と呼ばれて、現在でも親しまれています。
05まとめ
世界各地に広がる刺繍文化。それぞれの国によって歴史も特徴も様々です。さらに現代では、アートとしての刺繍も生まれています。刺繍を楽しむときには、その背景の歴史や文化などを思い出してみてはいかが?
3-1中国刺繍の歴史
中国刺繍は約三千年という古い歴史を誇っていますが、その中でも重要な存在となるのがインド。
インドの人々はエジプトに綿を伝えたことでも知られていますが、金や銀を混ぜた華やかな刺繍糸もインドにルーツを持っています。
これらの豪華な糸が中国へと伝わり、身分の高い人々の衣装として愛用されるようになりました。
また、刺繍は官吏の服にも階級を表すものとして使用され、様々な動物や模様が描かれるようになります。これらは工芸品としても受け継がれ、現代でも中国の各地では美術品として精巧な刺繍が好まれています。
3-2中国四大刺繍
中国には、地域によって特徴の異なる刺繍が存在し、これらは「中国四大刺繍」と呼ばれています。現代でも、衣装やインテリア、舞台の装飾などに用いられることもあります。
3-3蘇州の「蘇繍」
中国の刺繍の中でももっとも古い歴史を持っていると言われるのが、蘇州で行われている「蘇繍」です。蘇繍は二千六百年以上の歴史があると言われ、宋の時代にはすでに大きな規模を誇るようになっていました。その後、明の時代に独特な技術などが確立、さらに広く人々の間に伝わるようになりました。清の時代になると、蘇繍の勢いは頂点を迎え、当時の皇帝やその親族の衣装にはほとんど蘇繍が使用されていたほど。
そんな蘇繍の特徴は両面に刺繍を施すことで、表から見ても裏から見ても糸の結び目が見えないようになっています。
さらに一本の絹糸を三十本以上に分けて刺繍を行うことで、繊細で上品な模様や色合いを表現、その美しさは「東方の真珠」として世界的にも知られています。
3-4広州の「粤繍」
広東省を中心とした広州で有名な刺繍が広州の「粤繍」です。粤繍はその地名から「広繍」と呼ばれることがあるもので、特に広東省に三百年前から行われていた刺繍を刺すこともあります。
粤繍の刺繍は模様が非常に複雑で、色鮮やかな点が特徴と言われています。そんな粤繍の中でも代表的な存在とされるのが汕頭刺繍です。
また、吸水性や吸湿性の高い綿や麻の生地を用いることが多く、実用性が高いことから、現在でも世界中に多くのファンを持っています。
3-5湖南の「湘繍」
湖南省長沙市を中心に、周辺の地域で多く行われている刺繍が「湘繍」です。湘繍は湖南省に古くから伝わっている刺繍に、蘇繍や粤繍の持っている特徴や長所を加えて完成されたもの。
絹の糸で縫い取りを行っているだけでなく、複雑な針の運び方を行うため、絵柄の力強さとリアリティのある質感を特徴としています。
モチーフとして用いられるのは古典的な中国画で、獅子や虎、花などが色彩豊かに描かれるため、ヨーロッパでも高い人気を誇っています。
3-6四川の「蜀繍」
四川省成都を中心に行われているのが「蜀繍」と呼ばれる刺繍です。蜀繍は「川繍」と呼ばれることもあり、写実的に表現された植物や動物などが知られています。特に色が鮮やかで立体感があり、絵画のように光や色を重視しているため、芸術品としても認められているものも少なくありません。
絵柄には人物や風景をモチーフにしたものも多く、大きな作品では様々な変化が楽しめることから、写真のようだと言われることもあり、根強い人気がある刺繍です。
4-1日本には中国から刺繍が伝わったと言われる
日本の刺繍のルーツは五世紀ごろ。インドから中国を経由して伝えられた「繍仏」が起源だと言われています。
「繍仏」とは、刺繍によって仏像を表現するもので、仏教が伝来するとともに、数多く作られるようになりました。その時代の代表的なものが、奈良の中宮寺に伝わる「天寿国曼荼羅繍帳」。これは若くして死去した聖徳太子を傷むために推古天皇が作らせたと伝わるもので、日本の刺繍の歴史の中でも特に重要な存在とされています。
また、日本の刺繍の発展に大きな役割を果たしたのが遣唐使。遣唐使は、奈良時代から平安時代にかけて、当時は唐と呼ばれた中国に派遣された使節団のことですが、この遣唐使が多くの刺繍を中国からもたらしたことで、日本の刺繍はさらに発展していきました。
4-2日本刺繍の種類
その後、日本の刺繍は着物や帯、日本人形、芸能の衣装などに用いられるようになり、全国へと広まっていきます。
日本刺繍の特徴は絹の糸を使い、両手を使って指していくことと、生産地によって呼び名や特徴が異なること。実は日本各地には、それぞれの特徴を持った刺繍が伝えられています。
4-3京繍(きょうぬい)
京都府京都市周辺で生産されている刺繍は「京繍」と呼ばれています。京繍のルーツは都が平安京に遷都された時代までさかのぼると言われています。
当時、平安京に都を移す際、京都に刺繍専門の職人ばかりを集めた「織部司」という機関が設置され、彼らが貴族の衣装や武士の武具などを作り始めたのがきっかけだと言われています。京繍の特徴は、絹や麻の布地に、絹糸、金糸、銀糸などを使用した豪華な点。京繍では十五種類以上の特殊な技法が使用され、それらの伝統は今日にも受け継がれています。
4-4加賀繍(かがぬい)
「加賀繍」は石川県金沢市を中心に行われている刺繍です。加賀繍の起源は室町時代初期。当時、仏教の不況と共に、仏具や僧侶の袈裟といった品々を作るため、京都から刺繍の技術が伝えられました。
当時の加賀は北海道と大阪とを結ぶ日本海海運の重要な存在だった北前船の寄港地として発展、豊かな経済力を背景に、加賀繍も独自の発展を遂げていきました。
加賀繍の特徴は絹糸や金糸・銀糸を使った立体感のある絵柄。加賀繍は現代でも芸能や生活の中に溶け込んだ存在です。
4-5江戸繍(えどぬい)
江戸繍は江戸を中心に広がった刺繍のことを指しています。江戸繍が生まれたのは江戸時代の中期。当時、経済力を蓄えた町人階級がそれまでの衣装に飽き足らず、染色技術に豪華な刺繍を加えて生み出した新しい着物が始まりとされています。
豪華な江戸繍は幕府によって取り締まりの対象となることもありましたが、江戸の繁栄とともに、江戸繍も受け継がれていきます。
江戸繍の特徴は、絵画のような精密さ。職人によって考え抜かれた糸や色合いなどによって、精密に縫い上げられていきます。
4-6東北で古くから伝わる刺し子
刺繍は貴族や宗教など特権階級だけのものではありません。日本の庶民に愛されてきた刺繍が「刺し子」。刺し子は着物や布などを長持ちさせるために生み出されたもので、青森県津軽の「こぎん刺し」、青森県南部の「菱刺し」、山形県庄内の「庄内刺し子」は、日本三大刺し子と呼ばれて、現在でも親しまれています。
05まとめ
世界各地に広がる刺繍文化。それぞれの国によって歴史も特徴も様々です。さらに現代では、アートとしての刺繍も生まれています。刺繍を楽しむときには、その背景の歴史や文化などを思い出してみてはいかが?
この講座は!プロの監修を受けています!

和歌山県出身で、現在は京都在住。
福祉の仕事をしながら趣味でハンドメイドをしていたが、刺繍の奥深さに惹かれ、2020年に「はるひな」を開業。
ハンドメイド誌にも多数掲載される。
現在は関西を中心にイベント出店も行っている。

- アクセサリーにも変身!余った刺繍糸の使い道
- こうすれば失敗しらず!刺繍図案の映し方やポイントについて
- これなら簡単!刺繍糸を針に通すコツと、刺繍の刺し始め・刺し終わりの方法について
- 覚えておきたい!刺繍糸の取り方・使い方について
- こんなに違う?刺繍糸の種類やメーカー別の違いについて
- こうすれば見た目もOK!刺繍糸の保管方法や整理の仕方について
- 接着芯って?刺繍に接着芯が必要な場合の選び方や貼り方のコツについて
- 刺繍を飾りたい!額の選び方や飾り方について
- 知っておけばもっと楽しくなる!刺繍の歴史について
- ここからスタート!刺繍の始め方と必要な道具について
- いつまでもきれいなままで!刺繍作品の仕上げ方やお手入れ方法について
- こんなにあった!刺繍に関する仕事と資格について
- 刺繍におすすめの生地は?布の特徴や選び方について